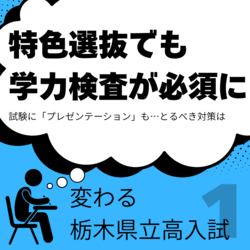硫黄島は、2400キロ離れた東京とサイパンのほぼ真ん中に浮かぶ。
戦争末期、日米双方の重要地点だった。
サイパンなどでの相次ぐ玉砕。本土を米軍機の爆撃圏内に収められた日本にとって、本土侵攻を阻む「最後の砦(とりで)」。米国にとっては効果的な爆撃の中継地点になる。
一日でも長く抵抗し本土攻略を遅らせる-。1944年6月、硫黄島に降り立った最高指揮官の陸軍中将、栗林忠道(くりばやしただみち)への至上命令だ。
全長18キロにも及ぶ地下壕(ごう)を島に張り巡らせた。奇襲をかけるゲリラ戦を企て、決行していった。
栗林が着任した1カ月後、太平洋上を航行する船内。
「硫黄島に向かっているなら、地獄行きだぜ」
海軍通信兵として乗っていた足利市島田町、17歳だった秋草鶴次(あきくさつるじ)さん(87)は、誰かの言葉を耳にした。行き先は知らされていなかった。
太平洋戦争史上、最激戦の一つといわれる36日間の攻防。日本軍の2万2千人、米軍の7千人が犠牲になり、日本軍の生き残りはわずか1千人。
秋草さんは、迷路のような地下壕をさまよい、散った戦友たちの心を思い続けている。
「断末魔の叫びの中、彼らは何を言いたかったのか」と。
硫黄島 ■ 「おれも連れて行ってくれ。一緒に死なせてくれ」
「なぜ生かされた」自問 秋草鶴次さん(87)(足利)

爆撃を受けて舞い上がる土砂に混ざって飛び散る人の頭や手足、肉片。
「おっかさーん」。いまわの際の叫びが、方々に波紋のように広がっていった。
1945年2月、硫黄島。通信兵だった秋草鶴次さんは、島中心部の小高い場所にあった玉名山送信所から、双眼鏡でつぶさに監視を続けた。
岩肌があらわで起伏の激しい地形。周囲22キロの島を取り囲んだ米艦船の艦砲射撃、空からの機銃掃射を浴び続けた。
視界を埋め尽くすほどに飛び交う銃弾。1分ごとに3人、部隊が1メートル進むたびに1人が死んでいく。敵の手に掛かりそうになると、手榴弾(しゅりゅうだん)や銃で自決する者も多かった。
3月になると、送信所は突如、火炎放射に襲われた。髪が焼け焦げ、腕は腫れ上がった。
志願兵だった秋草さんは、その矜持(きょうじ)を胸に刻んでいた。「死んでたまるか」。送信所壊滅を報告するため本部へ。地べたにへばりつき進んだ。
「伏せろ」。誰かの声を聞くや否や、艦砲射撃の砲弾が至近距離で爆発した。左手で右手をまさぐると、指3本がない。血まみれの左足は弾が貫通し動かなかった。
◇ ◇ ◇

圧倒的な米軍の攻勢に、じりじりと後退する日本軍。まもなく海軍による総攻撃が決まった。
「おれも連れて行ってくれ。一緒に死なせてくれ」。同年兵の仲間にそう懇願したが、手負いの身ではかなわなかった。
秋草さんが残された地下壕は暑さがむせかえり、排せつ物や遺体の腐乱臭が充満していた。食料の補給はおろか、一滴の水もなかった。
「地獄のような飢えとの戦い」。体に付いたノミやシラミ、傷口にわいたウジさえ口にした。
薄暗い壕で過ごし日時の感覚もなくなったころ、壕に液体が流れ込んだ。「水だ!」。兵士たちは飛び付いたが、その正体は油を混ぜた海水。米軍の火炎放射が放たれた。兵士は火だるまとなり倒れていった。
間一髪逃れたが、壕の中をさまよい、いつの間にか意識を失った。
気が付いたのは、グアム捕虜収容所のベッドの上。送信所が火炎放射を受けた3カ月後だった。
◇ ◇ ◇
生還後、執筆や講演活動を続けている。
「自分はなぜ生かされたのか」と常に自問する。「あの事実を語り継ぐためなのか。ならば、まだ足りないんじゃないのか」
「おっかさーん」と叫び死んでいった戦友が、その次に言いたかったことを、こう推し量る。
「必ず平和が来ると信じて戦った。だから、自分の分も幸せに生きてくれ」

 ポストする
ポストする