11月も残すところあと数日。今年も師走となります。一つのテーマや話題に沿って人やグループを紹介する月イチ企画「Tochigi 人びと」。今回は師走12月に忙しくなる人たちが登場します。「先生が走る」だけでなく忙しい人たちは多種多様な職業でいらっしゃるようです。
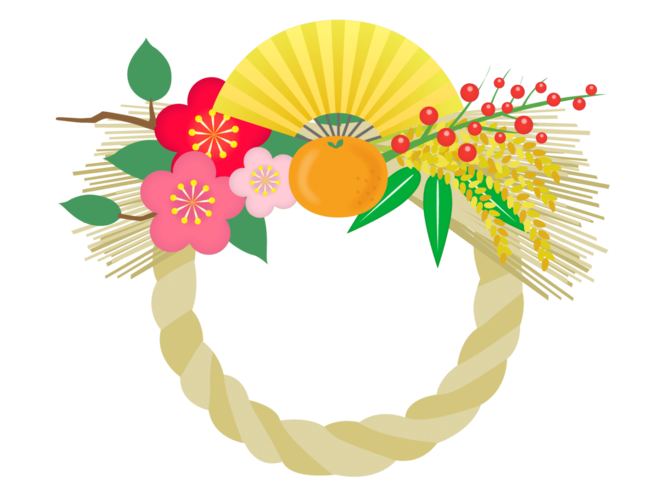
〝神宿る植物〟守り続ける

寺社仏閣で祭られているしめ縄や鈴尾。その素材となる麻の栽培をしています。出荷作業がピークになる11月から年末にかけてが一番忙しい時期。
麻引きと呼ばれる精麻にする出荷前の最後の工程は、美しく仕上げる重要な作業。「試行錯誤しながらコツをつかむまで苦労しました」と、若手麻農家として活躍する阿久津憲人さん。
黄金色に輝く精麻が作れるのは県の品種である「とちぎしろ」のみ。国内で流通している精麻の約8割が栃木県産です。収穫後に三日三晩、麻を寝かせる発酵体積法は江戸時代から続く方法で、この過程を行う農家はごく少数に。「昔からの麻文化を残していきたい」と、その製法にもこだわります。
麻栽培の免許を取得したのは6年前。古くからある伝統の継承と現代に合わせた麻製品の普及を目標に麻と向き合う日々で心に深く刻まれたのは、昨年執り行われた天皇即位の大嘗祭(だいじょうさい)。その時に徳島県で栽培した麻の収穫作業の一員として加われたこと。
「麻は神が宿る植物と信じられています。戦前日本では当たり前のように身近な存在でした。それが今は生産者が減り、貴重なものに。若手の麻農家の一人としてこの麻を守り続けることも僕の使命」

栃木の恵みで和洋中おせち

「農産直売所あぜみち」が毎年販売する人気のおせちが、今年は和・洋・中の三段重とパワーアップ。県内生産者から届く新鮮な野菜や国産の食材など厳選素材を使い、冷凍しない直接渡しの「栃木の恵みが凝縮された合計27品目のおせち」(1万6200円)です。
人気総菜コーナー「あぜでり」の上戸祭店、駅東店、鹿沼店各料理長が指揮をとり限定300食を12月28日から各店舗で調理を始め、31日に店頭で販売(要予約)。
オードブルなどを扱うテークアウトのエキスパートの上戸祭店秋葉料理長、洋食のエキスパートの駅東店本橋料理長、栄養士の資格を持つ鹿沼店の増子料理長、さらに駅東店の中華のエキスパートがレシピを作ります。それぞれの専門分野で、伝統的なおせちを生かしつつアレンジを加えたおせちを届けます。
30、31日にはおせちの単品販売もあり、31日は1〜2人前のミニお節も店頭に並びます。31日は午後1時まで。
(問)農産直売所あぜみち 滝の原店☎028・632・5431、駅東店☎028・680・5031、上戸祭店☎028・678・9687、鹿沼店☎0289・74・7030。

経験と勘で品質の良い花を

クリスマスシーズンに人気のポインセチア。同社ではジェスター、ウィンターローズ、イエロールクスなど5種類を作っています。現在、出荷作業のピーク。12月6日までに約5000鉢を全国の生花店へ出荷します。
1983(昭和58)年にシクラメンとサイネリアの生産を始め、現在は約60品種を作っています。ポインセチアは93(平成5)年に始めました。クリスマスに飾る風習が定着し、現在は冬の主力商品です。栽培期間は約6か月。6月に苗を植え、成育に合わせた温度や水の管理、光の調整に気を配ります。7月に行う剪定(せんてい)は、高さや形に影響が出る重要な作業。「ここが決めて。経験と勘が頼り」。約7000鉢の剪定を黒川さん1人で行います。
今夏は長雨の後、猛暑が続き、温度や水の調整に苦労しましたが、例年通りに仕上がりました。「家族や従業員に助けられ生産は順調。お客さまの期待に応え、品質の良い花を作ることにやりがいを感じます」。特大サイズの育成にも力を入れています。直径30㌢の10号鉢はボリュームがあり、百貨店やゴルフ場、ホテルのロビーなどに飾られます。家庭用サイズは、「花屋黒川」で販売。
(問)花屋黒川☎0285・44・2799。

男女ペアで〝爽やかな空間〟
店長 大塚力さん(49)

「お客さまにいつも爽やかな笑顔で対応し、掃除をした後には緑の風が吹くような爽やかな空間を提供したい」との思いから付けた社名。NPO法人日本ハウスクリーニング協会認定ハウスクリーニング士、一般社団法人日本家事代行協会家事代行アドバイザーの早乙女さんと同ハウスクリーニング士の大塚さんが、今年1月1日に創業。
大学病院での清掃業務経験を持つ早乙女さん。同社の最大のセールスポイントは、男女ペアで活動すること。一人暮らしから高齢の人まで安心して依頼することができ、男性だからこそできる力仕事と女性ならではの心配りの両方をカバー。1人で行うのと同じ時間をかけて丁寧に、さらにきめ細かく掃除をします。洗剤は、人と環境に優しいエコ洗剤とアルカリ電解水を使用します。
開業した仲間との情報交換や現場での経験が技術の向上につながります。「お客さまの『きれいになったね』と喜んでくれる声が一番うれしい」と話す2人。お客さんとのコミュニケーションを大切に笑顔と感動を届けられる掃除をしていきます。
(問)同社☎0285・37・6714。js3gm1@gmail.com

奇祭で一年のストレス発散

足利市の西北、745年開創の古刹(こさつ)最勝寺。大みそかの晩から新年にかけて、どちらも江戸時代から続くといわれる奇祭「悪口まつり」と「滝流しの式」が続けて行われます。
修験者が鳴らすほら貝の響きに導かれ、暗闇に包まれた山道を歩きながら、空に向かって腹の底から「ばかやろう」と叫んで一年のうっぷんを晴らす「悪口まつり」。疫病退散を願い悪夢を食べるという想像上の動物「バク」を拝んで「バク様」と呼んでいたものがいつしか「ばかやろう」に変化したと伝わります。
「不安や迷い、祈りや願いは人それぞれ。祭りに参加したり、初詣に訪れることで心の安らぎを得る人もいる。フェイスガードやマスクの着用などを徹底し、新型コロナ感染対策に十分に配慮して、なんとか実施したい」。祭りを支える7人のボランティアたちと今年は夏頃から準備を進めてきたといいます。
例年12月20日前後にすす払いが行われ、約2㌔に及ぶ参道の清掃、会場設営など祭りの準備は大詰めを迎えます。
31日午後10時半「悪口大声コンクール」、同11時「悪口まつり」、午前0時「滝流しの式」。
(問)同寺☎0284・21・8885。ホームページアドレスhttps://www.oiwasan.or.jp

 ポストする
ポストする












