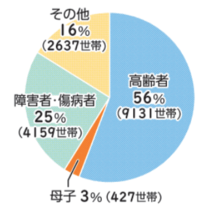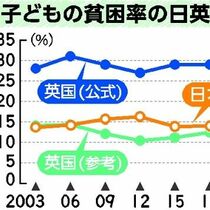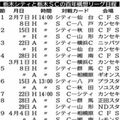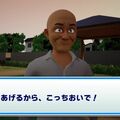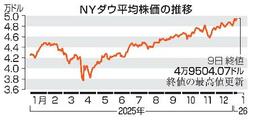新型コロナウイルス禍で収入が落ち込み、困窮を深めた家庭は少なくない。国の特例貸付制度を利用した県内の子育て世帯からは「貸付金だけでは家計が回らず、ほかの借金を重ねたが、返済もできずいまだ生活は苦しい」と窮状を訴える声が挙がる。
「コロナ禍の経済的な余波は今も大きい」。宇都宮市内で幼稚園児の長女と暮らす40代女性が声を落とす。
派遣社員だった夫は、コロナ禍の影響で2020年から仕事が激減し、精神疾患も患った。女性は幼い長女を療養中の夫に預けて働くことはできず、収入が完全に途絶えた。
夫は21年から特例貸付制度で計100万円超を借りたが、その後も病の影響で仕事がままならず、一家は銀行のカードローンなどで生活費を捻出した。
経済的な不安から夫婦間のいさかいが絶えず23年7月に離婚。女性には銀行や消費者金融からの借金100万円超が残った。
女性はその後、飲食店アルバイトなどで生計をつないできたが、自身のけがや娘の体調不良も重なり満足に出勤できず、月の生活費は4万円弱に落ち込んだ。市内団体の食料支援を受けながら綱渡りの生活を続けており「自己破産も考えないといけない」と嘆く。
一方、貸し付けの窓口業務を担った県内各市町の社会福祉協議会は、同制度を利用した世帯へのアンケートを行うなど生活状況の把握に注力している。
県東地区の社協は昨年、特例貸付制度の利用世帯へアンケートを実施した。返信のあった32件のうち、生活状況が「改善した」と回答したのはわずか2件のみだった。
同社協は回答者を中心に、こまめな電話や面談などを重ね生活状況を把握。都度、貸付金の返済猶予の相談を受け付けている。子育て世帯であれば、食費が家計を圧迫する家庭にフードバンクを紹介したり、学校への入学準備を手伝ったりするなど支援を広げた例もある。
同社協の担当者は「長くつながりを持ち続ける中で状況に合わせた情報提供やサポートをしていきたい」と話した。

 ポストする
ポストする