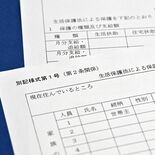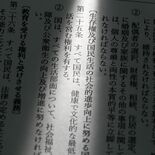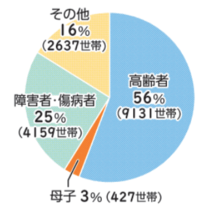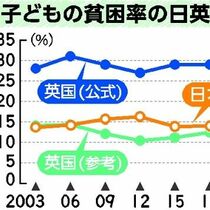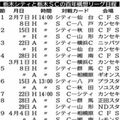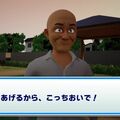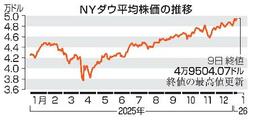■社会との分断 回避を
生活保護法4条は「保護は生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力、その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と定めている。つまり生活保護は、最低限度の生活をするための補足性の制度ということ。

補足性とは、自分の能力や資産を足していっても最低生活費に満たない場合に、その差額を支給することを指す。
自動車は資産になることや維持費がかかることなどから、原則所有することはできない。ただ、必ずしも車を手放さないと保護を受けられないということではない。例えば障害があって車がないと生活に支障が出る、公共交通機関へのアクセスが悪い、就労のために必要といったケースでは認められることもある。
県内では過去に那須町で保有が認められたことがある一方で、交通の便が良い市街地では認められないこともあり、地域間格差はあると言える。
ただ車がなくなってしまうと、子どもの部活動の送迎ができなかったり、買い物に行けなくなったりしてしまう。そうすると社会と分断されてしまう。相談を受ける職員はじっくりと話を聞いて、保有が認められるかどうかを判断してほしい。
福祉事務所が生活保護を申請した人の親族に援助が可能かどうかを問い合わせる扶養照会が、申請をためらう理由の一つになっている。民法で一定範囲内の近親者が扶養義務を負うと定められている以上、連絡が行くのはやむを得ない。ただDVや虐待があった場合などは照会が行われない。
精神疾患を発症するなど働けなくなってから申請、受給につながることが多い。そうではなく、まだ働く力があるという手前の段階で使える制度であるべきだ。

 ポストする
ポストする