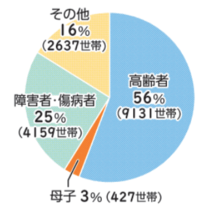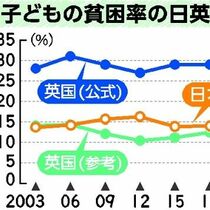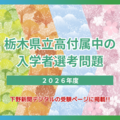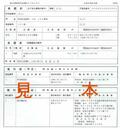■包括支援 困り事に合わせ援助
貧困などで養育環境に課題を抱える家庭の子どもたちを支える「子どもの居場所」を増やそうと、国は新年度、居場所の運営費用などを補助する「児童育成支援拠点事業」を始める。分科会では、トークセッションを実施しながら、こども家庭庁の担当者が事業について説明した。
トークセッションにはこども家庭庁成育局成育環境課の山口正行(やまぐちまさゆき)課長、自治体、支援団体の関係者4人が登壇した。
児童育成支援拠点事業は、子どもに安心安全な居場所を提供し、生活習慣形成のサポートや学習支援、食事、課外活動の提供、学校や医療機関との連携、保護者の相談対応など包括的な支援を行う。実施主体は市区町村で、補助率は国と県、市区町村の3分の1ずつ。開所日数は週3日以上。専門職の配置や送迎の有無などにも応じて補助の加算がある。

山口課長は「居場所をつくることによって、そこに来た子どものニーズが分かるようになる」と市区町村が居場所をつくる利点を挙げた。市区町村には子育て支援のメニューがたくさんあるため、子どもの困り事に応じて居場所以外のサービスを紹介したり、支援事業の実施を検討したりすることもできると訴えた。
一方、事業実施にこぎ着けるために支援者側ができる対応について問われると、「市区町村の担当職員がやりたいと思っていても、予算を得るために(事業の意味を)財政課へ説明しないといけない。そのために、支援者である皆さんは(居場所の効果などの)材料を提供してもらいたい」と促した。
最後に、「居場所づくりの考え方を国として示して取り組んでいるので、ぜひ積極的に進めていただきたい」と呼びかけた。

 ポストする
ポストする