
地震や台風、豪雨など、私たちの暮らしを脅かす自然災害は、いつどこで起きても不思議ではありません。いざという時に慌てず、家族や地域とともに命を守るためには、日頃からの備えが欠かせません。防災士の指導をもとに行った避難所運営体験の様子のほか、防災士の役割などについて紹介します。「備えあれば憂いなし」。9月は防災月間です。この機会に、家族で防災について話し合ってみませんか。

「気付く力」が重要
40人、避難所支援と運営学ぶ
「誰一人取り残さない」
パルティ防災フォーラム
「パルティ防災フォーラム2025」(県主催)が8月28日に開かれ、男女共同参画の視点で取り組む避難所支援の講義と避難所運営の実践に約40人が参加しました。男女共同参画地域みらいねっと(青森)代表理事の小山内世喜子さんの講義「災害関連死ゼロをめざす」と「実践!みんなにやさしい避難所運営」体験が行われました。


被災地支援で大切なことは「災害関連死ゼロ」と「誰一人取り残さない、ジェンダー視点からみた被災者支援」だと小山内さんは話します。災害関連死を防ぐためには、生活者の視点から〝気付く力〟が重要であり、平常時からの平等・多様性のある地域づくりの必要性を訴えます。


参加者の一人、防災士の資格を持つ宇都宮市の根上均さん(64)は「東日本大震災の時、避難所の人たちに物資や郵便物を届ける中で、防災への意識を持ちました。いざとなったらできるのかという思いがあり参加しました」
避難所づくりでは、県避難所運営マニュアル作成指針を参考に本部、女性・子育て・高齢者の各要配慮者支援班、保健・衛生班の5班に分かれて活動。要配慮者を重点に動線を考えたレイアウトや衛生対策などに取り組みました。

その中で、被災者に重要な情報を分かりやすく掲示する、段ボールベッドの必要性、トイレに凝固剤を活用する―などがポイントとして挙げられました。
佐野市の猿橋洋子さん(63)は「みんなで意見を出し合いました。椅子の向きひとつにしても、その人のためにという思いが大切。学んだことを地元でも生かしていけたら」と話していました。

災害に備える「防災士」知識と実行力
地域の命守るために
社会のさまざまな場で防災力を高める活動を行っているのが「防災士」です。〝自助〟〝共助〟〝協働〟を理念とした意識を持ち、知識と技能を習得した人々です。

県内には5197人(2025年7月末現在)の防災士がいて、そのうち217人が県防災士会に所属しています。地域において、災害に備える「声かけ役」であり、いざという時に率先して動く実動部隊でもあります。
防災士は「日本防災士機構」が認証する民間の資格です。あくまでも自発的な防災ボランティア活動を行うものですが、その活動は「命を守る力」として地域社会に深く根差しています。
普段は家庭や職場で備蓄や耐震補強などを実践。避難所訓練や災害図上訓練などをリードします。また、自主防災組織への参加をはじめ、出前講座などを通して地域の防災ネットワーク強化に尽力します。
災害時には、初期対応のリーダーとして避難誘導や初期消火、救助活動などを率先して行います。避難所の開設では混乱を防ぎ、安心できる場づくりを担います。
地域からの信頼は大きく、被災地においても災害時の即戦力として活躍する力強い存在です。
●「防災士資格」を取得するためには
❶日本防災士機構が認証した研修機関が実施する「防災士養成研修講座」を受講する。
❷日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」を受験し、合格する。
❸各地域の消防署などが実施する普通救命講習(3時間以上)などを受講する。
県内では鹿沼、小山、大田原市のほか作新学院大学が防災士養成研修実施機関になっています。
詳しくは同機構のホームページを。
さくらの防災士渡邉さん一家
防災リュックの備品確認忘れず
9月1日の防災の日に、さくら市在住の防災士・渡邉文香さん(38)と家族は、あらためて防災リュックの備品を確認しました。
自宅近くを流れる荒川。2019年の東日本台風時、サイレンが鳴り響く中で、5歳と2歳だった息子を抱え「避難するのにもどうすればよいのかが分からなかった」と振り返ります。そして、その経験から、防災士の資格を取ることを決断しました。
渡邉さんは防災用品で「必ず備えておくべきものは携帯トイレです」と力説します。
また、子どもが食べられる防災食を準備し「一度、一緒に食べてみるのも大切ですね」と日頃の取り組みについて話します。











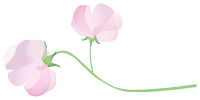
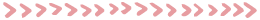
 028-625-1847
028-625-1847


