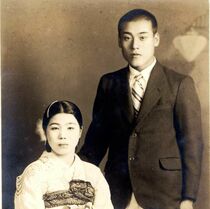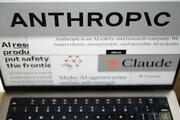県都が炎に包まれた1945年7月12日夜の宇都宮空襲。戦争を語り継ぐキャンペーン「#あちこちのすずさん」に投稿を寄せた宇都宮市、郷間恒男(ごうまつねお)さん(84)は当時、宇都宮二荒山神社近くの防空壕(ごう)に一人逃げ込んだ。「同じ経験を子どもたちにさせたくない」。あの日から77年。郷間さんと12日、現場を歩いた。
「街並みは変わったけど、土の感じはあの頃と変わってないね」。県庁近くの赤門通りから見える二荒山神社の東側擁壁。やぶに隠れた防空壕(ごう)の入り口を懐かしそうに見つめ、郷間さんは記憶をたどった。
当時7歳だった。町の警防団が手作業で掘った高さ1メートルほどの空洞。近所に住んでいた郷間さんは放課後、小石を外に運び出すのを手伝った。「二つ造って中をつなぐ予定だったが、完成前に空襲が来たんだ」
7月12日の夜は雨だった。「空襲だ!」と叫ぶ父の声で目覚めた。ランドセルを背負い、防空壕(ごう)に駆け込んだ。「中は人でいっぱいで、押しつぶされそうなほどだった」。
気付けばランドセルは背中からなくなっていた。「一人でも多くの人を避難させるために、壕に入る時に誰かに投げられてしまったのかもしれない」
降り注ぐ焼夷(しょうい)弾。次第に火の手が迫り、壕から出ざるを得なくなった。はしごで擁壁を上ると、東の空が赤く染まるのが見えた。
同神社境内で母と幼い妹に再会し、火のない方へと、西参道から県庁前を通り戸祭方面へ一緒に避難した。現昭和小付近の民家の軒下で雨宿りしていると、家の中へ迎え入れられ、一夜を明かすことができた。「とてもありがたかった」
翌日は「どこが家だったか分からないくらい何もなかった」。焼け野原が広がっていた。焼け跡から砂糖を入れる一斗缶が出てきたので、開けると全てべっこうあめになっていた。「甘い物が貴重だったので、家族と大切にいただいた」
77年がたった今、郷間さんは「無差別に住民が攻撃される」ウクライナ侵攻の状況を宇都宮空襲に重ねる。「突然日常が奪われる経験を子どもたちにさせたくない」とつぶやいた。
郷間さんの案内がなければ、壕の場所に気づくことはなかった。死と隣り合わせだった夜、命をつなぐために逃げた道のりを一緒にたどりながら、「あの戦争を忘れてはいけない」という強い思いを受け止めた。

 ポストする
ポストする