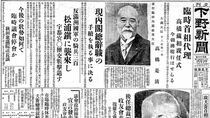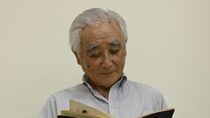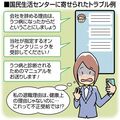1944(昭和19)年8月23日、女子挺身(ていしん)勤労令が公布、施行された。国家総動員法に基づき、それまで地域や学校で自主的に組織していた女子挺身隊を義務化。内地に住む12~40歳の未婚女性が、軍需工場などでの勤労奉仕に総動員されることになった。
背景にあったのが、労働力不足だ。男性の多くが学徒出陣も含め、戦地に駆り出される中、貴重な労働力として国内の生産体制は女性に任された。
本紙は、宇都宮市にあった関東工業の軍需工場で勤労奉仕していた坂本依子さんの手記を「女子挺身隊員の記録」と題して掲載。地元村長の激励を受け「私たち若い乙女たちは、全身を震わせて喜んでどんな仕事でもやり抜きましょうと誓った」と記している。
つるはしを担いでの防空壕(ごう)掘りでは音を上げる仲間もおり、「悔しかったら米英を恨めばいいじゃない」と励まし合い、しばらくすると機械作業も難なくこなせるようになったとも報告している。
こうして義務化された女子挺身隊だが、戦局が悪化する中で、本土決戦に備えた国民義勇隊へと統合されていくことになる。

 ポストする
ポストする