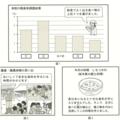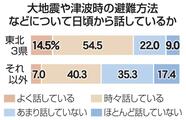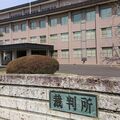「父に抱き締められた思い出はない。仕事や青年団で家を空けがちな人だった」
那須烏山市曲畑(そりはた)の自宅で7月下旬、渡辺美樹(わたなべよしき)さん(87)は幼少期を思い起こし、複雑な表情を見せた。
79年前、父佐登美(さとみ)さんを亡くした。子ども5人を残し、フィリピンで戦病死した。35歳だった。
太平洋戦争の戦況が悪化していた1944年ごろ、父は召集された。当時は「そんなに深刻なことじゃないと思っていた」。新聞紙で作った日の丸の旗を振って見送った。
数カ月後、父の国外出兵が決まった。神奈川県の横須賀港で面会を許されたが、「行ってもつまらない」と留守番をすることにした。父と会える最後の機会になるとは、想像すらしていなかった。
終戦後しばらくして父の死を知った。大黒柱を失った一家。母を助けるため農業を手伝った。農繁期は作業をしてから中学校へ通った。星明かりを頼りに3時間かけ、牛車を引いて葉タバコを納めに行ったこともあった。
連日続く農作業の傍ら家族の勧めもあり、なんとか高校に進学した。だが、今度は母が病に倒れた。学業どころではなくなった。長男としての責任感があった。身を粉にして働いた。
間もなく母は帰らぬ人となった。48歳だった。
妹や弟の親代わりにもなった。「父と母がいたらと思う暇もないぐらい、当時は精いっぱいだった」
終戦から55年がたった2000年。「どういうところで父は亡くなったのか。それを知りたい」。渡辺さんは厚生労働省の慰霊巡拝に参加し、フィリピンの離島を訪れた。
戦没地を巡りながら、他の参加者と歌った童謡「ふるさと」。母国に帰れず家族を残して亡くなった父を思うと、涙が止まらなかった。「それが父を思って流した初めての涙でした」
年を重ねた今、人生を振り返って思い出すのは、生きるために必死だった青春時代。「金もない、親もいない。とにかく寂しかった」。渡辺さんは声を震わせた。
今夏、戦後の体験を記した渡辺さんの手紙が下野新聞社に届いた。苦労の日々がつづられ、最後はこう締めくくられていた。
「戦争の傷跡は続いています」
親亡き後、生き抜くために負った心の傷は今も癒えないでいる。

 ポストする
ポストする