「みなみちゃん」というかわいらしい名前を持つJAなす南の特産カボチャが出荷シーズンを迎えています。JAなす南のもう一つの特産カボチャである「中山かぼちゃ」と「みやこかぼちゃ」の交配種で、約20年前に旧南那須町で栽培が始まったことからそう命名されました。まるでハートのような形状と、濃い緑色の果皮、鮮やかなオレンジ色の果肉、そして何より食味の良さが特徴です。
▽安全安心にも尽力
「今年は霜やひょうによる被害もなく、順調に育ってくれました。いいカボチャができたと思いますよ」。「みなみちゃん南瓜(かぼちゃ)部会」(部会員43人)の部会長を務める越雲徹(こしくもとおる)さん(68)=那須烏山市熊田=は、そう言って顔をほころばせました。▽特別感をアピール

こうした実情を受け、今年は出荷で新機軸を打ち出しました。それは、これまでの最上級の「秀」の上にさらに格上の「極(きわみ)」というクラスを設けて出荷する販売スタイルです。石川さんは「ほかの産地との差別化を図り、消費者の皆さんに対してプレミアム感をアピールするのが狙いです」と説明します。
県塩谷南那須農業振興事務所園芸課の松本華苗(まつもとかなえ)さんも「今年はいいものが多くできたので、『極』の出来が楽しみです」と、ブランド力のさらなる向上に期待しています。
越雲さんは最後に自慢のカボチャへの愛情あふれる言葉で締めてくれました。「ぽくぽくとした食感と、カボチャらしい濃厚な味わいを多くの人に知ってほしい。『みなみちゃん』の良さは、一度食べてさえいただければ分かってもらえますから」
◇◆◇ 雑学辞典 ◇◆◇
-
カボチャの歴史 原産地はアメリカ大陸で、紀元前7000年~5500年のメキシコの洞窟の地層から種が発見されている。日本には16世紀ごろに伝えられ、名前の由来はポルトガル語のカンボジアを意味する「Camboja(カンボジャ)」とされる。
-
カボチャの種類 日本での栽培は、主に日本カボチャ、西洋カボチャ、ペポカボチャの3種類。
-
文化の中のカボチャ 日本では冬至にカボチャを食べる風習が各地に残っており、これは明治時代以降の風習とされる。米国などではハロウィーンが近付くと、だいだい色のカボチャの中身をくりぬいて目鼻をつけた観賞用のちょうちん(ジャック・オー・ランタン)を作り、中にロウソクを立てて戸口に飾る。
坂入良輔(さかいりりょうすけ)さん(29)/安定品質と多収量を両立

アスパラガスは、一度植えたら同じ株で10年以上収穫できます。そこが毎年種をまくトマトなどとは違うところです。今年ためた栄養分が来年の作物につながり、管理の出来が大きく影響してくるので、「毎年が勝負」という気持ちで取り組んでいます。
父親の下で就農して7年目。4年前からは自分一人で管理するハウスを任されています。前年より収量が上がった時の喜びは格別ですね。これからも、安定品質と多収量を両立させていきたいと思っています。
専門部の若手でつくる「研究グループ」では、メンバーで刺激し合いながら、先進地の視察や、道の駅での直売などを行っています。また、商工会などと多業種コラボの「かみのかわBQグルメ研究会」の一員として、地元産のアスパラガスやニラ、トマトなどを使った「かみのかわ黒チャーハン」のPRにも力を入れています。
アスパラガスは、疲労回復に効く成分を含む健康野菜です。春の野菜のイメージが強いかもしれませんが、夏のアスパラガスもシャキシャキしておいしいのでぜひ食べてみてください。
JAうつのみやでは地域のみなさんを対象にJAくらしの活動の一環として「アグリスクール」を実施しています。
「アグリスクール」は農業体験を主として、食と農に関する理解を深めてもらう活動です。定植・種まきから収穫、試食までの各過程を体験することで、より作物を収穫する喜びを味わってもらいます。
平成26年度は13活動を行う予定です。すでに5活動を実施し、6月7日のリンゴの摘果作業体験には9組28人が参加しました。約1時間摘果作業に参加したみなさんは「秋に大きく育った実をとって食べるのが楽しみ」と収穫への期待を話してくれました。
7月以降は、8月下旬にブロッコリー・キャベツの農業体験、9月下旬に稲刈り体験教室、10月下旬にはさつまいも収穫・干しいも作り等を予定しています。
各活動の詳細や参加応募については、JAうつのみやHP(http://www.jau.or.jp)に随時掲載していきますので、ぜひご参加ください。
[写真説明]特産カボチャの「みなみちゃん」
[写真説明]「味と安全安心には自信があります」と話す越雲さん
[写真説明]坂入良輔さん
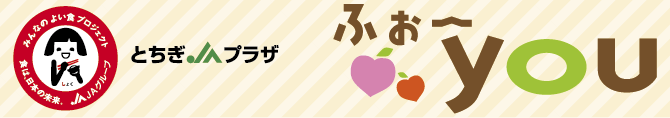
 ポストする
ポストする


























































