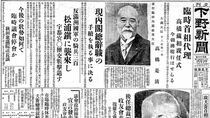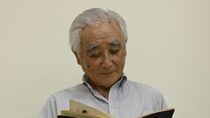1943(昭和18)年9月、兵力不足を補うため東條英機(とうじょうひでき)内閣は、理工医学系など一部を除いた学生の徴兵猶予の停止を決定した。「学徒出陣」と呼ばれ、多くの学生が兵役に就くこととなった。
日本軍の戦局悪化が背景にあった。42(昭和17)年のミッドウェー海戦、ソロモン諸島・ガダルカナル島の戦いなどの敗退が響き、主導権は次第に米軍へ。43年は連合艦隊司令長官の山本五十六(やまもといそろく)の戦死をはじめ、戦死者数が増加したことで学生の徴兵を余儀なくされた。
10月21日には東京・明治神宮外苑で出陣学徒壮行会が開かれた。翌22日付の本紙では「決戦進撃の路啓く」「無上の栄誉 男子の本懐」の見出しで、文部大臣の訓示などを伝えている。
同年は大政翼賛会を中心に全国各地で造船のための供木運動が盛んに。本県では日光杉並木も対象とされ、同会今市支部などが県や日光東照宮に全木伐採の陳情を行った。
本紙は2月26日付で、その様子を報道している。しかし文部省や有識者らから伐採反対を受け、実際に伐採されたのは2本だけだった。

 ポストする
ポストする