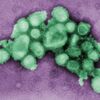県立美術館が国立アートリサーチセンターと連携する事業「国立美術館コレクション・プラス」の第1号に選ばれた。国立美術館の所蔵品を活用し、研究成果を踏まえた県立美術館の作品を鑑賞できる有意義な機会となる。今後も積極的に事業へ名乗りを上げ、本県所蔵品の魅力を多くの県民に伝えてほしい。
事業は昨春、アート振興の新たな拠点として国立美術館内に設立されたセンターの取り組みだ。全国の美術館の所蔵品に国立美術館の作品を数点加えることで、テーマ性の高い特集展示開催の推進、調査研究活性化へ貢献をすることが狙いで、輸送費など経費の一部も負担する。
美術館にとって所蔵品の調査研究は重要な役割の一つである。作家の考察を突き詰める上で他の美術館に影響を受けた作品があれば、借用し比較研究を望むのは当然だろう。一方、国立美術館所蔵品のように貴重な作品ともなれば、輸送費や保険料など金銭的なコストがかかり、予算が限られた地方の美術館は二の足を踏んでしまうのが現状だ。
県立美術館も同様の悩みを抱えていたが、所蔵する栃木市ゆかりの画家刑部人(おさかべじん)の作品と国立西洋美術館所蔵のフランス人画家ギュスターヴ・クールベの作品との関連性に着目し事業に応募。国立西洋美術館の作品を活用し検証する提案が、センターの考えと合致し選定された。県立美術館学芸課の武関彩瑛(ぶせきさえ)主任(31)は「借用コストが抑えられたことはもちろん、作品を比較することにより画像では分からない質感の変化まで確認できた」と事業による考察の成果を強調する。
開催中のコレクション展は刑部の作品がメインだが、クールベの作品が加わったことで鑑賞者に説得力を持つ。新たな形の展示は、県民に所蔵品の価値を再認識してもらう好機ともいえるだろう。
事業は今後、国立工芸館や国立国際美術館など対象館を変え、借用対象のジャンルも広げて継続される。県立美術館には本県ゆかりの近現代美術品をはじめ約9千点もの所蔵品があるだけに、積極的な応募を期待したい。
その際、県内の美術大や専門学校と連携した企画を提案してはどうだろう。所蔵品の活用に加え、人材育成の面でも意義を見いだせれば、同館の価値をさらに高めることになるのではないだろうか。
 ポストする
ポストする