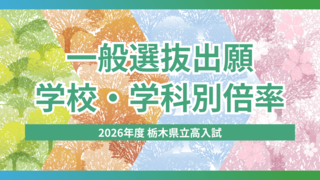足利市は今月、ベトナム中部のクイニョン市と「相互協定に関する覚書」を締結した。人材交流を促進させることで、労働力の確保や訪日外国人客の増加を期待している。
自治体と海外都市との提携はかつて、学生の派遣やイベント参加といった教育的、親善的な意味合いが強かった。こうした友好交流も必要だが、クイニョン市とは実効性にこだわったパートナーシップの構築を目指すべきだ。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、14万人弱の足利市の人口は2050年には約10万人にまで減り、高齢化率は44・1%に上る見通し。15~64歳の「生産年齢人口」の減少は働き手不足や消費意欲の低下を招き、税収減などの負のスパイラルに陥る。そこで課題解決策の一つとして目を付けたのが、経済成長が著しく、人口約1億人のベトナムとの連携だった。
クイニョン市は同国ビンディン省の省都で人口30万人以上。主要産業は観光業や製造業で、国立クイニョン大は日本語教育に力を入れる。同大と足利大も先日、学術交流協定を結んだ。
そもそも、本県は同国とのつながりを強化している経緯がある。福田富一(ふくだとみかず)知事は2019、22、23年にトップセールスで訪れ、23年には経済交流に関する覚書を締結した。
早川尚秀(はやかわなおひで)足利市長は22年、知事に同行してベトナムを訪問。外務省や県、日本貿易振興機構(ジェトロ)とちぎなどと連携して交渉を続け、今年6月には2回目の訪問をした。ベトナム側からの働きかけもあり、今後の成長が期待できるクイニョン市との覚書締結につながった。
今後の交流は未定だが、さまざまな可能性が考えられる。観光面では、希望する市民を募って訪問団を組織し、チャーター機で相互の来訪を促進してもいいのではないか。足利学校やあしかがフラワーパークなどの観光資源も活用できるだろう。人材面では足利大で留学生を受け入れて「高度外国人材」を育成し、引き続き地元企業で働いてもらうことも想定できる。
覚書を締結しただけで、輝かしい未来が約束されたわけではない。市や大学、地元企業などが協力し、具現化に尽力することが不可欠だ。着実に成果を上げ、他市町に先駆けた持続可能なまちづくりにつなげてほしい。
 ポストする
ポストする