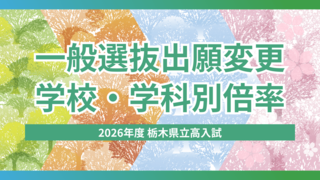新型コロナウイルス禍で収入が減り、国の特例貸付金によって生活資金を借りた人の多くが困窮から抜け出せずにいる。県社会福祉協議会(社協)によると、これまでに約5万7千件、計212億2800万円を貸し付けた。今年3月末時点で県内の約1万5600件、54億600万円の返済が免除されている。
免除されても、就労や家計改善など自立支援につなげることが重要だ。特例貸し付けの窓口となった都道府県社協が、その役割を担っている。
会計検査院は本県を含む一部の社協で、返済免除者らへの支援体制が不十分だったと指摘した。困窮者が置き去りにされることのないよう、支援体制を整える必要がある。
特例貸し付けは減収を補う最大20万円の「緊急小口資金」と、生活再建に充てるため1回最大60万円を3回まで貸す「総合支援資金」がある。住民税非課税世帯や、課税世帯でも返済困難と認められた場合は返済が免除される。
貸し付け申請は2022年9月末で終了した。会計検査院によると、全国では今年3月末時点で131万件、計4684億円の返済が免除され、滞納されているケースもある。
厚生労働省は全国の社協に通知を出し、返済免除者や滞納者と面談して自立支援機関などにつなげる「フォローアップ支援」を求めていた。
だが会計検査院が調査した17都府県の社協のうち、免除者について14社協で、滞納者についても10社協で、支援の実施体制が整備されていなかった。いずれも本県社協が含まれている。
原因の一つに、都道府県社協と市町村社協などの役割に応じた実施方法などについて、厚労省の指導が明確でなかったことなどが挙げられている。県社協は、通常の貸し付けと同様の対応を、市町社協に依頼していたという。
一方で滋賀県社協は免除者らに対し、生活状況を把握し必要な支援につなげるため、関係機関と調整し、実施方法を明示した事業計画を策定していた。
特例貸し付けは事前審査を簡素化し、条件も緩和した。その分、生活状況の把握は難しくなるだけに、事後の支援が一層、重要となるはずだ。本県でも県社協や市町社協、関係機関が連携し、生活再建を後押しする体制づくりが求められる。
 ポストする
ポストする