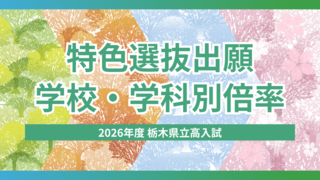大規模災害時にがれきなどを除去して救援ルートを確保する「道路啓開」作業について、県県土整備部が「県道路啓開計画」を策定し、ホームページで公開している。道路啓開は、初動のスピードが被災者の生死を分け、災害対応の成否に関わる活動といえる。計画を備えているだけでは十分ではない。計画の実効性を高める継続的な訓練が必要だ。
東日本大震災では、内陸部を南北に貫く東北自動車道と国道4号から、沿岸部へ延びる道路の通行を確保する「くしの歯作戦」により、迅速に主要都市へのアクセスルートが確保された。また、能登半島地震では、道路が寸断されて集落が孤立、救援活動、物資輸送に遅れが出たことなどが問題になった。
県は、対象を大規模地震とし、能登半島地震と同規模の地震が県庁直下で発生したと想定して計画を策定した。
最優先で啓開を行うのは国道4号(新4号国道を含む)、国道50号、東北自動車道、北関東自動車道の4路線で、被災状況や啓開作業時間を考慮し、優先的に啓開する路線を選定して作業に着手する。
作業完了は発災から48時間以内とした。広域的な救助にかかる防災拠点を結ぶルートを啓開させ、救助活動を本格的に行う。人命救助の「72時間の壁」を考慮すれば、啓開作業が生死を分かつとの姿勢で臨むのは当然で、48時間は猶予という意味ではない。
東日本大震災の「くしの歯作戦」は、成功例として語り継がれている。しかし、がれきの中からは多くの遺体が見つかり、大型重機の作業をあきらめ手作業で行ったなどの報告もある。想定を超えた状況となっても、対応が迫られる。
東日本大震災の道路啓開に当たった国土交通省東北地方整備局が、前例のない決断を迫られた発災からの1週間の活動をまとめた「災害初動期指揮心得」は示唆に富む。その中に「備えていたことしか、役には立たなかった。備えていただけでは、十分ではなかった」との一文がある。
計画を備えただけでなく、備えを訓練し実効性を持たせることが必要ということだ。本県の計画には、平時から各種訓練を定期的に実施し、現場対応力の向上を図る、と記されている。まさに、計画を基に、今後どう備えていくのかが成否の鍵となる。
 ポストする
ポストする