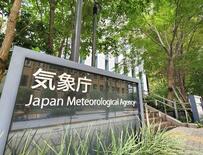2位 「ヒヨドリの啼く庭」 秋田柴子さん
「蓮くん、明日は遠足だね。おばあちゃんとてるてる坊主、作ろうか」
「てるてる坊主? そんなの『お天気ナビ』見りゃ一発でしょ。明日は晴れで、夕方までの降水確率は一〇%だからモンダイなくね?」
スマホから目も上げずに滔々(とうとう)と返す孫は、まだ十一歳だ。思わずため息が出る。
「お義母さん。私、明日は会社の送別会で遅いんで、蓮が遠足から帰ってきたら、夕飯とお風呂お願いします」
「はいはい、木曜だから塾はなかったわね」
「ええ、でも宿題はきちんとさせてください。どうせ遠足帰りでグダグダするんで。それから……」
嫁の細かな指示が延々と続く。それこそスマホで録音しておきたいぐらいだ。
私は狭い和室へ引っ込むと、またため息をついた。古い箪笥(たんす)や鏡台のひしめき合うこの六畳間が、今の私の部屋だ。以前使っていた二階の寝室は息子夫婦に譲ってしまった。それとてまわりからは「今時、同居してくれるお嫁さんなんてありがたいじゃない」と諭されるばかりで、愚痴をこぼす先もない。
そもそもの話、私の方から同居を頼んだわけではなかった。夫亡き後に一人で住んでいた小さな戸建てへ、息子家族が半ば強引に転がり込んできたのだ。家族で暮らせば寂しさも紛れるかと、安易に同居を受け入れた自分の浅はかさにも嫌気が差す。ふたを開けてみれば日々の家事も子供の世話も、夫婦そろってこちらへ丸投げだ。「親の面倒は実子で見るべき」と盛んに言われるこの時代に、他人であるはずの義理の親へ家事や育児の〝面倒〟を頼むことが問題にならないのは、何とも不思議だった。
翌朝全員を家から送り出すと、私は庭へ出た。朝のまっさらな空気を胸に満たしながら、野鳥のために水盆の水を張るのが日課なのだ。昔は姿見たさに古い米をまいていたのだが、今日び野鳥の餌付けは厳禁らしい。だが水場があるだけでも、住宅街に生きる鳥たちには好評のようだった。今日も庭の隅にある金木犀(きんもくせい)の茂みから、大きなヒヨドリがじっとこちらを窺(うかが)っている。啼(な)き声こそ騒々しいが、よく見るとふさふさした頭と顔の赤い斑点が可愛(かわい)らしい。だがしげしげ見られるのが気に入らないのか、ヒヨドリは甲高い声を残して、どこかへ飛び立っていってしまった。
――さあ、私も出かけましょうか。
今日は待ちかねていた本の発売日なのだ。数年前に定年退職をした身では、意識して外へ出ないと、それこそ家に根が張ってしまう。
平日の午前だけあって、駅前の大型書店は空いていた。首尾よく新刊を手に入れたついでに、せっかく来たのだからと店内に併設されたカフェへ足を運ぶ。
窓際の席へ座って熱いコーヒーに口をつけた時、ふとテーブルに貼られたシール広告が目に入った。『新しい時代のビジネスホテルで、あなただけの快適な時間を』……どうやら全国チェーンのホテルが近くにオープンしたようだ。
「え、一泊四九〇〇円から!?」
思わず声を上げると、隣の若い女性がちらりとこちらを見た。私は慌てて頭を下げると、急いでスマホを取り出した。だが寄る年波の哀(かな)しさで、なかなか目当ての画面までたどり着けない。
「あの、お手伝いしましょうか?」
驚いて横を見ると、隣の女性がこちらへ微笑(ほほえ)みかけていた。背中を丸めてスマホと格闘する姿がよほど痛々しく映ったのだろうか。
「ご旅行ですか?」
「いえ、そういうわけじゃ……ただこの値段で泊まれるなんて驚いちゃって」
「最近のビジホはこんな感じですよ。その割にはきれいだし、実は結構お得かも」
「びじほ?」
ビジネスホテルです、と女性は苦笑いと共に付け足した。
「別に旅行じゃなくても、ホテルステイっていいですよね。短い間だけでも非日常を味わえるって言うか。気分を変えるって大事ですから」
――非日常を味わう。
花が咲いたような彼女の笑顔につられて、私は画面の宿泊予約ボタンを押していた。
「確かにきれいねえ……ホテルって言うよりマンションみたい」
シックなグレーのトーンで整えられた部屋は、思ったよりも広かった。まだ新しいせいか、靴の底がカーペットにふかりと埋まる。小さな荷物を置くと、浴室やトイレをひととおり覗(のぞ)いてみた。バスタブがそこまで狭くないことにほっとする。
昨晩、息子夫婦に「明日、ホテルに泊まるから、食事や蓮の送迎は自分たちでやってね」と告げた時は、ちょっとした騒ぎだった。無理もない、私が夜に家を空けることなどまずなかったのだ。
だが「何考えてんだよ、金がもったいないだろう」とあきれる息子に「あんたが毎週行ってる午前様の飲み会より安いわよ」と啖呵(たんか)を切って出てきたものの、自宅から一時間と離れていないホテルのロビーで無料のコーヒーをすする自分がどうにも気恥ずかしく、むずむずと落ち着かないのには閉口した。気を紛らわそうとスマホで調べてみたら、家を持たずにホテル暮らしをする人は意外にいるらしい。一流ホテルを終の棲家にという有名人もいれば、こういう小さなホテルを遊牧民のように泊まり歩く人もいるようだ。
画面をたどる手を止め、ふと考え込む。私が予約した部屋の料金は五六〇〇円。ざっくり計算すると一カ月で約十七万弱だ。そこには光熱費や水道費、シャンプーやティッシュのような消耗品代も含まれる。食費こそ別だが、数日に一回は部屋や水回りの掃除に、シーツ交換までしてもらって十七万なら、あながち非現実的な数字でもないと皮算用を弾く自分が、我ながらおかしかった。
やがて夕闇が空を覆い、仕事を終えた人たちがビルから吐き出されてくる。目についた和食の店で、私は久しぶりに一人きりの夕食の膳に向かった。旬の野菜の天ぷらに海老真丈、柚子胡椒(ゆずこしょう)のきいた鶏ささみの炙(あぶ)り焼き。幼い孫や、濃い味つけの好きな息子夫婦との同居では望むべくもない品々だ。日常の殻をほんの少し破れたお祝いにと、小さなグラスの日本酒を傾ける。夫が生きていた頃は、よく二人で杯を楽しんだものだ。一皿の旨味(うまみ)をじっくりと味わって食べた、あの頃の静かな食卓がひどく懐かしかった。
気づけば一週間が経っていた。
一泊で帰るつもりが、〝ホテルステイ〟の思わぬ快適さについ日を重ねてしまったのだ。部屋に小さな机と真新しいファブリックの椅子があるのは嬉(うれ)しかった。腰を据えて本を読むのに、座り心地のいい椅子は欠かせない。
だが当然ながら、家から矢のような催促が来るのは避けられなかった。
「いい歳してプチ家出とか勘弁してくれよ、母さん。だいたい無責任じゃないか。香凜も仕事に支障が出て困ってるんだよ。蓮だって、帰ってきても誰もいないから……」
「蓮のことはどうしてるの?」
息子はごにょごにょと口ごもった。どうやら以前使ったことのある、近所の有料サポートルームに預けているらしい。それを聞いて、あっさり気が抜けた。そうだ、私がいなくても成り立つのだ。家族だから手の空いている自分がやらねばと、私が勝手に思い込んでいただけなのだ。考えてみれば向こうは共働きの上、食費や光熱費は折半、住宅費に至ってはゼロなのだから、外部のサービスを利用するぐらいの余裕はあるはずだった。
「それに母さんの姿が見えないから、近所からいろいろ聞かれるんだよ。歳取った母親を追い出して、ホテル暮らしさせてるなんて思われたら……」
「――ホテル暮らしか。それも悪くないわね」
独りごとのように呟(つぶや)くと、途端にスマホの向こうの声が慌て出した。
「じょ、冗談はやめてよ、母さん! えーと、なんか家に不満があるとか? そりゃ家事や蓮の世話を任せきりなのは、俺も香凜も悪いと思ってるけど……」
露骨な声色の変わりように、思わず噴き出しそうになる。私がもう帰らないつもりだとでも思ったのだろうか。
だが私自身、長年夫と暮らしたあの家をあっさり手放す勇気はなかった。仕事も辞めた今、誰かに必要とされることを心のどこかで求めてもいた。だからこそ家のためにと尽くしているつもりで、実際には家族という尽きぬ波に、自分の砂浜をじわじわと音もなく削り取られていたのかもしれない。
そう思うと、たった一週間でも〝ホテル暮らし〟の効果は絶大だった。カフェで出会った若い彼女の言ったとおりだ。削られた砂浜は、戻してやらねばならない。いや、削られる前に護(まも)ってやらねばならないのだ。
「――明日、帰るわ。また家で話しましょう」
焦る息子に構わず通話を切ると、小さな窓から今夜限りの景色を眺めた。高層階ならではの夜景は見事だが、昼間は切り取られた空の一部しか見られない。そろそろ自分だけの空が見える、あの狭い庭が恋しくなっていた。そうだ、水盆の水もそのままだった。さすがに水も濁ってしまっているだろう。いつも来るヒヨドリの不満げな啼き声が聞こえるようだ。それとも気まぐれな家主に愛想を尽かして、どこか他所(よそ)へ移ってしまっただろうか。
――明日には帰るから、また来てね。
私は窓辺を離れると、しまったきりだった鞄(かばん)を取り出して、部屋の中に散らばった荷物を少しずつ丁寧に詰め込んでいった。

 ポストする
ポストする