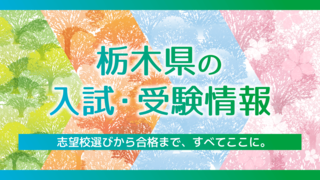2024年に下野新聞が取材し、報じた能登半島地震関連の記事は260本を超えた。募金やボランティア、行政の応援、チャリティーイベントなど、さまざまな活動が展開された。県内関係者の動きを一部の記事で振り返る。
■被災地復旧へ一丸 各地で募金箱を設置(1月5日)
【全県】1日に発生した能登半島地震の被災地を支援するため、少なくとも県内14市町が4日までに募金箱を設置した。

下野新聞社のまとめによると、募金箱を設置したのは足利、佐野、栃木、下野、鹿沼、宇都宮、さくら、那須烏山、矢板、大田原、那須塩原の11市と上三川、高根沢、茂木の3町。足利や那須烏山市などは社会福祉協議会とも連携し、日光市も準備を進めている。
足利市は同日、市役所1階や公民館など19カ所に募金箱を設置し、各市町も庁舎内や支所の窓口などに設けた。義援金は日本赤十字社などを通じて被災地へ送られる予定。
一方、日光市山内の世界遺産・日光山輪王寺も同日までに、境内4カ所に募金箱を設置。本堂「三仏堂」では本尊の一つ千手観音の下に設けられ、すでに多くの浄財が寄せられていた。
同寺の鈴木常元(すずきじょうげん)教化部長は「被災地への支援はいろいろあると思うが、まずはできる支援として募金を始めた。多くの人にご協力いただき、少しでも力になれれば」と話した。
■佐野市 被災女性 受け入れへ(1月6日)
能登半島地震に関連し、金子裕(かねこゆたか)佐野市長は5日の定例記者会見で、被災した石川県珠洲市の女性(81)を市営住宅で受け入れることを明らかにした。
佐野市によると、女性は珠洲市内で1人暮らし。地震発生後は避難所で生活しているという。佐野市内に住む女性の息子夫婦から4日、女性の受け入れについて相談があり、同市が準備を整えた。女性は11日ごろまでに、市営住宅に入居する予定。
記者会見で小倉浩史(おぐらひろし)行政経営部長は「2019年の台風被害などで、全国からたくさんの支援をいただいた。それらに応えることができれば」と話した。金子市長は「各被災者のニーズに応じて市全体での支援に取り組んでいく」と述べた。
■応急給水業務の職員2人を派遣 那須烏山市(1月31日)
【那須烏山】能登半島地震の被災地支援で市は30日、応急給水業務に当たる職員2人と給水タンク積載のトラック1台を派遣した。

派遣されたのは市上下水道課の高瀬浩明(たかせひろあき)係長(43)と塩野淳(しおのじゅん)主査(36)。派遣期間は2月5日まで。石川県輪島市または志賀町で、自衛隊の給水車や病院の受水槽への補給などを行う。
同被災地への市職員の派遣は初めて。市役所水道庁舎で行われた出発式で川俣純子(かわまたじゅんこ)市長は「健康に気を付けて、できる範囲のことをやってきてほしい」と激励。高瀬さんは「少しでも被災地の不便を解消できるように業務に当たりたい」と応えた。
2月には、住宅被害の調査業務を担当する都市建設課平野祐太郎(ひらのゆうたろう)主査(37)と避難所運営を支援する総務課伊藤大道(いとうひろみち)主査(33)を穴水町に派遣する。
■ボランティア団体「チームかぬま」 息長い復興支援目指す(3月2日)
【鹿沼】災害ボランティア団体「チームかぬま」はこのほど、能登半島地震で被災した石川県珠洲市の沿岸部で災害復興支援に当たった。メンバー3人が浸水した家屋からの家財の運び出しや、戸が壊れて風が吹き抜ける家の防風措置などに奔走。発生から2カ月がたつ中でも、被災の痕跡が残る状況に、山野井濱市(やまのいはまいち)代表(73)は「あんな光景は初めて。津波の怖さですよ」と吐露した。
チームかぬまは2012年、前年の東日本大震災の被災地支援に取り組む市民有志が結成した。重機の操作やブルーシート張りなどの専門技術を持つメンバーが中心。16年の熊本地震や18年の西日本豪雨の被災地などにも足を運んだ。
今回は早期に現地入りしたNPO法人災害救援レスキューアシスト(奈良県)の要請を受け、山野井さんら3人が2月16~18日の3日間、珠洲市を訪れた。3人は避難所となっていた同市の滞在交流施設「日置ハウス」を拠点に、能登半島最東端の同市折戸町、狼煙(のろし)町、川浦町の3地区で活動した。
断水が17日に解消したばかりで、同施設では50人近くが避難生活を続けていた。市中心部からの山道には崩れた土砂や激しい道路の隆起が依然残り、県を通じた一般ボランティアは受け入れていない。点在する民家は高所から見回すと、どの家も1階部分を失い、屋根瓦が落下したまま。ブルーシートの応急処置すら手つかずの家も多かった。
3人は折戸町の独り暮らしの70代男性宅を訪れた。柱は傾き、家財はかび、障子戸には多くの穴。倒れたたんすは引き出しが飛び出したままで、潮のにおいがまだ残っていた。
ジャッキを使ってふすまを立ち上げたり、たんすの転倒を予防する措置を取ったりしたほか、ブルーシートで玄関を覆うなどの応急処置を施した。男性は「2カ月間、自分だけじゃどうしようもなかった。ありがとう」と何度も感謝を口にした。泥だらけの家財も運び出し、ダンプカーで災害廃棄物の仮置き場に運んだ。
3日間で10軒ほどの民家で活動した。強い風雪の対策と思われる分厚い木の壁や屋根瓦は重く、連日の作業で腕がしびれた。「まだまだ数年はかかる」。山野井さんたちは今後も予算の許す限り現地入りし、息の長い支援を続けるという。
■浄財7761万円を寄託 救援募金、本社から日赤に(4月12日)
下野新聞社は11日、「下野新聞・能登半島地震救援募金」に個人や企業・団体から寄せられた浄財計7761万6653円(預金利子を含む)を、日本赤十字社県支部(宇都宮市若草1丁目)に寄託した。石川、富山、新潟、福井の4県を通じて被災者のために役立てられる。
若菜英晴(わかなえいせい)社長が同日、同支部を訪れ、県保健福祉部長で日赤県副支部長の岩佐景一郎(いわさけいいちろう)氏に目録を手渡した。
若菜社長は「被災地の力になりたい県民がたくさんいた。現地の再建は長い道のりなので、復興に役立ててほしい」と託した。岩佐氏は「多くの県民の方から寄付をいただきありがたい。温かい気持ちとともに浄財を適切に現地の被災者に届ける」と謝辞を述べた。
募金は1月22日~3月29日までに、個人や企業・団体から計943件寄せられた。
■被災禍“飛び越え”願い 那須塩原 支援兼ね障害馬術大会(6月8日)
【那須塩原】能登半島地震のチャリティーイベントを兼ねた障害馬術大会「那須グランドホースショー」が7日、寺子の那須トレーニングファームで始まった。9日まで。
同ファーム(広田龍馬(ひろたりゅうま)代表)が主催。エントリー料やパンフレットなどの売り上げの一部が引退馬の暮らす石川県珠洲市の牧場に寄付される。3日間で18競技が行われ、8日の「那須グランプリ」は障害馬術ワールドカップの国内予選に位置づけられている。
7日は中障害など6競技が実施された。馬にまたがった選手たちはコース内の障害を次々と飛び越え、人馬一体の息の合った動きに観客席からは声援が送られていた。広田代表(48)は「馬術競技を通して社会貢献がしたいと思い開催した。人を乗せて飛ぶ馬の美しさや息づかいを感じてほしい」と話した。
■能登半島地震きょう半年 輪島・町野町地区 至る所に倒壊家屋(7月1日)
元日夕に最大震度7を観測した能登半島地震は1日、発災から半年を迎えた。行政や医療機関、民間、個人など、多くの人たちがさまざまな支援で被災地入りしてきた。認定NPO法人「とちぎボランティアネットワーク」(とちぎVネット)は活動を継続する団体の一つだ。これまでに約30回、延べ550人がボランティア活動に従事。29、30の両日は14人が同県輪島市町野町(まちのまち)地区で、被災家屋から家財道具を運び出すなどした。「まだまだ人手が足りない」。Vネットは継続的な支援の必要性を訴える。

Vネットが活動する町野町地区は、一面を焼失した観光地「輪島朝市」がある市中心部から東方面へ約20キロに位置。北側の一部が海と接し、内陸に入ると周囲を山が囲む。2級河川の町野川の両側に水田が広がり、住宅が点在している。
至る所で道路が隆起や陥没し、倒壊した建物が目に付く。ある住民は「地震前に約2千人だった住民は、避難や移住で500人に減った」とこぼす。
支援の必要性を感じたVネットは4月、同県穴水町から同地区に活動拠点を移した。
記者が同行した30日、ボランティアは風雨の中、同市町野町鈴屋の中村一(なかむらはじめ)さん(68)宅で、半壊した住宅の片付けを手伝った。築50年で倒壊を免れたが、屋根瓦の一部は抜け落ちた。ぬれて使えない家財道具を運び出した。いずれは解体する予定だ。
中村さんは地震で長女を亡くした。夫の実家で正月を迎えていた時、大きな揺れが襲った。子どもを守ろうとし、家屋の倒壊に巻き込まれたという。「なかなか片付けも手に付かず、当時のままだった。本当に助かる」。ボランティアに何度も感謝を口にした。
とちぎVネットは7月の週末も支援活動に入る。矢野正広(やのまさひろ)理事長(62)は「町野町地区では私たち以外のボランティアをほとんど見かけない。まだまだ人手が足りない」と現状を強調する。ボランティアを募り、協力を呼びかけている。
■疲弊する能登、支えたい 本紙記者ルポ 輪島・町野町(9月30日)
家々をのみ込んだ土砂、橋に堆積した流木など、随所に爪痕が残る。能登半島北部を襲った記録的大雨から1週間超。記者は29日、川の氾濫などで甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町を訪れた。地震と豪雨。同じ年に2度も大災害に見舞われた。「ここで暮らしていけるのか」。住民は途方に暮れる。疲弊する被災地を何とか支えようと、本県などから多くのボランティアが駆け付け、復旧作業に当たる姿があった。
「住みやすいのどかな田舎だった」。住民がそう振り返る同地区は、土砂と泥で覆われていた。記者も震災後に二度、ボランティアで訪れた。6月には解体される建物が増え、「前に進もう」との声も聞こえてきていた。
豪雨で再び、町は一変した。周囲の里山は山肌が露出し、土砂や折れた木々が容赦なく麓の家々を飲み込んでいた。大雨で氾濫した鈴屋川の橋には流木などが堆積したまま。収穫期を迎えた稲は地面に倒れ、ひっそりと枯れ始めていた。
鈴屋川の氾濫で会社員常林坊伸治(じょうりんぼうしんじ)さん(54)方は床上浸水した。「住みやすい所だったんだけど、地震と雨で変わっちゃった。心が折れた」と視線を落とす。
認定NPO法人「とちぎボランティアネットワーク」は28、29の両日、常林坊さん方の片付けの他、集会所で足湯を提供した。初めて活動に参加した下野市、帝京大4年有田和貴(ありたかずき)さん(23)は「自分にできることをしよう」と汗を拭った。
本県民も参加する災害救援活動の任意団体「風組関東」(東京都)も両日、同地区で活動した。震災で家が被災し、住人が仮住まいする納屋が土砂に押し流された。メンバーが財布や携帯電話を探し出すと、住人女性から笑みがこぼれた。
小林直樹(こばやしなおき)代表(49)は「僕たちが頑張る姿を通して地元の方を励まし、復興の道筋をつくりたい」と話す。被災地を取り残さない-。そんな強い思いを感じた。
■被災者支援 協力を とちぎVネット 窮状報告(10月5日)
能登半島地震の被災地を支援している認定NPO法人「とちぎボランティアネットワーク」(とちぎVネット)は4日、県庁記者クラブで記者会見を開き、9月下旬の記録的豪雨で再び被災した現地の窮状を報告した。「被災者を支えるには、もっと多くの人の力が必要」と協力を求めた。
会見に臨んだのは9月28、29日に石川県輪島市町野町で活動したボランティア4人。住宅の片付けや、足湯の提供などを行った。
初めて参加した増田璃玖(ますだりく)さん(20)は「自分の背丈ほどまで家に土砂などが流れてきていた。片付けるには人手が足りない」と振り返った。大学生の小栗駿一(おぐりしゅんいち)さん(22)は地元の小学生が復旧作業を手伝っている実情などを説明し、「学生など若い人の力が必要」と訴えた。
社会福祉士の柾木美登利(まさきみどり)さん(50)は「家財を全て失った人にかける言葉がなかった。でも皆さん話し相手を求めている」。団体職員の渡辺貴也(わたなべたかや)さん(34)は「活動を通して、わずかでも希望や活力をお裾分けできる」と語った。
とちぎVネットのボランティアは毎週金曜正午に宇都宮を出発し、日曜夜に戻る。参加費3千円。同法人ホームページで詳細を確認できる。参加を検討する人らを対象に土曜午後6時から事前説明会を開いており、オンライン参加も可能。
 ポストする
ポストする