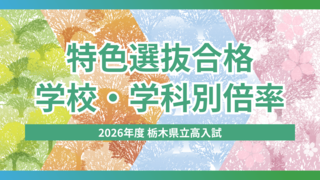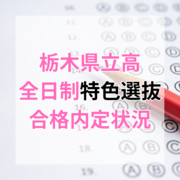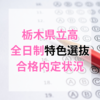鹿沼市上粕尾地区の国指定重要無形民俗文化財「発光路(ほっこうじ)の強飯式」の地元保存会が今月に予定していた本年度の開催を中止した。集落の過疎化や高齢化による担い手不足が大きな要因だ。無形民俗文化財はそれぞれの地域で育んできた貴重な財産だが、同様の課題を抱える県内の保存会は少なくない。官民などが連携して守り、次世代へしっかりと継承したい。
発光路の強飯式は毎年1月3日、妙見神社の祭り当番引き継ぎの後で行われる強力(ごうりき)行事。日光山輪王寺の「日光責(ぜめ)」の流れをくみ、室町時代から続くとされ1996年に国指定となった。新型コロナウイルス禍の影響で中止が続き、4年ぶりに昨年再開されたばかりだった。
県内には国指定5件、県指定20件の無形民俗文化財がある。さらに約180件が各市町の指定を受けているが、過疎化や後継者不足などの課題は深刻さを増している。
国指定の「川俣の元服式」(日光市)は対象者がいないため2016年を最後に行われず、今後も実施見通しはないという。県が確認しているだけで、県指定の「茂木町山内上組の百堂念仏」「半俵の寒念仏」(那須町)「富山の佐々良舞」(那珂川町)の3件も近年休止となっている。少子高齢化の流れを考えれば継承に向けた対策は急務だ。
県は22年度に「デジタルミュージアム」を開設し、文化財を映像化するなどして保存・活用する取り組みを進めている。本年度には文化財活用支援補助金を創設。国、県指定などを対象に30万円を上限に補助する仕組みで、市町などを通して呼びかけたが採択は3件にとどまる。県は周知にもっと力を入れるべきだ。
大分県では年2回、各保存会の実施状況調査を行っている。本年度は県の担当課を事務局に「大分県民俗文化財連絡協議会」を設立。県内各地の保存会が地域や芸能の枠を超え、継承に向けた情報共有や意見交換などを行っている。抱える課題はどこも同じであり、本県でも参考になる取り組みだろう。
保存継承へ向けた住民意識の向上も重要だ。県内には実施形式を変えて存続させている保存会もある。市町などが旗振り役となり、地域の垣根を越えて連携する方法もある。関係者がそれぞれの立場で現状と向き合い、今できる取り組みに力を注ぎたい。
 ポストする
ポストする