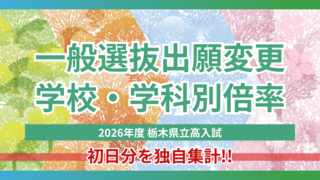悪質な交通事故に適用される自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪を巡り、高速度と飲酒の類型に数値基準が設けられる見通しとなった。鈴木馨祐(すずきけいすけ)法相が10日、諮問機関の法制審議会(法制審)に諮問する。
現行制度では数値基準はなく、要件の曖昧さが指摘されている。宇都宮市内で2023年、乗用車がオートバイに追突した死亡事故は、過失致死罪で起訴された乗用車の被告の罪名が、より法定刑の重い危険運転致死罪に訴因変更された。乗用車は一般道にもかかわらず、時速160キロ超だったとされる。
捜査当局が過失運転で逮捕・起訴しても遺族の訴えで危険運転に訴因変更したり、逆に危険運転で起訴された事件を裁判所が過失運転と判断したりする例が、後を絶たなかった。現場も迷う制度の見直しは当然だろう。その上で、政府には国民の常識にかなった制度の運用を求めたい。
同じ致死罪でも、法定刑の上限が過失運転の懲役7年に対し、危険運転は同20年と格段に重い。それだけに厳格な法の運用が求められる。
法務省の有識者会議が昨年11月にまとめた報告書によると、速度に関して具体的な数値は示さなかったが「最高速度の1・5倍や2倍」との委員の意見が紹介されている。
ただ、事故の状況はそれぞれ周囲の環境などにも左右される。速度にしても路面の状況や道路の幅員、混雑状況によっても危険度は異なるだろう。悪質で利己的な運転が見過ごされることのないよう、法制審ではあらゆる場面を想定して数値基準を検討してもらいたい。
飲酒に限れば、明らかに運動能力や判断能力が低下する基準を導入することは可能だろう。新たな被害を防ぐためにも、スピード感を持って進めるべきである。
法制審では、タイヤを曲芸的に滑らせるなどの「ドリフト走行」も、危険運転の新たな類型に加えることが諮られる。過去には登校中の児童を巻き込んだ重大事故も起きた。危険運転と見なすのは当然だろう。
あまりにも利己的な重大事故は、過失でなく故意犯として裁かれるべきだとの考えが国民に浸透しつつある。訴因変更が認められた宇都宮の事故も、7万を超える署名が集まった。法制審にはその重みをかみしめてもらいたい。
 ポストする
ポストする