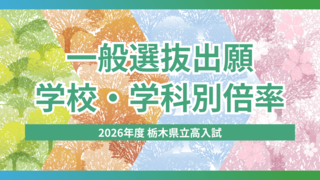埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、本県は管理する下水道管(総延長160・8キロ)を目視で総点検した。下水道管が地中に埋設された道路上の隆起や段差の有無を調べ、異常は確認されなかった。八潮市の事故は太い管路だったため、損壊により吸い込む土砂の量が多く大陥没につながったとされる。
高度成長期以降に集中的に整備されたトンネルや橋などのインフラが、老朽化の目安とされる建設から50年を次々と経過している。特に地中にある下水道管の破損の察知は難しい。県や市町は、陥没事故を教訓としたインフラ全般の現状把握と対策を急ぐ必要がある。ドローンや人工知能(AI)の先端技術を駆使した新たな点検手法など、国の積極的な支援も欠かせない。
八潮市の県道交差点で起きた道路陥没事故は、1月28日の発生からきょう11日で2週間となる。落下したトラックの運転手とみられる男性(74)の救助活動は現在も難航し、穴が拡大するなど収束まで長期化が懸念されている。
県内でも下水道管の老朽化などが原因とみられる道路陥没が相次ぐ。近年は2017年度に野木町の県道で直径2メートル強、深さ約3・4メートルの大きな陥没があった。データが残る23年度までの3年間でも計5件発生している。国内では下水道官に起因する陥没が年間約2600件にも上る。
下水道法は、腐食の恐れが大きな箇所の管路を対象に5年に1回以上の頻度での点検を義務付けている。このほか県は独自に、管理する管路上の道路の状況を月1回目視でチェックしているほか、全マンホール約2千カ所のふたを開けて内部に入り損傷の有無などを年1回確認している。
埼玉県のケースを念頭に、県は点検の頻度を増やすことを検討すべきだろう。また県内の下水道管の総延長約8600キロの大半を管理する市町も、県同様に法定点検以外の確認体制を取りたい。
国は13年に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、30年ごろに「老朽化に起因する重要インフラの重大事故ゼロ」の目標を掲げる。
重大事故ゼロの達成に向けて、国や県、市町は現在の取り組みが十分なのか連携を図りながら総点検すべきだ。とりわけ国は老朽化の予測や点検、調査などの技術開発を急ぎ、国内のインフラが安全に使えるよう万全を期したい。
 ポストする
ポストする