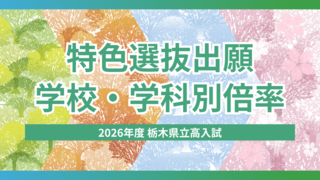児童相談所の一時保護所や児童養護施設などに入る子どもが、自分の気持ちや意見を表明した上で納得した支援を受けられるよう、県は3月から「意見表明支援員(アドボケイト)」による「こどもの権利擁護サポート事業」に乗り出す。
子どもの意見を尊重することは、権利擁護の基本と言える。それぞれの事情で親の保護を受けられず、社会的養護を受ける立場の子どもにとっては、なおのこと重要となる。子どもの気持ちをくみ取り、処遇決定に反映される仕組みを整えなければならない。
アドボケイトは、子どもの福祉に関して知識や経験を持つ専門家が、親や関係機関から独立した中立的立場で、子どもの意見や意向を聞き取る。その声を踏まえ、児童相談所などの関係機関との連絡調整を行う役割も担う。
本県では一般社団法人とちぎこども総合研究所が県の委託を受け、6人のアドボケイトによる支援を始める。初めは一時保護所の子どもを対象とし、児童養護施設やその他の施設、里親委託となった子どもへ順次、拡大する。
子どもの意見表明権は日本が1994年に批准した「子どもの権利条約」に盛り込まれていたが、国内の制度化は遅れていた。本年度施行された改正児童福祉法で、子どもの意見表明支援が都道府県の事業として位置付けられた。これを受け、県は新たに策定した県社会的養育推進計画案(2025~29年度)に、関連事業を盛り込んだ。
県が昨年行ったアンケートによると、児童養護施設や里親・ファミリーホーム、自立援助ホームにいる子どものうち、6~8割が「気持ちや意見が大切にされていると感じる」とした一方、約2~4割が「分からない」と回答した。一時保護所の子どもに限っては「分からない」が6割にも上った。
中には「職員さんに気を遣い過ぎてしまう」「悩みがあってもなかなか話せない」という子どももいる。こうした不安を取り除き、信頼関係を築いた上で、子どもの意見を把握することが求められる。
子どもの意見を無視したまま、本人の人生を左右する処遇が決定されるようなことがあってはならない。意見表明支援は、当面は小学生以上が対象となるが、小学生未満の子どもへの支援も積極的に検討してほしい。
 ポストする
ポストする