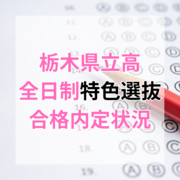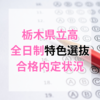妊婦健診をほとんど受けないまま出産に至る「未受診妊婦」は、母体だけでなく胎児にも危険が及ぶとされる。県が初めて調査した結果、2023年に県内医療機関を訪れた約100人が該当したという。県内で生まれた赤ちゃんは24年に初めて1万人を割り込み、過去最少の9670人と見込まれる。23年は1万260人程度で、いずれにしても未受診妊婦は約1%いる。
背景には、物価高に伴う経済苦や外国人労働者の拡大、予期せぬ妊娠で周囲に隠さざるを得ないなど複雑な要因が絡み合っている。県は妊婦と接する市町と連携し、健診の啓発はもちろんのこと、医療機関や妊婦、出産後の親子への支援の充実を図るべきだ。
県こども政策課によると、妊婦の95%以上が妊娠11週までに妊娠の届け出をし、最終的に100%近くが届け出て健診も受けているが、出生数が減り続ける中で未受診妊婦の存在は見過ごせない。
未受診妊婦には母子ともに健康上のリスクが伴う。例えば妊娠糖尿病などがあると難産になる可能性が高くなり、胎児をすぐに取り上げることができず命の危険も生じる。健診を受け、妊婦が適正に健康を管理すればこうした危険を避けられるという。
さらに、事前に育児指導を受けられないことも大きい。こうした妊婦は孤立しているケースが多いとされ、出産後に虐待をしてしまうリスクが高まることも知られている。
医療機関は、妊婦の健康や家族構成などの背景を知らされずに突然出産に臨む困難を強いられる。本来は感染症なども含めてリスク管理した上で分娩(ぶんべん)の対応に専念するはずが、並行して妊婦の身元を確認することから始まる福祉的な業務もこなさねばならない。負担は大きい。
今回県が実施した調査で未受診妊婦の存在が明らかになったことは評価したい。一方、県医療政策課によると、調査では妊婦の国籍や年齢層などの属性、医療機関が負担軽減のために具体的に何を望んでいるかなどの詳細については尋ねていない。
県は新年度、若い世代に将来の妊娠・出産を意識した健康管理を促す「プレコンセプションケア」を推進し、啓発に力を入れるが、さらなる対策が必要なのは明らかだ。効果的な支援を実現するためにはまず、より踏み込んだ今後の調査が必要だろう。
 ポストする
ポストする