「引き続きクロシオンズでB3リーグを目指したい。そういうメンバーもいらっしゃるのではないでしょうか?」
「それはないですね」と菊池(きくち)は即答する。「今回の一件で懲りましたから。もう二度とごめんや。そういうメンバーがほとんどですね。それに僕らは社会人なんです。そこまでバスケにのめり込めないんですよ。それに……」
代表者や親会社の変更など、事務手続きも煩雑になると菊池は説明した。その点は大丈夫だと奨吾(しょうご)は考えていた。書類関係の手続きなら公務員の本領発揮だ。奨吾自身がやらなくても、部下に頼んでしまってもいい。
問題はホームタウンだ。クロシオンズは高知市をホームタウンとしており、そのためチーム名にも高知の文字が入っている。できれば堅魚(かつお)市をチーム名に入れたい。そうでなければ宣伝効果が見込まれないからだ。あくまでも最終的な目標は堅魚市に人を集めることなのである。
「菊池さん、チーム名ですが、変更することは可能でしょうか?」
「できると思いますよ。事務局の許可を得られれば。でも赤羽(あかばね)さん、気が早いと思いますよ」
「どういうことですか?」
「さっきも言った通り、バスケチームの運営は大変なんです。チーム名なんて二の次でしょうね」
菊池が目を細めてこちらを見ている。このおじさん、何もわかってないな。そういうことを考えていそうな目つきだった。
「ただいま」
奨吾が家に帰宅したのは午後九時過ぎのことだった。リビングには誰もいない。冷蔵庫からペットボトルの緑茶を出す。その緑茶には奨吾の名前が書かれた付箋が貼られている。自分が買ってきた品物には自分の名前を書いた付箋を貼る。それが赤羽家のルールだ。
誰もいないリビングで一人、冷たい緑茶で喉を潤す。さきほどまで菊池と一緒だった。カフェだけでは終わらず、そのまま居酒屋に場所を移して語り合った。
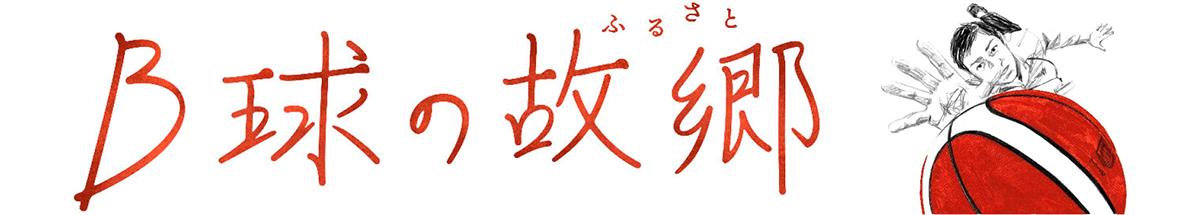
 ポストする
ポストする



















