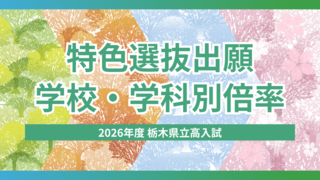大田原市の伝統行事で19、20日に行われる「大田原屋台まつり」は本年度から、市内全域から公募した小学生の引き手が屋台運行に参加する。少子高齢化による担い手不足の加速は必至で、祭りが行われる市中心部9町会に限らず、担い手を育む新事業である。地元の誇りを守るため、祭りの存続、盛り上げに粘り強く取り組んでほしい。
屋台まつりは、大田原神社例大祭の付け祭りとして江戸時代に始まった。現在は地元の実行委員会が主催する市無形民俗文化財。氏子9町会はそれぞれ、絢爛(けんらん)豪華な屋台を運行する。観衆が気おされるような祭り人の心意気、おはやしのぶっつけは圧巻である。
かつて参加する子どもは一つの町会に数十人おり、祭りは親から子、孫へと受け継がれてきたが、今は4、5人に減った町会もある。多くの祭りや伝統行事に通じる懸案だ。実行委員長の平山一浩(ひらやまかずひろ)さん(61)は「手を打たなければ将来の担い手がいなくなる」と懸念を隠さない。こうした危機感を広く共有したい。
子ども引き手の参加に当たり、参加者側に負担をかけないよう、貸し出し用はんてんや弁当を用意する。はんてんに身を包むこと自体が有意義な体験になるだろう。まずは子どもたちが祭りの良さを体感することが先決である。
子どもを預かる各町会は運行時などに目配りする担当者を設け、安全確保に万全を期す。保護者を含め参加者を引き込むため、安全安心や魅力について継続的な工夫が欠かせない。公的な財政支援の検討も必要となろう。
子ども引き手には、約30人の応募があった。目標に届かなかったが、着手したことで課題も浮かび上がり、持続可能な祭りへの第一歩を踏み出す意義は大きい。取り組みを通じて興味を持つ人が増え、祭りに足を運んで見る立場から体験する側となり、さらに後進に伝える側になる好循環を目指したい。
祭りの時季に戻る地元出身者もおり、絆づくりにも大切な行事だ。付け祭りだった頃、地域のコミュニケーションの場だった。人のつながりが希薄になっているからこそ、原点を見つめ直してもいいのではないか。「屋台まつりをもっとメジャーに」との実行委の願いや待望論のある屋台会館整備も、そうした着実な歩みの積み重ねからだろう。
 ポストする
ポストする