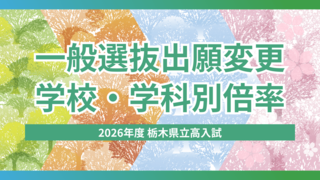県内の児童相談所(児相)と市町による2023年度の児童虐待相談対応件数が過去最多の3828件となった。対応の充実を図り未然防止の仕組みづくりを急ぐべきだ。
県によると、児相が対応した1745件のうち、子どもの前で家族に暴力を振るう「面前DV」などの心理的虐待が921件と最も多い。10年前までは身体的虐待や養育放棄が多くを占めたが、県は「心理的虐待が子どもの心に傷を負わせることが知られてきた」と社会全体で理解が進んだ表れと受け止める。
県は、県内三つの児相の常勤職員数をこの20年間で2倍超の151人(24年)に増員するなど対応を進めるが、十分とはいえない。例えば一時保護した子どもの対応は定員25人の一時保護所では足りず、児童養護施設などに委託するケースが多い。処遇が決まるまで子どもがそこで過ごす延べ日数は、23年度は前年度比1・5倍に増えている。
現在、宇都宮市が独自に児相を設置する計画を進めているが、現場の負担は増している。児相増設を待たず、体制強化を進めたい。
未然防止にも力を注ぎたい。県は虐待増加の背景に「核家族やひとり親など家族の単位が小さくなり育児負担感が増している」ことを挙げる。保護された子どもが措置される代表的な場所に児童養護施設があるが、家庭的な養育を目指す方針の下で里親委託が増え、施設への入所人数は年々減少している。一方、児童養護施設には要保護児童を支援できる人材が集まっており、地域や親族を頼れない家庭が増える現状があるならその資源を生かしたい。
実際、県内では児童養護施設と乳児院の2カ所がそれぞれ、短期間子どもを預かることができるショートステイや親子関係形成支援などを手がける児童家庭支援センター(児家セン)を運営している。
県内市町では母子保健と児童福祉両分野の一体的な支援を行う「こども家庭センター」の設置が進み、現在までに20市町にある。25年度中に全市町に設置される予定で、全国的にも先駆的とされる。
次は、市町と共に支援に当たる児家センの設置を進め、育児に悩む家庭を支えたい。県が25年度から取り組む「社会的養育推進計画」(5カ年)は29年度までに児家センを3~6カ所増やすとしている。計画を着実に実行したい。
 ポストする
ポストする