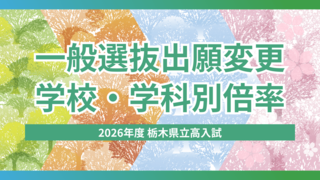人手不足が深刻な県内企業などの外国人材活用をサポートするため県は本年度、宇都宮市にある県国際交流協会内に「とちぎ外国人材受入支援センター」を新設した。外国人向けの語学や日本の商習慣に関する研修の企画、事業者の巡回業務などを行い、企業側のニーズに応じたオーダーメード型の支援に取り組む。
外国人材を巡り国は2027年度までに、原則職場を変えられない技能実習から、同じ業務分野なら「転籍」が可能になる育成就労へ制度を移行させる。制度変更やセンター機能の周知を徹底させるとともに、企業と共に外国人材が安心して長く働ける環境の整備に努めたい。
栃木労働局によると、24年10月末時点の県内外国人労働者数は約3万6千人。国籍別ではベトナムの約9千人をトップに、フィリピン約4100人、インドネシア約3500人と続く。外国人を雇用する事業所も約5200カ所に上り、総労働者数とともに過去最多を更新した。
こうした状況に加え、今後の制度変更で外国人材の需要が高まると県は見込み、今月1日にセンターを創設した。
県は19年度から同協会に外国人材受け入れの相談に対応するコーディネーター1人を配置している。今回はさらに、民間企業などで外国人採用や育成業務の経験を持つ「外国人受入支援コンシェルジュ」2人を新たに採用し、手厚い支援につなげる。
技能実習では長時間労働や賃金不払いなどさまざまな問題が噴出した。職場を原則変えられなかったことが要因の一つとされ、入管難民法の改正などで外国人材が長く働けるよう環境を整え、人手不足の解消を図る。この理念を行政と企業も共有し人材の確保と定着に結び付けるべきだ。
県などでつくる「とちぎ外国人材活用促進協議会」が24年度に実施した外国人雇用に関するアンケート(712社)では、雇用に際して必須な支援として、企業側は日本語能力の向上や住まいなどの生活面、育成のための技術などを挙げている。センターはこうした結果を今後の業務に反映させるべきだろう。
一方、アンケートでは育成就労を「あまり知らない」「全く知らない」が8割強を占めた。まずは新制度とセンターを企業側に認知してもらい、外国人材から「選ばれる栃木」を目指したい。
 ポストする
ポストする