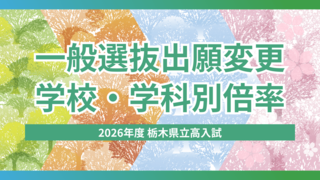真岡市にある親鸞(しんらん)ゆかりの国指定史跡高田山専修寺(せんじゅじ)で、国重要文化財「楼門(ろうもん)」の保存修理、耐震補強工事が終了した。瓦ぶきだった屋根が建築当時のかやぶきに戻され、文化財としての重みが一層増した景観を醸す。17日には落慶法要も営まれる。生まれ変わった楼門を観光資源として活用しながら、地域の宝として大切に守っていきたい。
専修寺は浄土真宗の開祖親鸞が建立した唯一の寺院と伝わる。楼門は江戸中期の建築とされ、老朽化や東日本大震災の影響で棟のずれなどが確認されていた。入り母屋造りで改修前の高さは約9・6メートル。かやぶき屋根に戻したことで約14・8メートルとなった。
今回の工事に伴う解体調査で建築年が1691(元禄4)年と特定されたほか、くぎの形の変化などから過去5回にわたって修理されていたことも判明した。さらに、基礎部分の発掘調査で建築時よりも古い遺構の溝も見つかった。これは親鸞が関わった寺建立当時の姿につながる手がかりとも言え、調査がもたらした大きな成果と評価したい。
国内外を問わず昨今、文化財保護を巡る格差問題がクローズアップされている。寺社の資金力や知名度、支援体制などによって保護状況に大きな差が生まれるという。寺を支える檀家(だんか)の減少、高齢化が進む専修寺でも問題は深刻で、今回の工事も総事業費約2億5千万円のうち国、県、市が大部分を補助したからこそ実現できたと言える。今後は5年ごとにかやぶき屋根のメンテナンスが必要になり、30~40年後には次のふき替え時期を迎える。このスケジュールにどう対応していくかが課題だ。
文化庁は「文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会総がかりで継承に取り組んでいくことが必要」と2019年に文化財保護法を改正。文化財を活用した地域振興を推し進める方針を示した。県も24年度に新たな補助金制度を創設し、文化財の活用を後押ししている。専修寺は県の補助金を活用し、改修された楼門の動画を制作してPRを図っていくという。
このような取り組みを単発で終わらせず、継続させたい。そのためには多方面からの支援が不可欠となろう。5年後には秘仏一光三尊仏像(いっこうさんぞんぶつぞう)の御開帳という一大行事も控える。地域振興へ知恵を絞りたい。
 ポストする
ポストする