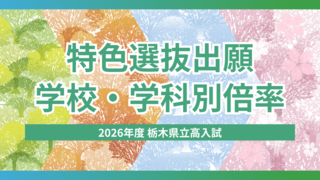改正障害者差別解消法と本県の同推進条例が2024年4月に施行されて1年が経過した。障害を理由とした差別を禁じ、無理のない範囲で困りごとに対応する「合理的配慮」が民間事業者に義務づけられた。だが、県の調査では「合理的配慮」が十分に浸透しているとは言いがたい。県など行政当局はさまざまな機会を利用し、事業者への周知を強化すべきだ。
県が昨秋実施したインターネットアンケートによると、同法や同条例について6割超が「どちらも知らない」と答えた。合理的配慮を知っていたり聞いたりしたことがあっても、事業者に義務づけられたことに関して6割超が「知らない」とし、「知っている」は4割に満たなかった。
合理的配慮を知らないために障害者を差別する結果となることもある。広く周知するにはどのような方法が有効か考えなければならない。
昨年4月以降、県は障害者差別解消をテーマとした県政出前講座を14回開催、ラッピングバスを宇都宮市内などで1年間走らせるなど周知を図ってきた。県のホームページや交流サイト(SNS)を活用してPRするほか、県が包括連携協定を締結している事業所にチラシを配布したりもした。
県は本年度も出前講座を中心に同様の取り組みを続ける考えだが、十分に浸透していない現状を踏まえれば、これまで以上の発信は必要だ。特に事業者が集まる機会に出向いて説明し理解を促すなど、事業者への働きかけを強めるべきだろう。
一方、障害者差別解消に関する県への相談は年々増えており、24年度は前年度比30件増の102件だった。県は、当事者には一定程度浸透していると見ている。
相談は障害者や事業者双方から受け付け、県など自治体は状況を調査するなどして解決を目指す。重要なのは障害者と事業者が対話を重ね、合理的配慮の着地点を見いだすことだ。
宇都宮市では、人工呼吸器を付けた車いすの男性が当初バス乗車を控えるよう求められたが、話し合いを経て乗車できるようになったケースもあった。男性側の求めに対し事業者側が前向きに検討した結果で、合理的配慮の好例と言える。県民の理解が進み、合理的配慮という言葉を使わなくなる社会を目指したい。
 ポストする
ポストする