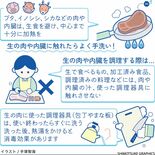大田原高が24日、那須野ケ原を一昼夜かけて踏破する学校行事「強歩」の距離を、本年度は従来の85キロから35キロに短縮すると発表しました。「強歩」は1986年度に始まり、本紙の若手記者も何度か挑戦しています。「強歩」とは何なのか-記者たちが体験した名物行事のルポを紹介します。
(以下、見出しの後の日付は紙面掲載日。市町村名など、記事の表現は原則として当時のままです)
大田原高「85キロ強歩」同行記 雨、奪われる体温…自分との闘い 生徒に自信と連帯感(1997年5月26日)
【大田原】大田原高(遠藤忠校長)で85キロ強歩があると聞き、参加を思い付いた。男子校である同校の強歩は、那須野ヶ原をほぼ一周する恒例の行事。一緒に歩くことで、貧弱だとか軽薄と思われがちな高校生たちが、この過酷な行事をどのように考え、挑戦しているのかを知りたいと思った。

■「完歩しないと勘当だ」
出発は雨天のため一旦順延された二十三日。健康上の理由で参加できない二十人を除く九百十六人が午前十時、二十六時間の長い戦いをスタートさせた。強歩委員長として準備に当たった渋江隼輔君(18)は、これまで二年間完歩した。「最近怒られるようなことをして、父親から『完歩しないと勘当だ』と言われてるんです。でも今日は笑顔で送り出してくれました」と同校ののぼりを片手に歩く。
テレビゲームの話をする生徒。歌を口ずさんでいる生徒-。思い思いに歩く中、一人きりで歩いている生徒を見て別の生徒が声を掛けた言葉が印象に残った。「一人では歩けないぞ。一緒に歩こう」。通常の生活の中だけでは深めることのできない友情や連帯感がこの言頭に込められているような気がした。
ひざの痛みや疲れは、スタートしてから約六時間半後の塩原町に入ったあたりから一段とひどくなった。昼前にやんだ雨がまた降り始め、つらくて立ち止まると、たちまち体温が奪われていく。たまらず動き出すが足は動かない。自分との闘いだと実感した。四十五キロを過ぎた。進もうとしても何としても足が上がらない。どんどん遅れる。つらい。悔しい。でも、高校生がやっているのだから、自分に負けるわけにはいかない。スタートから五十三キロ。やっと休憩所に着いた。既に日付は変わっていた。ひざが全く上がらなくなり、リタイアを決意した。
■「歩いて何になる」批判も
二十四日午前十一時半、ゴールしてくる生徒を正門で迎えた。完歩したの生徒は八割の七百五十六人。先頭グループに渋江君がいた。「これで勘当されずに済みます」と照れ笑い。 「つらかったけど励ましてくれた友人がいたから完歩できました。何年かたてはいい思い出になると思います」と誇らしそうだ。
「八十五キロ歩いて何になる」という批判の声を町で聞いた。こうした声に対し、「理屈じゃないんだ。やってみないと分からないものだと思う」と遠藤校長。確かに五十三キロ歩いた私に残ったものも、目に見えるものは何もない。しかし一緒に歩くことで、高校生たちの強さや友情を知ることができた。完歩した生徒たちにはほかでは得られない充実感と「やればできる」という自信が残った。それも強歩を実施する意味の一つではないだろうか。
大田原高85キロ強歩ルポ 伝統の“耐久戦”に挑戦 不撓不屈の精神実感 父母や住民の温かさも(2002年5月30日)
【大田原】大田原高(八百三十四人)で二十三日、恒例の「八十五キロ強歩」が行われた。生徒八百二十三人が、県北の五市町村(大田原、黒磯、矢板、塩原、黒羽)を通過するコースを夜通し歩き続け、約二十六時間かけ八十五キロを歩き抜く“耐久戦”に同行した。

午前十時、晴天の下、関係者に見送られて校門を出発。長い道のりを考え、二食分の食料、防寒着をリュックに詰め、生徒たちの後を追った。
■新緑楽しみ歩く
暑い日差しの中、生徒たちの表情はハイキング気分のように明るい。サッカーのワールドカップの話題、歌いながら歩く生徒。矢板市を通過して約三十キロ歩き、薄暗くなった塩原町に入る。箒川の渓流と新緑が美しい。まだ余裕がある。
那須野ケ原を北上して五十四キロ地点の黒磯中に到着。時計は既に午前零時を回っていた。靴下を脱ぎ、靴擦れの傷を治療する生徒も現れた。自分も足の指にまめができ、くるぶしがはれる。
このころから、生徒たちの言葉数が減り、自分との戦いが始まった。二-七キロ間隔で設けられた休憩地点で、ぐったり横たわる生徒が目立つ。互いに「あきらめずに完歩を目指そう」。言葉を掛け、足をマッサージし合う光景が見られた。
深夜にもかかわらず、コースには約五十メートルおきに、保護者が数人ずつ立って、事故がないよう誘導役を担当。伝統行事を支える関係者の熱意に頭が下がった。
■励まし励まされ
夜明けを迎えた午前五時、黒羽町の観光やなに到着。極度の疲労で朝食を取れない生徒も。「ここまで来たんだ。最後まで行こう」と、あちこちで話している。自分も励まされ、生徒たちの応援を裏切れない。
ゴールの校門まで数キロ。大田原市の中心商店街の人が歩道で、氷やクッキーを振る舞う姿に、地域住民の温かさを感じた。
午前十一時半すぎ、続々とゴール。生徒たちに笑顔が戻った。完歩者七百三十七人。強歩の目的「不撓(ふとう)不屈の精神の確立」が実感できた。
大田原高「強歩」体験ルポ 85キロ 痛みと闇乗り越え 充実感に包まれゴール 伝統支える熱意実感(2006年6月1日)
【大田原】大田原高(七百六十人)で五月二十五日から二十六日にかけて、恒例の「八十五キロ強歩」が行われた。北那須地域で知らない人はいないというほどの名物行事。二十一回目の今年は七百四十二人の生徒が大田原、矢板、那須塩原の県北三市を通過するコースに挑戦した。夜通し歩き続け、約二十六時間かけてゴールを目指す“過酷な伝統行事”に同行した。

■不安と疑問も
八十五キロといえば、大田原から小山市の自分の実家までの距離とほぼ同じ。「挑戦は無謀だったか」と出発前に不安がよぎる。
「最後の方になると下半身全部取り替えたくなりますよ」。午前九時四十五分の出発直後、陸上部に所属する三年生が笑いながら言った。歩き続けていると足のあらゆるところが痛くなるそうだ。過去二回完歩している三年生の言葉だけに説得力がある。
なぜ、そんな行事に生徒たちは参加するのか。早くも疑問がわいた。
スタートから十五キロほど歩き矢板市に入る。日中、日陰のない田園地帯を歩いていると、初夏を思わせる日差しが想像以上にきつい。
さらに北上し那須塩原市に。箒根中で持参した夕食を取り、さらにひたすら歩く。
周りが闇に包まれた深夜一時すぎに約五十六キロ地点の黒磯中に到着。この辺りが強歩で最もつらかった。一歩踏み出すたびに足全体に痛みが走る。足を引きずりながら歩く生徒や休憩所でぐったりと横になる生徒が目立つ。
■リタイア寸前
歩きながら何度も「リタイア」が頭をよぎる。足の痛みがピーク。まめもできた。救護医の皆さんの世話になることに。 医者のほとんどが同校OB。まめの治療を丁寧にしてもらい、筋肉痛を和らげるスプレーをしてもらう。
周りはさながら野戦病院の様子。多くの生徒が次々に治療に来る。「これでよく歩けたな」と医者があきれるほどのまめを作り、足の裏全部をテーピングしてもらった一年生。「これからどうするの」と聞くと、「もちろん歩きます」ときっぱり。
治療のおかげで少し楽になった足で未明の道をひたすら歩く。午前三時。「夜中が一番つらい。寂しさが襲ってくる」と事前に聞いていた。自分の世界に入り、ひたすら歩いた。生徒たちも無口になっている。
夜明けを迎え、午前七時に川西中に到着。ゴールが目前に迫り不思議と歩く気力が戻ってきた。生徒たちも「もう少しだから絶対にゴールしよう」と気合を入れ直す。
午前十一時すぎ、大田原高に戻ってきた。父母たちが正門の両脇に列を作り拍手で迎える。涙を流す生徒の母親も。ついにゴール。充実感ともう歩かなくていい安堵(あんど)感に包まれた。
伝統支える熱意実感
大田原高の「八十五キロ強歩」を終えて、約二十年間続いてきた伝統行事の重みとそれにかかわる人々の熱意を感じた。
先生方や生徒の保護者、同校OB、地域の方々など多くの人の惜しみない協力があった。生徒の安全を守るために出発からゴールまで、強歩のコースに立って誘導し「頑張れ」と声を掛ける。
三-七キロごとにある休憩所では真夜中でも冷たい飲み物や食事などが用意され、傷の治療をする医者も同校OBが多い。どれだけの人が携わっているか見当もつかない。
今年は六百九十人の生徒が完歩し、完歩率は93%。完歩した生徒も途中でリタイアしてしまった生徒も、自分の力だけで歩いたと思っている生徒はいないのではないか。
藤田一夫校長が生徒に話したように「歩くことで感謝を学ぶ」が、同校の校訓「不撓(ふとう)不屈の精神の確立」につながっていることを実感した。
一昼夜85キロ踏破に達成感 本紙記者体験ルポ 大田原高、伝統の「強歩」 地元の温かい支えを実感(2019年5月28日)
【大田原】16~17日に行われた大田原高の「85キロ強歩」。大田原、矢板、那須塩原の3市を一昼夜歩き通す厳しい伝統行事に、入社2年目の記者が挑戦した。暗闇で感じた孤独感、足の痛みと、生徒や地域住民らの温かい励まし。約26時間後のゴールには、日常生活では得難い感動が待っていた。

16日午前9時40分。大勢の保護者らに見送られ、曇り空の下を生徒たちが意気揚々と歩き出す。私も2食分の食料や水筒、上着などを詰めたリュックを背負い校門を出た。胸が高鳴る。
■保護者に感謝
約9キロ歩き矢板市へ。雲の切れ間から初夏の日差しが降り注ぎ始め、頬が火照る。コースには3~4キロごとに休憩所が設けられており、保護者らが用意してくれた水や氷がありがたい。
那須塩原市へと北上し、約35キロ地点の「道の駅湯の香しおばら」で夕食を取った。ここで日没を迎えたが、体はまだ余裕がある。
深夜。コースの各所に教職員や保護者が立ち、「頑張れ」と励ましながら誘導する。安全を守り行事を支える努力に頭が下がった。
出発前は、ひそかに自信のようなものがあった。学生時代、トライアスロンや陸上の経験があったからだ。しかし、次第に足の裏から太ももまで痛みが広がってきた。眠気との戦いも始まり、休憩所に寄るたびに足取りが重くなった。
同校OBの医師らによる救護団の治療を受ける生徒もいたが、元気そうに歩く生徒が目立つ。前を歩く3年生に話し掛けると、「きつい時こそ楽しもうと思って」と笑顔。「うつむかず遠くを見た方がいいと先生が教えてくれた」。確かに心が折れかけ、下を向いてばかりだった。顔を上げると、気分も少し前向きになった。
■夜明けの空気
大田原市の黒羽地区へ入る直前で夜明けを迎えた。爽やかな朝の空気に包まれると、再び気力が湧いてくる。人々が家の前に立って旗を振ったり、農作業の手を止めたりして声援を送ってくれる。行事が地域に定着していることと、住民の温かさを感じた。
午前11時すぎ。同校校門が見えてきた。沿道の大歓声と拍手を浴び、正門をくぐってついにゴール。道中の苦しさが吹き飛ぶほどの達成感がこみ上げた。
完歩した生徒もリタイアした生徒も、前向きに行事に取り組み、ゴールに向かって努力する姿には感銘を受けた。
私も大勢の人に励まされて何とか歩き抜くことができ、同校の校訓「不撓不屈(ふとうふくつ)」の精神を学んだ。この経験があれば、今後はどんなに体力勝負の取材でも乗り越えられそうだ。
 ポストする
ポストする