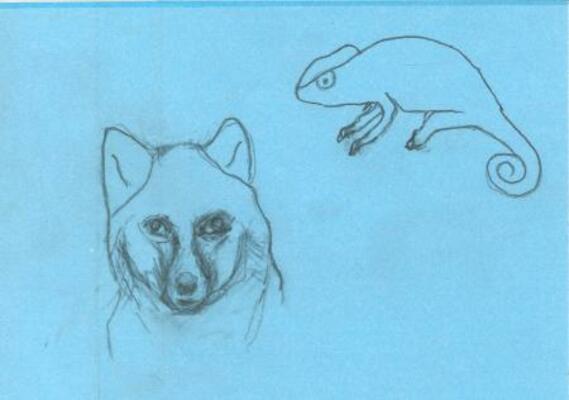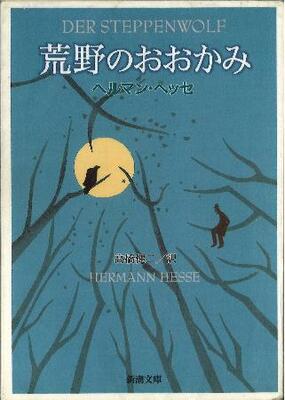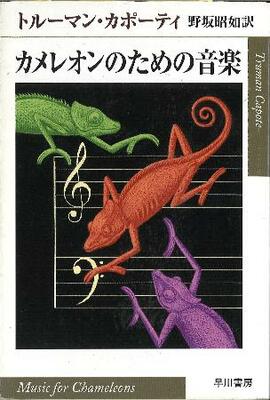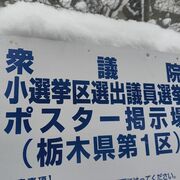ヘルマン・ヘッセ(1877~1962)が青春の苦悩を抒情的に描いた自伝的小説『車輪の下』(1906年)を読むことはある一時期、いやかなり長い間、思春期の通過儀礼のようなものだった。少なくとも私が10代半ばのころ(既に半世紀以上前のことだ)は確かにそうだったし、おそらく、それ以前もそれ以後も、この位置付けはあまり変わらずに続いてきたのではないだろうか。
しかし、ヘッセを読み続けて『荒野のおおかみ』(1927年)にまで至る人はそう多くなかったと思う。こちらは五十絡みの男の屈折した内面に目を向けた、皮肉っぽく、幻想的で、そしてエロティックな小説である。今回取り上げようと思ったのは、主人公が幻覚の中でモーツァルトに出会う場面があるからだが、まずは同書が1960~70年代のアメリカで若者に大きな影響を与えたということから始めたい。ヘッセの愛読者やカウンター・カルチャーに詳しい人々以外にはあまり知られていない、あるいは忘れられている事実だと思うので、長い前置きになるがお許しいただきたい。
1971年に出た新潮文庫版の解説で、訳者の高橋健二が「一九七〇年のアメリカの若者が、『荒野のおおかみ』に共鳴し、そういう名のロックンロールのグループを作り、ヒッピー族がヘッセを現代の聖者に祭りあげているのも、ヘッセが四十年前に、二十世紀後半の精神的状況を先取りして感じとっているからである」と書いている。これはどういうことだろうか。
主人公のハリー・ハラーは、モーツァルトとゲーテの芸術に精通したインテリで、市民的な暮らしに感傷と憧れを抱いているが、その一方で、体制に同調できない<荒野のおおかみ>のごときアウトサイダーだと自己認識している。戦争反対の意見を表明して保守派から攻撃されることもしばしばだ。さらに、彼はアンダーワールドの若い男女と知り合って陶酔的なセックスやドラッグを体験し、最後は幻覚の世界<魔術劇場>に誘い込まれていく。こうしてみると、ベトナム戦争当時のアメリカで読まれるにふさわしい条件がいくつも揃っていたわけである。
ドイツ文学者ルードルフ・ケースターの論文『現代アメリカとヘッセ』(『ユリイカ』1982年4月号のヘッセ特集に収録)に付された資料によると、1969年から1976年上半期までに『荒野のおおかみ』の英訳本は160万部売れたという。1971年刊行の『シッダルタ』も140万部に達していた。1970年に出た『車輪の下』は46万部だった。
評論家コリン・ウィルソンの『アウトサイダー』(1956年)で『荒野のおおかみ』が大きく取り上げられていたこと、<サイケデリック・ムーヴメントの父>と呼ばれた心理学者ティモシー・リアリーが「LSDをやる前に『シッダルタ』と『荒野のおおかみ』を読んでおけ」とけしかけていることも付け加えておこう。
日本のヘッセ受容は多分に教養主義的だったが、アメリカの動きを察知している人がいなかったわけではない。五木寛之の短篇小説『悪い夏 悪い旅』(1970年)は古書店で買ったヘッセ作『春の嵐』の文庫本に大麻草の葉が挟まっていたことから展開していく物語だ。話者の<ぼく>はそれまで読みもせずにヘッセを軽蔑していたが、知人から「あっちのヒッピーたちの間でヘッセが盛んに読まれている」という話を聞いてこの本を買った。
「そういう名のロックンロールのグループ」は、『荒野のおおかみ』の原題が<Der Steppenwolf>であると言えばそれ以上の説明は不要だろう。ハード・ロック界の雄ステッペンウルフが1968年に放ったヒット曲『ワイルドでいこう!』(Born To Be Wild)は、映画『イージー・ライダー』の挿入曲としても有名だ。『悪い夏 悪い旅』が収録された文藝春秋版五木寛之作品集(3)の解説で、植草甚一はステッペンウルフを知ったとき「いい名前をつけたなあ、こいつはヘッセの『荒野の狼』の原題じゃないかと思った」と書いている。
さて、ここからは、高橋訳を引用しながら小説の中身について話を進めていくことにしよう。
ハリーは当世の風潮にいらだっている。「もし世の中が正しいとするならば、カフェーの音楽や、大衆娯楽や、あんなに安直なものに満足しているアメリカ的な人間が正しいとするならば、私はまちがっており、気が狂っている」。彼が愛しているのはモーツァルトやヘンデルの音楽だが、酒を飲んで街を歩けばダンスホールから激しいジャズがこぼれだしてくる。この手の音楽をひどく嫌っているハリーだが、実はひそかに魅力を感じてもいる。「私は一瞬鼻をひくひくさせながらたたずんで、殺伐などぎつい音楽のにおいをかぎ、これらのホールの雰囲気を邪心と欲情をもってさぐった」
ある夜そんな店のひとつに迷い込み、<男たちをほれこませる腕>で暮らしている美少女ヘルミーネと知り合った。生きるために苦労をしていると語るハリーに、ヘルミーネは<シミー>を踊ろうという。シミーは前後に肩や胸を振るわせるセクシーなダンスだ。ハリーはシミーどころかワルツもポルカも踊れない。単純なワンステップさえもだめだ。ヘルミーネはあきれてこう言う。「踊ろうとさえしないで、生きるために骨をおったなんて、どうして言えるの?」
ところでヘッセ自身はダンスを踊ったか。臨川書店版ヘルマン・ヘッセ全集(第13巻)の解説で里村和秋が引用している1926年の書簡には、こんな事が書かれている。「最近の私の生活は不安定で変化の多いものでした。(中略)私は若いプレーボーイのように暮らし、頻繁にダンスに通い、現代生活における軽薄な快楽をさんざん漁ったのです」。やはりそのくらいの経験がないと、この小説は書けなかっただろう。
作品に戻れば、ヘルミーネはハリーにダンスを教え、女友達のマリアに彼を誘惑させた。ハリーは彼女たちの友人でもあるジャズバンドの楽師パブロに紹介され、彼の手引きで何種類かの麻薬を体験した。マリアとのあいびきで一緒に使ったこともあった。ここでちょっと覚えておいていただきたいが、パブロはハリーをひとめ見てすぐ、笑うことのできない気の毒な人だと見抜いていた。後になってハリーはそのことをヘルミーネから知らされた。
また脱線するが、パブロが演奏する曲は『ヤーニング』や『ヴァレンシア』である。どちらも1920年代半ばのヒット曲で、ダンス音楽の枠を超えたスタンダード・ナンバーになっている。前者はニューオリンズ・ジャズからスウィング・ジャズ、ウエスタン・スウィングまでさまざまなスタイルで演奏され、フランク・シナトラも歌った。後者は同名アメリカ映画の主題歌。クラシック畑のプラシド・ドミンゴやホセ・カレーラスも取り上げている。
小説の最後で、ハリーはヘルミーネたちと仮装舞踏会に来ている。パブロの案内で小部屋に入り、異様な味の液体を飲み、長く黄色い巻きタバコを吸うと気分が活気づき、<ガスでみたされて、重みを失うような感じ>を味わった。その状態で部屋を出ていくと、目の前に現れたのは幻想空間<魔術劇場>だった。ハリーはそこでいくつもの荒唐無稽な体験をするが、最後に『ドン・ジョヴァンニ』が鳴り響き、甲高く冷たい笑い声と共にモーツァルトが登場する。
ここから先は話が込み入ってくるので要点だけ言うと、モーツァルトはハリーに欠けていた<笑うこと>を教えた。ラジオ(当時の音質は非常に悪かった)でヘンデルの音楽を聴かせ、ハリーが「こんな鼻持ちならぬ器械を、われわれの時代の勝ちどきを、芸術にたいする全滅戦において勝ち誇る最終兵器を、われわれに向けてぶっ放すのですか」と悲憤慷慨すると、楽聖は次のように答えた。「ヘンデルはこんな鼻持ちならぬ現れ方をしても、やはり神々しいのだ」。そして後に「(君は)人生ののろわれたラジオ音楽を聞くことを学ばねばならない。その背後にある精神をあがめなければならない。その中の空騒ぎを笑うことを学ばねばならない」と諭した。
<空騒ぎ>とは放送の雑音かもしれない。あるいは雑多なプログラムのことかもしれない。いずれにせよラジオは現代生活の比喩だろう。モーツァルトの言葉は人生全般にかかわる忠告である。その命令を聞かなければどうなるかとハリーが尋ねると、モーツァルトは「そしたら、わしは君にわしの上等のタバコを一本吸うように提議するだろう」と穏やかに言って彼に一服を勧めた。その瞬間、モーツァルトの姿はパブロに変わった。ハリーは甘く濃い煙に包まれて「ああ、私はすべてを理解した。パブロを理解し、モーツァルトを理解した」と直感して新しい生き方に目覚める。いささか飛躍のある結末で、けむに巻かれたような気がしないでもないが、不思議な余韻が残る。
ローン・ウルフの目まぐるしい自己探求の日々(高橋健二はあるところで『荒野のおおかみ』を<精神分裂症的な狂躁曲>と呼んでいる)はここでひとまず終わった。次にトルーマン・カポーティ(1924~1984)の洒落た短篇『カメレオンのための音楽』(1979年)を楽しむことにしよう。アメリカの高級週刊誌『ニューヨーカー』に発表されたこの作品は一応、紀行文とされているが、描き方は全く小説風だ。そんな区別はどうでもよいが、とにかく独特の雰囲気に包まれた、魅惑的な小品である。本作を標題にした短篇集が現在、野坂昭如の訳でハヤカワepi文庫に入っている。
カポーティは『ティファニーで朝食を』の作者として最も知られるが、都会的な小説を書いたばかりでなく、一家殺人事件を扱ったノン・フィクションの大作『冷血』があるし、映画に関わったり、派手な私生活で知られたりと、自分自身がカメレオンのような人物であった。しかし、この作品で語られるのは、正真正銘、爬虫類のカメレオンの方である。それも音楽が好きな!
<私/カポーティ>は今、カリブ海に浮かぶマルティニーク島のフォール・ド・フランスを訪れている。優雅を絵に描いたような貴族女性――「背が高くて痩せぎす、年の頃七十前後。すこぶる身だしなみが良く、そのラム酒のような淡い褐色の肌に、銀髪がまた素晴らしく合う」(野坂訳、以下同)――の住まいに招かれ、少量のアブサンを加えたミント・ティーをいただきながら、彼女がフランス語を交えて次々に語る奇妙な話を聞いている。この家にはたくさんの幽霊が出ること、夜になると巨大な蛾の大群が庭に集まって乱舞すること、彼を乗せてきてくれた品の良い運転手が実は妻殺しの脱獄囚であること…。
カメレオンが3匹、テラスを横切ってきた。カメレオンは音楽が好きなのだとマダムは言う。本気にされていないと思うと、彼女は嘘でない証拠をお見せしましょうと客間のピアノに向かい、モーツァルトのソナタを弾き始めた。
すると、緑、緋色、藤色などのカメレオンが10匹も20匹も、素早くテラスを横切って集まってきた。「いずれもまこと熱心に、またうっとり妙なる調べに聞き惚れる態」だったという。演奏を終えたマダムが立ち上がり、床を踏みならすと、カメレオンの一群はたちまち姿を消した。
すべてカポーティの実体験通りかどうかは謎だが、印象的な場面だ。ところで、このとき弾かれたモーツァルトのソナタはどれだったのだろう。作者は何も書いていないから、しばし想像にふけってみる。うっとり聞き惚れたのなら、極端に速くも遅くもない、美しい楽章ではないか。ソナタ11番イ長調(トルコ行進曲付き)の第1楽章あたりが合いそうに思われるが、おそらく読者ひとりひとりに異なった意見があるだろう。
閑話休題。カメレオンの音楽鑑賞に驚かされたあと、カポーティは机の上に置かれたブラック・ミラー(表面が黒っぽい鏡のことで、野坂は黒鏡と訳している)に目を留めた。マダムによると、元の持ち主は、マルティニークにもいたことのあるゴーギャンで、19世紀の画家たちは視覚をリフレッシュさせ、色彩と色調に対する反応を新鮮にするため、このような鏡を使っていたのだという。
黒鏡に映った風景は色彩が抑えられるので、それを参考にして柔らかな色調の絵を描くことができる。また、実際の風景をそうした絵画のように見ることもできる。18世紀ごろに一部の画家や旅行者が愛用した。一方、ゴーギャンの絵画はヴィヴィッドな色遣いが特徴だから、彼が黒鏡を持っていたとしても、そのような使い方をしたとは考えられない。マダム自身は眩しい日光にさらされた時、目をいやすのに利用するという。カポーティは鏡を手渡されたが、どことなく不安な気持ちがよぎった。暗闇を見つめているうちに幻想世界へ引き込まれるのではないかと。
マダムの澄み切った声が聞こえてきた。「そういえば、こちらでお気の毒なことになったお友達がいらしたのね」。カポーティが答える。「かなり才能のある奴でした。音楽家、作曲家でした」「名前は、マーク・ブリッツスタイン」
ブリッツスタインについては少し詳しい説明が必要だろう。1905年にフィラデルフィアで生まれ、1964年にマルティニーク島で没した。彼の名前を一躍有名にしたのは、労働運動をテーマにし、オーソン・ウェルズが演出を担当したミュージカル『ゆりかごは揺れる』(The Cradle Will Rock)である。
左翼的な内容を危険視し、上演中止を求める経営側や保守派の突き上げを受けた政府は、プレヴュー開始の直前に劇場を封鎖し、装置や衣裳の持ち出しを禁じた。オーケストラも雇えなくなり、俳優組合は組合員が舞台に立つことを禁じた。しかしスタッフとキャストは別の劇場を確保し、なんとか幕を開けることができた。苦肉の策で舞台にはただひとりブリッツスタインがのぼることとし、客席内に散らばった俳優たちが彼のピアノに合わせて歌い、せりふを語ったのである。翌日、ニューヨークの新聞はそろって一面で報じ、演劇史に残る事件になった。後年再演された舞台の映像はYouTubeで見ることができる。
ブリッツスタインを尊敬する音楽家の1人に、レナード・バーンスタインがいた。ハンフリー・バートンは『バーンスタインの生涯』(青土社刊 棚橋志行訳)で「アーロン・コープランドにつづいて、ブリッツスタインは作曲家として、またひとりの人間としてバーンスタインの成長に最大の影響を与えたアメリカの作曲家である」と書いている。バーンスタインはハーバード大学時代に『ゆりかごは揺れる』を上演し、それをきっかけに作曲者の知遇を得た。1946年には彼の交響曲<The Airborne>をニューヨーク・シティ交響管弦楽団と録音し、友情はブリッツスタインの死まで続いた。
単独の曲では『アイ・ウィッシュ・イット・ソー』がよく歌われる。ソプラノ歌手のドーン・アップショーが同名のアルバムに入れているほか、ジャズ歌手のローズマリー・クルーニーも録音している。両者を聴き比べてみるのも面白い。
寄り道が長くなった。本筋に戻ろう。マダムが「お気の毒なことになった」と言ったのはもちろん、ブリッツスタインがこの地で亡くなったことを指す。原文では<murdered>。殺されたのである。彼女はおぼろげな記憶をよみがえらせた。「その方、夕食にお見えになったことがありましたわ」。彼はピアノでドイツの曲をいくつか弾いたという。<ドイツの曲>は山ほどあるが、ひょっとしてクルト・ワイル作曲の何かを弾き、歌いはしなかったか。ブリッツスタインはブレヒトとワイルによる『三文オペラ』の挿入曲『マック・ザ・ナイフ』の訳詞者だ。エラ・フィッツジェラルドやルイ・アームストロング、そのほか数え切れないほどの歌手が、この曲を彼の詞で歌っている。ちなみにテナー・サックスの巨人ソニー・ロリンズは、同じ曲を『モリタート』の題で録音した。
「家でのことは思い出しましたけど、あの方がどうして亡くなったのかは思い出せませんわ。誰がそんなことを」とマダム。カポーティは膝の上に置かれた黒鏡に目を落とした。「私の胸のうちにうごめくもの、触れてはいけない話題、それは、やがて明確な形をとり、言葉となる。言葉のもたらす、暗い予感を意識しながら」
カポーティが重い口を開いた。「船乗りの二人です」。地元の者ではなく、ポルトガル人だった。「友人はその二人に酒場で出会ったんです。友人はオペラの仕事でこちらに来ていて、一軒家を借りてたんですが、二人を家に連れ帰って――」
マダムもブリッツスタインが船員に撲殺されたことを思い出した。カポーティが「悲惨な事故でした」と言うと、黒鏡があざわらった。「何で言わないんだ、事故なんぞじゃなかったと」
ブリッツスタインはゲイだった。酒場で出会った船員は3人が正しいようだ。殺された場所は家ではなく路上で、持ち物も服も奪われた。詳しい事情は分からないが、事件の陰にはホモセクシャルな背景がのぞいて見える。
カポーティが黒鏡から目を上げたとき、マダムは再びピアノを触っていた。前のときと同じく、彼女の周りに赤、緑、紫のカメレオンが集まってきた。「テラコッタのテラスの床の上に並んだこの聴衆は、手書きのお玉杓子にそっくり。モーツァルトのモザイク模様だ。」という見立てが最後を飾る。魅力的なマダム、音楽に反応するカメレオン、謎めいた黒鏡、そしてブリッツスタインの不幸な死を見事に重ね合わせたカポーティの文章術は実に巧みだ。(松本泰樹・共同通信記者)
まつもと・やすき1955年信州生まれ。ハリーに笑うことを教えるのも、カメレオンをうっとりさせるのも、モーツァルトでなければならない気がする。少なくともベートーヴェンではしっくりこないと思うが、どうだろう。
 ポストする
ポストする