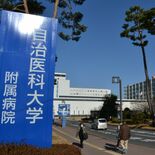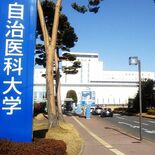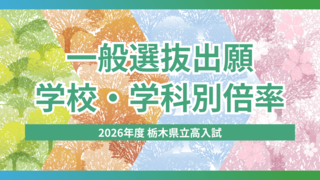県の「救急医療提供体制のあり方に関する検討委員会」のワーキンググループが8日、県庁で開かれ、県は高度救命救急センターの設置を検討することや、救急患者受け入れコーディネーター(仮称)を配置する方針を示した。急速に進む高齢化などに伴って救急医療の需要が高まる中、受け入れ態勢や病院間の連携を強化することで、重症度や症状に応じた適切な医療機関での受け入れを目指す。
県内の救急搬送人員数は増加傾向にあり、特に75歳以上の高齢者や中等症患者の搬送数が急増している。現状は重症度に関係なく患者が2次、3次救急医療機関に集中しているため、県は救急医療機関の機能分化を進め、高次医療機関の負担を減らしたい考え。
これまでの議論を踏まえて県がこの日示した提言の骨子案では、焦点となっていた高度救命救急センターについて、設置を検討することが初めて盛り込まれた。同センターは救命救急センターでも受け入れが困難な患者の治療を担う組織で、関東では本県が唯一設置されていない。
早期の設置か、理想を追求か 委員間でも認識に違い
「看板の掛け替えで人材は集まらない」「取り組めるところから取り組むべきだ」。8日に開かれた県の救急医療体制のあり方に関する検討委員会ワーキンググループでは、高度救命救急センターの形や設置時期を巡り、一部委員と県との間で意見が対立した。設置を急がず最初から理想の診療機能を追求すべきか、現状の救命救急センターの機能を強化して早期に設置すべきか-。委員間でも認識の違いが浮き彫りになった。
残り:約 961文字/全文:1630文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする