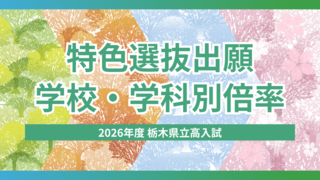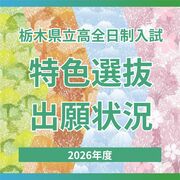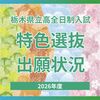「政治には金がかかる」。よく聞く決まり文句だが、果たして本当だろうか。中でも多額の金が必要とされる選挙で、選挙運動費用が余り、その「余剰金」の行方が不明瞭となっているケースが少なくないことが下野新聞社の取材で判明した。
自民党派閥の裏金事件などを受け、政治家の不透明な金の動きには国民から厳しい視線が注がれている。政治とカネの問題は、政治不信の最大の原因である。疑念を抱かれないよう、議員自ら改善に努めるべきだ。
2021年衆院選、22年参院選で当選した県内国会議員8人を対象に、本紙は選挙運動費用収支報告書などを詳しく調べた。余剰金は選挙運動に伴う収入からポスター代などの公費負担分を除く「実質的な支出」を差し引いて算出し、8人で計7200万円超に上った。3人が1千万円以上で、最多は約1988万円だった。
多額の余剰金がすぐに問題になるわけではない。問われるのはその処理の仕方だ。余剰金と同額を選挙後間もなく自身が代表を務める政党支部に寄付し、政治資金収支報告書上で使途が分かるように処理していたのは立憲民主党の藤岡隆雄(ふじおかたかお)衆院議員のみだった。余剰金481万4946円を1円単位で報告書に記載していた。「私的に使ったとの誤解を招かぬよう、透明性を確保した」と藤岡氏は説明する。選挙を明朗かつ信用あるものとする公選法の本旨からもっともな対応だ。
一方で、本紙の取材に3人は余剰金を政治団体に寄付しておらず、別の3人は複数年に分けて寄付していると回答した。これでは余剰金をどう処理し、何に使ったのかを第三者はチェックすることができない。
余剰金の取り扱いについて公選法には規定がない。ただ、選挙運動費用には大半の場合、政党支部からの寄付金が含まれており、税金を原資とする政党交付金にひも付く。公的な性質を帯びるものであるのに、仮に私的に流用されても違法ではない状態は納得できない。
余剰金の処理は、長く見過ごされてきた問題の一つだろう。公選法を見直し、使途を明確化すべきだ。現状で法に不備があるとしても、議員側は余剰金を政治団体に寄付するなどして使途を明らかにする必要がある。
 ポストする
ポストする