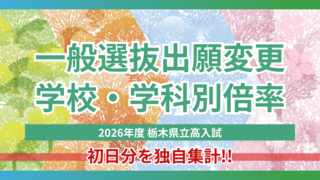上三川町で発見されたゾウムシが国内初確認の外来種と分かり、県立博物館が日本在来の生物多様性への影響などを調査している。現時点で害虫と断定できる要素はないが、県内の在来植物に大きな被害を及ぼしている特定外来生物クビアカツヤカミキリの例もある。早期の生態解明とともに、外来種について同館や県は県民に幅広く情報提供すべきだ。
ゾウムシは昨年4月、同町で開かれた自然観察会に参加した小学生が雌雄1匹ずつを中国原産の落葉高木ニワウルシから見つけ、とちぎ昆虫愛好会を通じ同館へ提供した。昆虫分類学が専門の栗原隆(くりはらたかし)学芸員(48)らが調査を進め、国内で初めて確認したことを愛好会メンバーらと論文で発表した。中国や台湾が原産のクチカクシゾウムシの一種とみられ、同館などが「カタビロシンジュクチカクシゾウムシ」と和名を付けた。
最新の調査では、上三川町と真岡、下野、小山、宇都宮、壬生の計6市町で100匹以上を採集。全てニワウルシで発見されているという。
気掛かりなのは、中国ではニワウルシの葉を食い荒らす害虫とされていることだ。ゾウムシに在来植物を食べる様子は確認されていないが、栗原学芸員は「ニワウルシに似た在来種のニガキを食べる可能性はある」と指摘する。
県内15市町で確認されたクビアカツヤカミキリの被害は2017年度に県南地域で初確認され、数年で県内各地に拡大した。駆除が課題となっているだけに、ゾウムシが害虫とされた場合は早急な対策が必要だ。一方、ゾウムシが発見されたニワウルシは生態系に悪影響を与える「侵略的外来種」に選定されている。考え方を変えれば、成長が早いニワウルシの除去に効果を発揮する余地もある。
在来種を守るには、外来種を無意識に屋外へ放つことがないよう県民が正しい知識を得ることも重要だ。現在、同館で開催する外来生物を巡る企画展は、県民に外来種と環境保全を意識してもらう一つの機会になるだろう。
県内で近年、外来種の発見が相次いでいるという。温暖化に伴う環境の変化とともに外来種が定着すれば、県民生活にさまざまな影響を及ぼすことも想定される。ゾウムシの生態解明にとどまらず、同館などは外来種に関した情報発信を続けてほしい。
 ポストする
ポストする