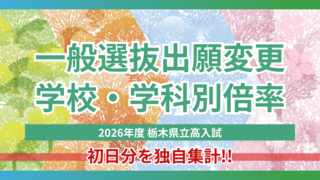コメの品質を低下させ、収量が減る原因にもなるイネカメムシの被害が県南を中心に懸念されている。昨年来のコメの価格高騰を招いた要因の一つとして指摘されている。コメの安定供給が求められる中、減収を防ぐため県や市町、農業団体は生産者と危機感を共有し、対策を徹底する必要がある。
県南地域では昨年、国道50号の南側を中心にイネカメムシの大量発生が確認された。田んぼによっては収量が大幅に減少したとされる。
イネカメムシは稲の主要害虫で、1950年代から減少し本県を含む一部地域では絶滅危惧種に指定されていた。しかし2000年代に西日本で被害が確認され、10年ごろから関東にも徐々に拡大してきた。温暖化などの影響とみられる。
県農業総合研究センターによると、本県でも21年に県南の自治体で発生が確認され、24年は県南と県央を中心に15市町に拡大した。このうち小山、栃木、足利、佐野、下野、野木、壬生の7市町では、今年1~3月の調査で越冬が確認された。
イネカメムシなどによる農産物の被害を食い止めるため、県は今年、関係機関や農業関係団体と「カメムシ防除作戦」を始めた。薬剤散布の指導や発生状況の情報発信、発生予測調査などに取り組んでいる。
県南では地域ごとに一斉に行う共同防除計画を見直し、イネカメムシが活発化する出穂期に合わせ、薬剤散布を7月中旬に早める地域もある。発生状況によっては、農家が個別に対策を講じなければならないケースもある。こまめな見回りと迅速な情報共有が重要になる。
ここ数年でイネカメムシが急増した埼玉県は今年、100ヘクタール以上の広域防除を実施する団体へ補助金を新設した。栃木県内でも市町によって補助金や、農業共済組合による助成もあるが、被害が拡大する場合は国や県による支援策の検討も迫られるだろう。
イネカメムシは今後、県内全域に拡大する可能性もある。全県で危機感を持つべきだ。そのためには県の役割が重要である。発生状況に応じて「イネカメムシ注意報」といった分かりやすい形で警鐘を鳴らしてはどうか。被害の実態把握や発生予測の精度向上、効果的な対策の検討に努めてほしい。
 ポストする
ポストする