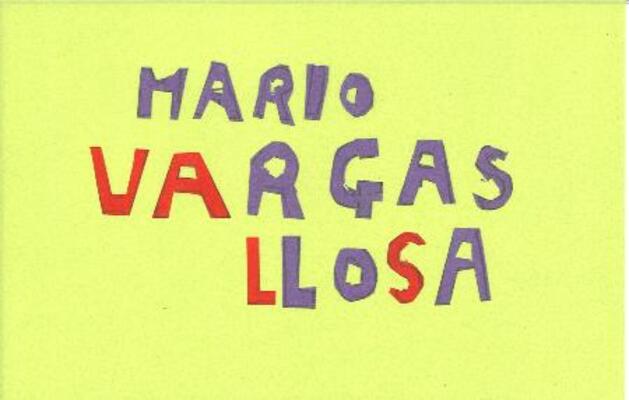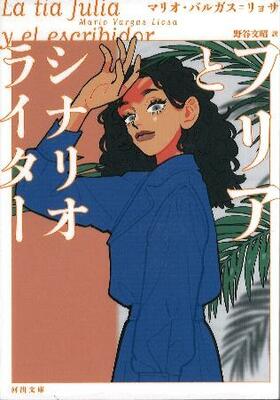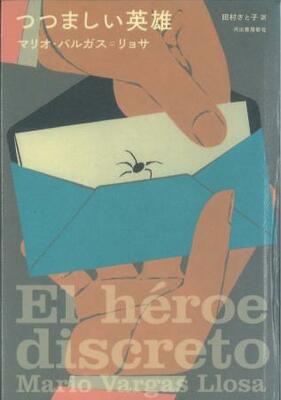今年4月に亡くなったペルーのノーベル賞作家、マリオ・バルガス=リョサ(ジョサ)は、ストーリー・テラーとして傑出した才能を持ち、巧緻な構造、独創的な文体、社会への鋭いまなざしなど、幾つもの観点から総合的に論じられている巨匠である。しかしまた、彼が小説の中にしばしば登場させた音楽――特に<ムシカ・クリオージャ(クリオーリャ)>と呼ばれる母国の大衆音楽――に興味を向けるのも、おそらく楽しみの多い読書になるのではないか。少なくとも本コラムの筆者はそのように感じている。お付き合い願えるだろうか。
本論に入る前に、2つばかり断っておくべきことがある。その1。いま<リョサ(ジョサ)>、<クリオージャ(クリオーリャ)>と不統一な書き方をしたのは、スペイン語の<LL>が片仮名表記される際、リャ行、ジャ行、あるいはヤ行でとまちまちになっているからである。スペイン語話者の発音そのものに地域差があるとも聞く。この件に関して私は門外漢なので、とりあえず多く目にした表記を採用し、Llosa は<リョサ>、criollaは<クリオージャ>でいくことにする。
その2。ムシカ・クリオージャは、ヨーロッパ、アフリカ、アンデスの音楽から影響を受け、ペルーの沿岸地方で生まれた都会的な混血音楽である。バルガス=リョサが作中でムシカ・クリオージャに言及するのは、単なる雰囲気づくりのためではなく、ペルー社会の多様性を描き出すのに欠かせない要素だからだと言えるだろう。
バルガス=リョサは1936年にペルー南部のアレキパで生まれ、1960年代に巻き起こったラテン・アメリカ文学の世界的な<ブーム>を、コロンビア出身のガブリエル・ガルシア=マルケスらと共に牽引した。1990年にはペルー大統領選に出馬し、決選投票でアルベルト・フジモリに敗れた。初期の代表作『緑の家』(1966年)や『ラ・カテドラルでの対話』(1969年)をはじめ、数多くの著作が邦訳されているが、今回まず注目したいのは、1977年に発表されたコミカルな自伝的長篇『フリアとシナリオライター』(河出文庫 野谷文昭訳)である。
主人公マリオは作家志望の18歳。ペルーの首都リマにあるサン・マルコス大学の法学部に籍を置きながら、ラジオ局で働いている。主要な登場人物がほかに2人いて、1人は彼の叔母フリア(叔父の義妹でマリオより14歳年長)、もう1人はラジオ・ドラマの書き手ペドロ・カマーチョ(超人的なライティング・マシーンで孤高の人)である。題名を直訳すると『フリアおばさんとへぼ作家』あたりか。ストーリーの運びには仕掛けがあり、マリオとフリアのロマンスの章、カマーチョ作のドラマの章(脚本ではなく小説スタイル)が交互に出てくる。背景となる時代は1950年代である。
マリオが勤めているのは、<スノッブでコスモポリタンな雰囲気>を持つラジオ・パメリカーノ。同じオーナーが持つラジオ・セントラルには<大衆性と郷土色>が漂い、両局の違いはオンエアする音楽にも現れる。「溢れんばかりのジャズとロック、それにクラシックを少々」「ニューヨークやヨーロッパの最新ヒットをいち早くリマに紹介した」「国産ならば厳選された上で<ワルツ>のレベルの音楽のみが電波に乗った」というのはもちろん前者。後者ではペルー中心のアンデス音楽が幅を利かせ、インディオの大物歌手が公開番組に出演することもあった。ブラジルやカリブ、メキシコ、アルゼンチンの音楽も流された。
おなじみのジャンル名ばかりだが、ここで言う<ワルツ>はヨーロッパ発祥のワルツがラテン・アメリカで土着化したものであることを言い添えておく。ムシカ・クリオージャの代表格であり、民族音楽関係の文章では主にスペイン語の<バルス vals>が使われるので、本稿もそれに倣いたい。バルスはウィンナ・ワルツよりも歯切れが良く、ギターの伴奏で歌われることが多い。<厳選された>という中には、ムシカ・クリオージャの歴史に名を残す歌手兼作曲家、チャブーカ・グランダの録音などが入っていたのではないか。
マリオがフリア叔母さん(最近離婚してボリビアからリマへやってきた)と初めて出会ったのは、ルーチョ叔父さんの家でのこと。リマにはマリオの親戚があちこちにいる。その1人パンクラシオ伯父さんは、親戚内でお祝いがあると箱形の打楽器カホンを1人で叩きまくる筋金入りのペルー音楽愛好家だ。従妹のナンシーはナット・キング・コール、ハリー・ベラフォンテ、フランク・シナトラ、ザビア・クガートなどのレコードをコレクションしている。
ペドロ・カマーチョはボリビアの放送局からスカウトされ、ラジオ・セントラルに雇われた。彼の手になるドラマを1つのぞいてみよう。主役は優雅に暮らす産婦人科医アルベルト・デ・キンテーロスである。
キンテーロスにはリチャードという甥(美男子だが女っ気なし)、その妹のエリアニータ(意外な相手との結婚が急に決まった内気な美人)がいる。エリアニータの結婚式に呼ばれた楽団は、チャチャチャ(キューバ)、メレンゲ(ドミニカ共和国)、クンビア(コロンビア)といった外来のダンス音楽に加え、ペルーのバルス『灰色の雲』(Nube Gris)を演奏した。この曲はバルスの中でも特に有名なものの1つで、ポール・モーリアのオーケストラも『雲に想いを』の邦題で録音しているから、知らず知らずのうちに耳にしていたという人も多いはずだ。私は女性歌手エバ・アイジョン(アイヨン)の歌唱を愛聴している。
そのほかのバルスでは『アイドル』(Idolo)も演奏された。花嫁はこの曲を踊り終えたとき、体をよろめかせ、倒れ込んでしまった。一時は意識も失った。別室でキンテーロスが診察すると、妊娠3、4カ月目であると分かった。それを聞かされた花婿は絶句する。彼の子ではなかったのだ。キンテーロスはまずいことを明かしてしまったと後悔し、バーで一杯飲んで家へ帰ることにした。「書斎に閉じこもって黒い革張りのソファーに身を沈め、モーツァルトにどっぷりと浸りたい気分だった」とここまでは、それほどの大事ではないような感じである。
ところが、外へ出ると、リチャードが酔いつぶれているのに出くわし、今度は彼の面倒を見なくてはならなくなった。家へ連れ帰るタクシーの中で、リチャードは花婿を呪い、ピストルだの殺してやるだのと口にした。その挙げ句に「だって僕は男としてあいつを愛してるんだよ、叔父さん。何がどうなろうとかもうもんか」。ということは兄と妹が…。
甥を寝かしつけたあと、医師はウイスキーのダブルをグラスについでオーディオルームに入り、アルビノーニ、ヴィヴァルディ、スカルラッティの曲を山のようにかけた。「というのも心にのしかかる重苦しい影を忘れるには、しばらくの間ベネチアのバロック的な軽い時を過ごすに限ると思ったからだ」。モーツァルトでもだめな時はヴィヴァルディ、なのか。
カマーチョのラジオ・ドラマは、大体どのシリーズもエキセントリックな登場人物をめぐるブラックな、あるいはドタバタ的なコメディである。その中の1回に<リマの吟遊詩人>と呼ばれる架空の天才音楽家が出てくる。彼の作ったバルス、マリネラ(アフロ系の影響を受けたペルーの伝統舞踊曲)、ポルカ(ヨーロッパ起源の舞曲)の題名はそれぞれ『信心深き人よ、あなたもかつては女だった』『母さん、真っ赤なとさかは危ないよ』『悪童たち』といったもの。いったいどんな曲を想像すればよいのだろう。
カマーチョが次々に作り出す奇談は大人気を博したが、彼はやがて働き過ぎで頭がおかしくなり、別々の番組の登場人物が入り乱れて登場したり、同じ人物がいつの間にか全く違った役割に変わったりして視聴者を憤慨させ、ついに職を失うことになった。年月が流れ、物語の最後でマリオは尾羽打ち枯らしたカマーチョに再会する。しかし、亡霊のようになったかつての人気脚本家は、作家として一本立ちした友人を認識することができなかった。
マリオとフリア叔母さんの話に戻ると、彼らの仲は紆余曲折を経ながら進行した。親戚中の猛反対を押し切ってついに結婚に至り、8年間幸せな時間を過ごしたのち離婚した。最後にひとこと付け加える。バルガス=リョサもまた、若いころに叔母と結婚していたことがある。彼女の名はフリア。本作は彼女に捧げられている。
次に紹介するのは、バルガス=リョサが2013年に書いた長篇『つつましい英雄』(河出書房新社刊 田村さと子訳)。時代設定は2000年代の中頃か。ペルー北部の街ピウラで展開する話が一方にあり、それと1章おきに、首都リマを舞台にした別の話が語られる。そしてその2つ(いずれにも醜い争いが絡む)が最後に合体するという、作者お得意の対位法的な仕立てで語られる小説である。さまざまな音楽が、それぞれの土地と登場人物を描き出す。
ピウラの話からいく。運送会社を経営する苦労人、フェリシト・ヤナケの自宅に脅迫状が届いた。みかじめ料の要求である。フェリシトは小作人だった父が言い残した言葉<けっして誰にも踏みつけにされてはならない>を固く守って生きてきた人間で、要求に応じるつもりはみじんもない。無視していると2通目が愛人の家に来た。オフィスが火事になった。それでもフェリシトは屈服せず、脅迫者に対する警告文を新聞に載せた。金を払うつもりがないこと、彼らを刑務所に送り込むまで断固として立ち向かうことを堂々と宣言したのである。
ここまでのところで出てきた音楽を見てみよう。警察に届けを出したフェリシトが<小便と揚げ物のにおいがする狭い道>を通っているときに聞こえてきたのは、ラジオがボリュームいっぱいに鳴らすサルサ『メレクンベ』。メレクンベはメレンゲとクンビアをミックスしたラテン音楽のリズム名でもあるが、ここではニューヨーク・ラテンのミュージシャン、ジョニー・コロンが作った同名の曲のことだろう。トロンボーンの分厚いサウンドが格好いい。
しかし、フェリシトが愛してやまないのはサルサではなく、ペルーの女性歌手セシリア・バラサ(Cecilia Barraza)の歌声である。最初は偶然ラジオで耳にした。お気に入りのバルス『魂と心と人生』(Alma, Corazon y Vida)が<いまだかつて聞いたことがない優美さ、情感、滑らかさ>で歌われ、たちまち心をわしづかみにされた。集めたCDは自宅と愛人宅の両方にストックしてある。事件で悶々とする時にも彼女の歌に救いを求めた。あるときは心が晴れず、別の時にはいくらか気持ちが軽くなった。
セシリア・バラサの名前は本作の中で10回ほど現れ、歌唱曲『薊(あざみ)と灰』『無垢な愛』『かわいい人』『牡牛は奪う』の名も挙がる。原文は見ていないが、それぞれ<Cardo o Ceniza><Inocente Amor><Carino Bonito><Toro Mata>のことと思われる。おそらくバルガス=リョサの愛聴曲でもあるのだろう。
リマ編は、妻に先立たれた保険会社の社長イスマエル・カレーラが、長く仕えてきたメイドのアルミダと再婚したことから起こる騒動である。イスマエルは80代でアルミダはその38歳年下。イスマエルは素行の悪い双子の息子たちに内緒で婚姻届けを出し、さっさとヨーロッパへ新婚旅行に出かけた。財産を横取りされたと怒る双子は、結婚の証人を務めた重役のリゴベルトを責め立てる。父が<老年性痴呆症>だと証言させて婚姻を無効にしたいのだが、ぴしゃりと拒絶された。
リゴベルトは、15歳になる自分の息子フォンチートに関して悩みがあった。息子が言うには、エディルベルト・トーレスと名乗る正体不明の男がしばしば彼の周辺に現れるとのこと。しかしリゴベルトには、その男が実在するのか、それとも息子が幻覚を見ているのか、あるいは作り話で親をかついでいるのかが分からない。実在するのであれば変質者だろうかとも心配する。
そんなある日の夕食後、リゴベルトは書斎に籠もり、ブラームスのピアノ協奏曲第2番を2つの録音で聴き比べて注意をそちらに振り向けようとした。どちらもオーケストラはベルリン・フィルで、1つは指揮者がアバドで独奏者がポリーニ、もう1つはラトルとブロンフマン。リゴベルトはブロンフマンの演奏を聴きながら両目を潤ませた。ブラームスのせいか、ピアニストのせいか、そのいずれでもなく、息子のことが気になって過度に感じやすくなっていたためか。
リゴベルトは別の時に、やはり書斎で20世紀の作曲家オネゲルのオラトリオ『ダヴィデ王』を聴いた。こちらは助けにならなかった。いつも感動する曲だのに、一瞬たりとも集中できず、レコード・プレイヤーを止めるしかなかった。
ここでピウラ編をちょっと思い出してもらおう。脅迫を受けたフェリシトは大好きなセシリア・バラサの歌を聴いて憂さを晴らそうとした。『フリアとシナリオライター』のキンテーロス医師も、重苦しい影をヴィヴァルディなどで振り払おうと考えた。バルガス=リョサは登場人物の不安な心を、何度も音楽との関連で描いている。
フェリシトの側にも、リゴベルトの側にも、ゴタゴタが続いて起こる。フェリシトの愛人は一時行方不明になった。リゴベルトのボス、イスマエルは新婚旅行から帰ってすぐ、心臓麻痺で亡くなった。推理小説的な要素もあるので詳しく触れるのはよすが、イスマエルと短い結婚生活を送ったアルミダが、実はフェリシトの妻ヘルトゥルディスの妹だったという大きな展開(実は伏線があったのだが、私は初読のとき感づかなかった)があって、2つの筋が撚り合わされる。
音楽絡みの話がもう1つ残っている。これも込み入った事情ゆえ途中は省くが、リゴベルト一家がピウラを訪れることになったときのことである。迎えに出たフェリシトの秘書が彼らにこう言った。「トンデロの曲が流れ、チェ・グア(方言で会話の末尾につける)を使う地へようこそ」。その言葉で分かるように、トンデロはピウラ周辺で育まれた民族舞踊と音楽であり、歌とギターの伴奏に合わせて求愛の仕草が優雅に踊られる。まるで観光協会のうたい文句のような歓迎の言葉だが、作者はそれまで小説全体を覆っていたトラブルが収束し、解決に向かっていることを、トンデロの快い調べに仮託してさりげなく示したかったのではないだろうか。
ここからはおまけ。バルガス=リョサが最後に書いた小説<Le dedico mi silencio>(2023年)は、まだ邦訳が出ていないようだが、ムシカ・クリオージャに正面から取り組んだ作品らしい。題名の意味は<私の沈黙をあなたに捧げる>。英文の書評をいくつか読んで理解した範囲のことをお伝えしよう。
主人公はトーニョ・アスピルクエータという音楽学者。隠れた天才ギタリスト、ラロ・モルフィーノの演奏を聴いて雷に打たれたように感激し、彼の本格的伝記に取りかかるが、その直後にモルフィーノが亡くなってしまう。そこから小説はペルーの音楽と社会の問題に広がっていく…。何しろ未読なので詳しいことは分からないが、『つつましい英雄』のフェリシト・ヤナケが熱愛した実在の女性歌手セシリア・バラサが登場し、重要な役を果たすということだ。(松本泰樹 共同通信記者)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。輸入盤のCD<AFRO-PERUVIAN CLASSCS THE SOUL OF BLACK PERU>は以前から手元にあり、時々聴いていた。チャブーカ・グランダ、セシリア・バラサ、エバ・アイジョンをはじめ、有名どころがだいたい揃っている。
 ポストする
ポストする