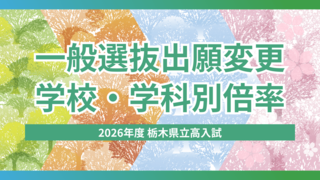大田原市が今春、国の構造改革特区制度で「おおたわら果実酒特区」に認定された。特産酒類の製造事業に関する特区認定は那須町、那須塩原市に続いて県内3例目。地域活性化に向けて規制緩和を活用した取り組みが広がるとともに、特区を生かした那須地区の連携にも期待したい。
特区認定により市は、地域の特産物として指定した市産のナシ、イチゴ、ブルーベリーを原料とした果実酒を市内で製造する場合、年間の最低製造量が6キロリットルから2キロリットルに引き下げられる。通常より少ない製造量でも製造免許の取得が可能となり、市は新たな特産品の開発や、知名度の向上といった効果も見込んでいる。
きっかけは日本酒「旭興」で知られる市内の渡辺酒造だった。「市の特産品を宣伝しきれていない」と感じていた渡辺英憲(わたなべひでのり)社長(51)が市に提案した。現在、規格外品の有効活用などを見据え、果実酒造りの準備を進めている。新しい取り組みが地元のPRとともに、フードロス削減に結び付いてほしい。
農業の振興も特区活用の意義の一つという。新たな特産品を開発しブランド化できれば、原料となる農産物の需要が増え、農家の収益向上につながる-。後継者不足や高齢化が進む中で、市はこのような好循環を描く。
ただ特区を活用した取り組みが、どれだけ広がるかは未知数だ。2017年に本県で初めて認定を受けた「どぶろく・ワイン特区」の那須町は、ワインでの適用例はいまだにないという。担当者は「(原料となる農産物の)生産者が少ないため」とみる。特区の周知の一方で、そもそも特産農産物の生産の維持、拡大は必要不可欠と言える。
特産酒類の製造事業に関する特区認定は全国で133件(3月末時点)。県内では大田原市の認定により、同様の特区が那須地区でそろったことになる。ワイン特区の那須塩原市は25年度、特区を生かすまちづくりとして「サーキュラーエコノミー(循環経済)ビジネスモデル事業」にも乗り出すという。
那須地区3市町のそれぞれの事業が相乗効果を生むと期待される。その一方で、観光業も含めた地域経済の活性化には広域連携も有効だろう。特区を軸に、那須地区が一体となるような取り組みも模索してほしい。
 ポストする
ポストする