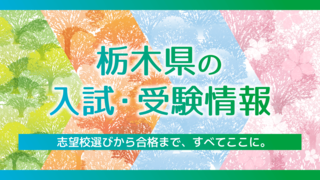渡良瀬遊水地内で増え続けているイノシシは2024年度、生息数が初めて千頭を超えた。県や周辺自治体は捕獲強化に努めているが、年に4、5頭産むという強い繁殖力に追いつけないでいる。
農作物への被害も増えており、今年はかまれてけがをする人も出た。一方で見過ごせないことが他にもある。捕獲に携わる人たちの負担も増していることだ。
捕獲されたイノシシは原則、全頭焼却処分されている。命を無駄にせず、再利用する方策を考える時期に来ているのではないか。
約3300ヘクタールの広大な渡良瀬遊水地は栃木、群馬、茨城、埼玉4県の6市町にまたがる。19年度調査では生息数が205頭だったが、23年度は834頭、24年度は1044頭まで増えた。生息地は遊水地の全域に広がっている。
これに伴い捕獲数も増えている。4県と6市町で構成する渡良瀬遊水地連携捕獲協議会は24年度、わなを用いて遊水地内で90頭捕獲した。周辺自治体も遊水地外で173頭捕獲している。
協議会は本年度から、イノシシの耳に衛星利用測位システム(GPS)発信器を取り付けて行動範囲を調査するなど、効果的な捕獲を目指している。情報通信技術の活用は、省力化のためにもできるだけ進めてほしい。
協議会と6市町は今年、合わせて520頭捕獲を目標としている。ただ、数が増えるほど捕獲に携わる人たちの負担も増す。例えば小山市内の焼却施設では、30キロを超えるイノシシは解体しないと受け付けない。焼却処分のためだけに解体までするという、心理的な負担も大きいという。
県猟友会小山支部の小川亘(おがわわたる)支部長は「イノシシ専門の食肉加工施設が受け入れてくれればありがたい」と話す。
県内で捕獲されたイノシシ肉は原子力災害対策特別措置法で制限され、一部を除いて出荷できない。だが栃木、小山両市で捕獲されたイノシシから放射性物質が検出された例は、12年以降で一度もない。イノシシ肉は高値で流通している。協議会で加工施設の新設、または外注を検討してはどうか。
イノシシは豚熱を媒介するので、慎重な扱いが求められることは理解できる。それだけに公的機関である協議会が介在すれば、流通にも信用度が増すだろう。
 ポストする
ポストする