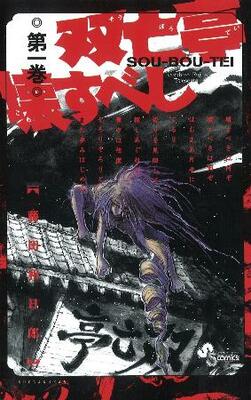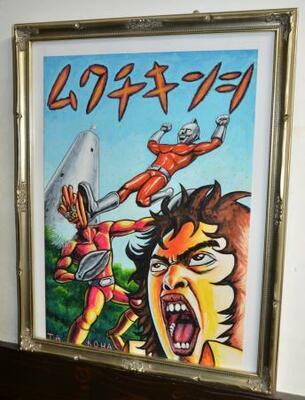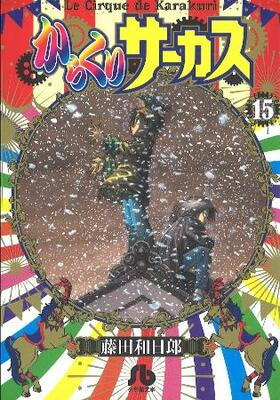1988年のデビュー以来、「うしおととら」「からくりサーカス」「黒博物館 ゴースト アンド レディ」など、数々の作品をほぼ休みなしで生み出してきた“漫豪”藤田和日郎さんの創作の秘密に迫るインタビュー第2弾。今回は、後進の漫画家を数多く輩出する藤田さんの仕事場の謎を探った。
【ふじた・かずひろ】1964年北海道旭川市生まれ。漫画家あさりよしとおさんのアシスタントなどを経て、88年に「連絡船奇譚」でデビュー。代表作の一つ「うしおととら」で小学館漫画賞少年部門受賞。「からくりサーカス」「月光条例」「双亡亭壊すべし」などの少年漫画に加え、「黒博物館」シリーズなどの青年漫画でも知られる。「黒博物館 ゴースト アンド レディ」は2024年、劇団四季でミュージカル化。漫画家を目指す若者に向けた漫画論「読者ハ読ムナ(笑)」も飯田一史さんとの共著で刊行した。
【(1)楽しませる技術を仲間たちに】
●記者 藤田先生の仕事場は、アシスタントの皆さんと慰安旅行に行ったり、飲み会に行ったりと、とても良好な雰囲気ですよね。作品で描かれる熱い友情や仲間同士の連帯にも通じる気がします。
「からくりサーカス」の黒賀村の「人形相撲」のシーンなど、藤田先生やアシスタントの皆さんが楽しんで描いているのが、画面を通して伝わります。「読者ハ読ムナ(笑)」など、新人向けのデビュー指南書まで書かれている。その熱意はどこからくるのでしょうか。
▼藤田 エンターテインメントって人を楽しませることじゃないですか。楽しませ方は流行に左右されるにしても、楽しむ側の喜怒哀楽って、歴史を経てもそんなに大きく変わっていないとも思ってるんですよね。だとすれば、人の感情を動かすのは技術でできると思うんですよ。
技術ならば伝承が可能なわけです。僕が偉いから教えてやるっていうんじゃなくて、35年も人を楽しませることを必死に考えてきましたから、僕は少なくともフツーの人よりはそこに特化された人間になっているはずでしょう? お笑い芸人の方や、芸能人の方と同じようなものです。その技術を仲間に伝えることで、社会とつながっている感覚が実感できるというか。
●記者 社会とつながっている感覚…ですか。
▼藤田 そうです。漫画家が一番怖いことは、中学の時の自分がヘッセの「車輪の下」に対して思ったように、「これは面白くないから、もう読まない。おまえの作品なんかいらないよ」って言われることですよ。不必要なものとして片付けられたくないという強烈な気持ちがある。
アシスタントに技術が伝承できたら役に立てたような感じがするし、そのアシスタントが漫画家になれたら、世間様の役に立てたような感じがするじゃないですか。僕は、漫画に関することしか、ずうずうしく自信を持って話せませんから(笑)。
●記者 藤田先生の仕事場は、他に例がないほど、多数の漫画家を輩出しています。「烈火の炎」の安西信行先生、「金色のガッシュ!!」の雷句誠先生、「ロックは淑女の嗜みでして」の福田宏先生、「あいこら」の井上和郎先生…。どうしてそのようなことが可能なのかと不思議に思っています。
▼藤田 みんな、いいやつなんですよ。そういう人間たちには、世に出て行ってもらいたいじゃないですか。
●記者 連載をしながら、“授業”のようなことをなさるんですか?
▼藤田 いえ(笑)、カリキュラムがあるわけじゃなくて、大事なことを繰り返し伝えるというか。「読者ハ読ムナ(笑)」に書いてあることが全部なんですが、「漫画はキャラクターだぜ」とかを何度も伝える。編集者さんも同じようなことを言いますけど、描き手じゃないので言葉が難しいし、はっきり言わない人も多い。だけど僕はここでみんなと一緒に仕事をして、みんなに漫画家になってもらいたいから具体的なことを言いますからね。
●記者 なるほど。しかし、しつこいようですが、ここまで多くの漫画家を輩出するには、それだけでは説明がつきません。
▼藤田 大事なことは、本人が腑に落ちることなんですよ。例えば、作業中に映画とかを見てしゃべっているとしますわね。そのアシスタントが「バック・トゥ・ザ・フューチャー」が好きだとする。自分ではなかなか思いが至らないけど、話しているうちに「そういえば藤田さんの言ってることってこういうことなんだな」と思う時がくる。そうなった時に、本人が納得できるものを「バック・トゥ・ザ・フューチャー」から持ってこられるんですよ。
●記者 気づきをアシストするような感じですね。
▼藤田 自分の気持ちを言語化するのは、そのものの本質をつかむってことじゃないかと思うんですよね。「言葉に何の力がある…?」って言う人がいるかもしれないけど、これがすごく重要なんですよ。だから新しく入ってきたアシスタントには、自分が何が好きか、どんなところで泣けたのか、どういうことをやりたいのか、なるべく言語化せい!と言っています(笑)。
●記者 だから「ムクチキンシ」なのですね。
▼藤田 あ、いえ(笑)、それは僕が問題のある人間なんで、仲良くしゃべっててもらった方が頭の中がガス抜きできるからでもあるんです。
●記者 そんなそんな(笑)。
▼藤田 仕事場の空気がピリピリして、シーンとしていると、僕の頭の中で嫌なこととかがぐるぐる回って増幅しちゃって、バーン!って爆発しちゃうんです(笑)。
あんまりしゃべるのが得意じゃないやつにはかわいそうなんですが、僕にとっては死活問題で…。僕がボカーン!って爆発して「なんだおまえら!」みたいになったらかわいそうなんで、「自分自身を救うためにも、僕が黙って作業してても仲良く話しててよ、会話しててよ」って要求しています。
アシスタントの採用基準が、絵が描けなくてもいいから、一緒にいて楽しいやつかどうかなんで(笑)、初めにしゃべれるかどうかを重視して採用しています。
【(2)リモートでは足りない】
●記者 先ほど来、藤田先生はご自身のことを「問題のある人間」などとおっしゃっていますが、それは藤田先生が常々おっしゃっている「ストーリーの作り方」に通じる考え方ですね。円の4分の1が欠けたキャラクターに、ストーリーを通して欠けた部分が補われて、丸い円になって、大団円を迎えるという。
▼藤田 面白い映画って、欠けたキャラクターが、物語を通して欠けたものを埋めていくっていう形が多いと思うんです。それって簡単なようだけど、自分が伝えたいことや、好きなことを手の先から出して執筆していくためには、それをなんとなく分かった気になっているだけではだめで、しっかりと言語化されてないといけない。もう本当に必死なんですよ、われわれは(笑)。
●記者 命懸けですよね。
▼藤田 落ち込んでいる人たちを、ちょっと時間つぶしに誘うために、そしてその作品を面白くするために、必死なんです。サバイバルをやっているようなもんで、これ食べられるだろうか、でもこれ食わないと死んじゃうぞというような中で漫画家をやっていますから(笑)。
かっこつけてるわけにはいかない。言語化と言っても、装飾された概念とかそういうものは全然いりませんから(笑)、友達のどんなところが好きだとか、どんなことをされたら悲しいとか、みんなが気に入ってくれるキャラクターはどんなのだろうとか、いち早く言語化して、漫画に描いていかないといけません。
●記者 なるほど。
▼藤田 そのための言語化です。美辞麗句じゃなくて、例えば「魅力的な女性はどういう女性か」みたいなことをみんなでしゃべって、「優しい人? ふざけんな!」みたいな(笑)。「どういう時に、どういうふうに、何をやってくれる子だよ?」って聞きますから(笑)。泥臭い感じですけど、魅力的に感じる部分がそれぞれで、話してみると面白いですよ。
●記者 ここでこうして机を寄せ合っていると、仲間意識が芽生えますよね。そういえば、藤田先生はアナログで執筆する派ですね。
▼藤田 僕が欠けてる人間なんで、リモートのデジタル作画だと欠けに欠けを持ってくるように感じて、足りなすぎるというか…(笑)。
ここでみんなで集まって、アシスタントに「おまえらの力がないと絶対に完成しないんだ!」って言うと、みんなちゃんと「ここ6本指になってますよ」とか「ここ間違ってますよ」って言ってくれるし(笑)、責任感を持ってくれる。
●記者 今もやっぱり夜に描いているんですか?
▼藤田 そうです。だいたい午後5時とかから始めて、朝まで。勤務は週4日ぐらい。眠いのに描いてもらってるからね、アシスタントにはいい思いをさせたいなあ…。
【(3)背伸びしてもらおうじゃないの】
●記者 ここからは、個別の作品についてうかがっていきますが、先に、少年漫画に懸ける思いをうかがいたいと思います。「漫画家本vol.1 藤田和日郎本」には「少年漫画の大前提は正義が悪に勝つ」ということで、「スカッとするような漫画を描きたい」と話されていますが、藤田先生にとって少年漫画とはどういうものですか。
▼藤田 小学館で最初に担当になってくれた武者正昭さんに「少年漫画はいいぞ~。子どもが読めるんだから大人も読める。子どもから大人まで読んでくれるのが少年漫画だぞ」って言われたのを胸に刻んでいます。みんなに楽しんでもらえるもの。そんなふうに読んでもらえたらうれしいって、今もそう思っています。
●記者 少年漫画を描く上で、心がけていることはありますか?
▼藤田 ちょっと脇道にそれますが、「子連れ狼」(小池一夫原作、小島剛夕作画)ってご存じですか。青年漫画なんですけど、父親の拝一刀がこれから復讐の旅に出る。その前に息子の大五郎を連れて行くかどうか、息子のしぐさで判断する場面があるんですね。手まりと日本刀を見せて、どっちを取るかっていう。
●記者 一刀は、日本刀を触ろうとする大五郎に涙を流し、親子で「冥府魔道」へ進む決心をするんですよね。
▼藤田 これって、自分にとっちゃたまらないくらいかっこいいエピソードなんですけど、妻にとってみたら「当たり前」らしいんですよね。「子どもは本物がほしいよ。携帯電話だって、おもちゃと本物なら、本物をいじりたがるじゃん」って。
そう言われて、子どもの心って、背伸びしたがっているんじゃないかと思ったんですよね。子どもは子ども向けに調理されたものじゃなくて、大人っぽい、本物くさいものをかぎ分けるんじゃないかと思う。
それと同じで、「うしおととら」を描いた時も、子どもたちに「背伸びしてもらおうじゃないの」って思っていました。多少難しい言葉があっても、面白そうだと思ったら、読んでくれるんです。
●記者 「うしおととら」は、古い寺の一人息子の「蒼月潮」が、蔵の地下室に「獣の槍」で封印されていた大妖怪「とら」と取引し、他の妖怪を退治する旅に出る物語ですね。潮が獣化してしまうのをヒロインたちが救うなど、全てのキャラクターが魅力的で、少年のみならず少女からも人気を集めました。
▼藤田 この作品には、自分が今まで蓄積してきた、民俗学的なものとか、妖怪的なものとか、怖いシーンもエロいシーンも、全部入れました。その代わり、少年漫画だから絶対に分かりにくくしないぞ、絶対観念的には描かないぞという思いがありました。
●記者 「黒博物館」シリーズなどの青年漫画でも、藤田先生の分かりやすさは貫かれているように思います。
▼藤田 そうだとうれしいですね。そこに関しては、青年漫画と少年漫画の違いをあんまり考えていないかもしれません。本物くさくて面白かったら、きっとみんな読んでくれると思っていますもん。
【(4)終わらせることに命懸け】
●記者 本物くささの追求というのは、キャラクターの名前にも通じていそうです。潮もそうですし、「からくりサーカス」の「加藤鳴海」、「月光条例」の「岩崎月光」、「双亡亭壊すべし」の「凧葉務」…。名字か下の名か、どちらかが親しみやすい名前です。
▼藤田 あれは、ゲームデザイナーの堀井雄二さんが言っていることと同じなんですけど、堀井さんは、いいタイトルの付け方について、聞いた事がある単語と聞いた事がない単語をくっつけるといい、みたいなことを言っているんですね。「ドラゴン」と「クエスト」とか。
それと同じで、あくまで個人的な感覚なんですけど、全部が聞いたことがない名前だと、僕がそのキャラクターの存在を信用できないんですよね。
●記者 リアリティーがないですよね。
▼藤田 漫画って記号じゃないですか。絵で楽しませるわけですから。その記号に、こんな名前の人いるわけないじゃんみたいな記号を重ねるファンタジーは個人的にちょっと避けたくて。
「からくりサーカス」なら加藤鳴海というやつがいて、主人公の「才賀勝」というやつがいて、読者に応援してもらいたいので、その2人があまりにもふわふわした名前だと、僕が信じ切れないんですよ。
●記者 なるほど、だから潮も…。
▼藤田 蒼月潮は、字で言うと、ちょっとかっこつけすぎかなと思います(笑)。ただ、ひらがなの「うしお」にしたら、ちょっとゆっくりした動きの、親近感のある名前だと思ってくれるかな、みたいな。潮の父親の「蒼月紫暮」は、今となってみればやり過ぎたと思っています(笑)。
●記者 「うしおととら」は、読んでいるうちに潮が友達のように思えてきて、ずっと一緒に走っていたい、この世界に熱中していたいと思えるような作品です。他方で「からくりサーカス」は、無数の伏線を張って、完璧に回収していく作品ですよね。どうしてこんなことができるのか、読んでいて不思議なほどでした。
▼藤田 僕は終わらせることに命を懸けるタイプですから(笑)。
●記者 読者の1人としては、情熱的な「うしおととら」も描けるし、緻密な「からくりサーカス」も描けるし、なんでもできるんじゃないかと思ってしまいますが…。
▼藤田 そんなことはないです。一つのやり方をがむしゃらにやっているだけです。
【(5)キャラクターには「花道」がある】
●記者 どちらの作品も没入させられるので、死んでしまうキャラクターが悲しいんですよね。「うしおととら」の秋葉流とか、「からくりサーカス」の阿紫花英良や、ナイフで曲芸をするヴィルマとか…。
▼藤田 読んでくださっているから、反対に聞いちゃいますけど、僕の作品の死ぬキャラクターって、最初から分かりません?
●記者 分かりませんよ(笑)。
▼藤田 僕はみんなに楽しいことを提供するために描いているんで、ショックを受けたり、がっかりして泣いちゃったりしたら本意じゃないんですが、キャラクターには「花道」っていうのがあるんですよ。
●記者 花道ですか?
▼藤田 例えば秋葉流でいうと、最後の場面で「潮ととら、すげー」って言って口をあんぐり開けているっていうのは、やつには似合わない。僕にとっては自分の分身を殺すことになるんですが、死にざまを描くっていうことは、生きざまを描くということ。相打ちであったり敵を倒したり、死に方はさまざまですが、そのキャラクターにとってはそれが一番重要なメッセージなんです。
●記者 死ぬキャラクターは余計、印象に残りますもんね。
▼藤田 阿紫花でいうと、ずっと退屈をしているキャラクターでした。じゃあ、なぜ退屈していたのか。約束がなかったからです。ずっと独りぼっちで、約束するやつがいなかったから。
●記者 なるほど。阿紫花は、ナイフ使いのヴィルマと、最後の戦いが片付いたら結婚する約束をし、「おめえのナイフの的になる毎日なら面白そうだ」と言いますね。
▼藤田 それもそうですし、物語の始めの方で鳴海と約束していますよね。10円で。
●記者 鳴海から「勝をきっと助けてくれ」「しくじったらぶっ飛ばすぜ」と言われ、阿紫花は10円を受け取るんですよね。ファンにとっては熱すぎるシーンです。
▼藤田 金でしか動かなかった阿紫花にとって、10円の約束が、何よりも大切だったんですよ。殺し屋のプロ根性もあって、その約束は破れなかった。自分自身にもちょっと苦笑しながら死んでいくということになるわけです。
ナイフ使いのヴィルマも、姉を信じている病気の弟に、それを証明してやりたくてナイフを投げたのに、的を外してしまった。弟の信頼に応えられなかったということで、この段階でヴィルマは死んでいるとも考えられます。だけど、最後の最後に敵にナイフを命中させた。だからほほ笑んであの世に逝けるのかもしれない。
●記者 その死にざま=生きざまが重要だったんですね。
▼藤田 そういうシーンを描く時は、力が入りますよ。このキャラクターにとって、何が一番大切だったのかと、繰り返し考えます。ですが、忘れてほしくないことは、僕が「厨房」の中でどう料理したかということは、読者にとってはどうでもいいということです。
一生懸命考えていますが、読み取ってねということはありません。面白くて、心に残ってくれたらいい。残らなくてもラーメンを待つ間の暇つぶしになればいい。
●記者 藤田先生らしい美学ですね。何度聞いても感動します。
▼藤田 そりゃあ、もっと記憶に残る漫画を描きたいし、その気合がないと弱くなりますけど、みんなに褒めてもらおうとは思いません。厨房からお出しする料理は、うまいか、まずいかしかない。一生懸命考えて、一生懸命描いて、それが一瞬で消費されて、だけど「うまかった」って、それが一番聞きたいことですもん。
(取材・文=共同通信 川村敦)
インタビューの(下)は6月25日に公開します。
 ポストする
ポストする