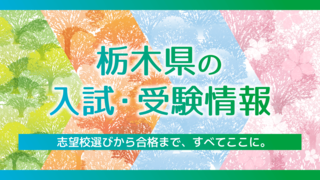小林醸造(鹿沼市上粕尾、小林一三(こばやしいちぞう)社長)が、7月4日で開業1年を迎えた。栃木県内で51年ぶりに誕生した日本酒酒蔵の拠点は、旧上粕尾小体育館を改修した「前日光醸造所」。要望に応じて酒を造る「オーダーメード酒」という新たなビジネスモデルの歩みを2回に分けて振り返り、2年目を展望する。


初年度に対応したオーダーメード酒は約80件。小林社長は「目標は100件を掲げていましたが、ほぼマックスで走り続けてきた。よくここまで来られたというのが正直な気持ちです。不安もあったが、お客さんに喜んでもらえ、励みになった」と手応えを感じている。
前日光醸造所のスタートは異例ずくめだった。始動は寒仕込みとは正反対の真夏。しかも最初にオーダーメードの話が舞い込んだのは、酒販店でも個人の日本酒ファンでもなく、ビッグネームの東武鉄道だった。新型特急「スペーシアX」の開業1周年にふさわしいストーリー性のあるものを車内で提供したいという。小林社長は「最初の仕事があの東武鉄道さんですよ。緊張感でいっぱいでした」と振り返る。
完成した酒の名前は「車窓」。往路は車窓から景色を眺めながら日光観光への期待を高め、帰路では日光観光の余韻に浸る酒となった。
次に挑んだのが、事業承継元の酒蔵・旧池島酒造(大田原市)の「池錦」の復活だ。旧池島酒造元社長の池嶋英哲(いけじまひであき)さん(74)に米麹造りから手ほどきを受け、9月には8年ぶりに「池錦」を形にした。


試飲した池嶋さんは「ちょっと甘いかな」との感想を漏らし、笑いを誘った。池嶋さんは事業承継の際、「池錦」の復活を条件とした訳ではなかったが、前日光醸造所では池島酒造の建物の古材を使うなど、歴史を少しでも残すことにこだわった。小林社長は「大田原市など県北では池錦ファンがいる。そのファンの期待にも応えたかった」。
さらに続いたのは、いずれも「鹿沼秋まつり」をテーマにした、酒類卸の横倉本店(宇都宮市)と酒類小売業の嶋田屋酒店(鹿沼市)からのオーダー。横倉本店は9月、地元町内会代表者も招いたお披露目会を開いた。「町内詰め所には約100本の酒が上がるが、どういう訳か福島の酒ばかりだった。これで地元の酒を奉納できる」。地酒「鹿沼彫刻屋台」復活を喜ぶ町内会関係者の表情は輝いていた。
オーダーメード酒蔵の開業を待ちに待っていたのが塩原温泉のホテル・旅館と居酒屋の有志だった。居酒屋Cava(サヴァ)の小山日生(おやまひろお)さんは酒米も大田原産の有機米を自前で用意し、仕込み水の一部は塩原温泉の飲用水。ホテルや旅館の看板メニューに合う味わいの日本酒を企画した。洗米から段仕込み、ラベル貼りまで自ら行った。小山さんは「インバウンド(訪日客)対応を含めて塩原温泉の新たな観光資源にしたい」と、小売りにも乗り出す意向だ。


小林社長は9月末、鹿沼商工会議所の事業に参加し、パリの日本飲料交流イベント「サロン・デュ・サケ」に出展。イベントをきっかけに、オランダを拠点に日本酒を扱う流通業者の「OtenbaSake」がオーダーメード酒に興味を示し、発注した。12月には代表の藤原康晴(ふじわらやすはる)さんが前日光醸造所を訪れ、試飲しながらオーダーを決めた。今ではスパークリング酒まで注文している。
藤原社長はゼロから参入した小林醸造の存在を知り、「新たに日本酒造りを始めるという意気込みに触れ、何か一緒にできないかという気持ちになった」と語った。欧州から日本酒ファンの送客にも取り組む考えだ。
日本青年会議所酒類部会の有志が今年6月、オリジナル銘柄を立ち上げるため前日光醸造所を訪れた。商品は単発ではなく、継続して全国の酒販店に広がり、まとまったロットになる。小林社長は開業2年目に入り、経営安定化の一つの要にする考えだ。

オーダーメード80件は、企業の周年事業の記念品、酒販店、飲食店、食品関連会社のオリジナル品、生徒が酒米作りに挑んだ鹿沼南高の日本酒など多彩だ。
ある酒造ベンチャー関係者は「お酒は地域のメディアだ」と評する。お酒が土地の名刺代わりに日本や世界中に旅立ってくれる存在となり、お酒を飲んでおいしければ、それが造られた場所に行ってみたくなるという考えだ。
確かに、同じベンチャーである小林醸造の「オーダーメード酒」の1年を振り返ると、改めて自分の地元を見詰め直したり、いろいろなアイデアが生まれたりするきっかけになり、可能性や話題性、コミュニケーションを広げてくれるメディアのような存在と感じる。
(伊藤一之(いとうかつゆき))

 ポストする
ポストする