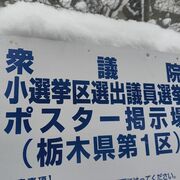参院選が始まり、県内でも街頭演説や選挙カーによる「連呼」が見られる。だが選挙戦の主役は、今や交流サイト(SNS)になりつつある。候補者や陣営は1日に何度もSNSを更新し、自らの主張の浸透に力を入れている。街頭活動はせず、選挙運動はSNSだけという候補者もいるほどだ。
ただ、SNSは候補者だけの発信ツールではない。誰もがいつでも、世界に向けて発信できる。その中には正確な情報もあれば、怪しい偽情報もある。それが候補者に向けられることもある。
選挙におけるSNSの規制強化を求める声もあるが、慎重でありたい。規制だらけの言論空間がいいとは思えない。健全な言論空間をどう守るか、民主主義が試されている。
昨年の兵庫県知事選では、SNSが有権者の投票行動に強い影響を与えたとされている。特定の候補者に関係する偽情報が出回ったばかりか、自らの当選を目標としない「2馬力選挙」も出現。誹謗(ひぼう)中傷も横行し、自殺者まで出てしまった。
SNSは人と人をつながりやすくする半面、同じ思考の持ち主の主張が優先的に表示される特性がある。それが社会の分断を生みかねないことを理解しておきたい。
下野新聞社が参院選を前にSNS上で行ったアンケートによると、今回の選挙で投票先を選ぶのにSNSを参考にするとした人は44%だった。しかし偽情報の疑いがあるとしても、正確な情報を確認しないという人も30%いた。
今、パソコンやスマートフォンの画面で見ている情報は本当に正しいのか。デマに踊らされてはいないか。有権者は複数の情報源に当たり、確認する習慣を身につけたい。
アンケートでは、選挙におけるSNS発信の規制強化に肯定的なのが62%、否定的なのが34%という結果もあった。高齢者ほど規制強化に肯定的で、若年層は否定的という傾向が見られた。
偽情報の氾濫や誹謗中傷が氾濫するSNSに、業を煮やす気持ちも分かる。それでも表現の自由の観点から、当局による規制は慎重であるべきだと考える。
本紙を含む各メディアの役割も問われている。真偽不明の情報が拡散していれば積極的にファクトチェックに乗り出し、有権者の判断に資する情報発信に努めたい。
 ポストする
ポストする