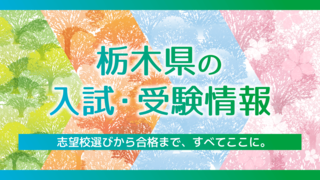「私たちのオーダーメード酒なり、酒造り体験は究極のエンターテインメントだと思っている」。開業1年を控えた6月5日、今季の酒造りを終える「甑(こしき)倒し」の日、小林一三(こばやしいちぞう)社長(51)はオーダーに訪れた日本青年会議所酒類部会の有志に説明した。

初年度にオーダーメード酒を注文した顧客のうち約半数は、蒸し米の放冷、櫂(かい)棒でもろみをかき混ぜる「留添え」などの酒造り体験を味わった。自分の希望する味わいの酒を一部でも自分の手を掛けることで、世界に一つしかない「オンリーワンの酒」になる。体験した人たち同士で互いに写真を撮り合ったり、社長の酒造り体験の様子を動画撮影して広報に活用したりする企業もあった。
小林社長は「酒造り体験では写真撮影に協力し、最大限、体験者が『映え』るようにする。細かく対応することで、数多くの方に発信してもらい、オーダーメード酒の魅力が広がるようにしたい」と狙いを話す。
観光面でも初年度から種をまいた。鹿沼商工会議所の協力を得て国の補助金を活用。昨年11月には旅行会社の東武トップツアーズとインバウンド向けの酒造り体験モニターツアーを実施した。参加した男女4人は在日外国人だったが、貴重な体験に目を丸くしていた。酒蔵を見学したことはあったが、蒸した熱い酒米に触れたり、櫂(かい)入れをしたりするのは初めて。「日本酒造りの大変さが分かり、日本酒の価値が高まった」と喜んだ。

一行は古峰神社の宿坊に泊まり、鹿沼伝統の木工芸の組子作りを体験するなど伝統文化、精進料理など地元食も堪能。「スペシャルな内容だった」と満足した様子だった。際立った観光資源に乏しい鹿沼エリアだが、日本酒造り体験というコンテンツが加わり、観光振興への期待も高まりつつある。2年目はインバウンド向けツアーの商品化に動く方針だ。
酒造り体験だけを受け入れる有料サービスは、年明けからホームページで募集したものの、参加者はなかった。2年目はこの受け入れを強化する。
前日光醸造所では酒造り体験の前、旧校舎の教室で、日本酒造りの特徴や工程など基本的な座学の講義が行われる。参加者は子どもたちが学んだ木製の机といすに座って酒造りを学び、小学校時代へ“タイムスリップ”という貴重な体験も話の種になる。
オーダーメード酒は銘柄「蓬莱泉」などで有名な関谷醸造(愛知県豊田市)が新しいビジネスモデルとして確立した「ほうらいせん吟醸工房」のやり方をそのまま再現した。しかし酒造り体験のメニューとなると、小林社長は「前日光醸造所は進化し、独自のスタイルになっている」と説明する。
ほうらいせん吟醸工房はオーダー数が多いこともあり、体験できる工程は蒸し米の放冷など段仕込みの一部に限られ、後は工場見学で終了する。しかし前日光醸造所はこれに加え、洗米、瓶詰め、レッテル貼りの体験も可能になる。

2年目は冬期、この体験をさらに進化させる方針。酒造りを象徴する作業といえば、米麹(こうじ)づくりのため蒸し米に容器を振って麹菌を付けていく「種切(たねきり)」作業を思い浮かぶ人も少なくないだろう。体験メニューにこの作業を加える試みだ。さすがに前日光醸造所の麹室は使えないが、みそ造りを行う市内の農産加工施設の麹室を使っての種切体験を実現させる。小林社長は「日本酒を飲まない人にも体験してもらうことで、日本酒の門戸を広げ、飲んでみようかと思えるような仕組みをつくり、人を呼び込みたい」とPRする。
酒造りのチャレンジも続く。製造部長を務める寺澤圭一(てらさわけいいち)さん(52)は東北の酒蔵で杜氏(とうじ)を務め、ほうらいせん吟醸工房でも2年近く、オーダーメード酒造りを修業した。200リットルタンクを自在に操り、大吟醸から純米酒、さらには山廃、白麹、スパークリングまで対応する。ただ初年度は初めての場所、環境での酒造りだったため、冬期、日々の天候変化による対応、管理が十分でなかった点があったという。「この1年、醸造所内セクションごとの温度、湿度のデータを取った。2年目はこのデータを生かし、ブラッシュアップしたい。どんな要望は来ても応えられるよう引き出しを増やし、気を引き締めていきたい」と力を込める。

大卒1年目でオーダーメード酒造りに携わった山脇健太郎(やまわきけんたろう)さん(23)は何事も初体験だったため、「クレームがなくよかった」と安堵(あんど)した様子。大学では天然酵母などの研究を行っており、「もし許されるなら新たな酵母造りをやってみたい」と夢を語る。小林社長も若い優秀な人材だけにモチベーションを高めるためにも応援する考えだ。
さまざまな取り組みに挑んだ初年度の小林醸造前日光醸造所。小林社長は「このような施設は他にはない。唯一無二の体験を提供したい」と呼び掛ける。どこまで進化し、あの山あいの地にどう人を引き付けるのか、2年目も目が離せない。
(伊藤一之)

 ポストする
ポストする