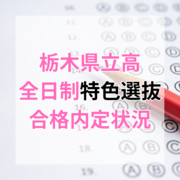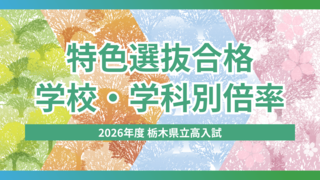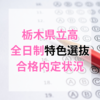激しいせきが長期間続く急性気道感染症「百日ぜき」が県内で猛威を振るっている。今年の累計患者数は今月20日時点で既に942人と昨年(12人)の約79倍に上り、異例の感染拡大が続いている。
全国の累計患者数も同日までに5万2490人と4千人余りだった昨年の約13倍となり、昨年までで最多だった19年の1万6845人の3倍超となっている。
乳児が感染すると重症化する可能性があり、兵庫県など各地で死亡例も出ている。乳児には予防の効果があるとされるワクチンの定期接種が推奨される一方、大人も手洗いやマスクの着用など感染防止対策を徹底させたい。
百日ぜきは「百日ぜき菌」が原因で、飛沫(ひまつ)や接触により広がる。7~10日の潜伏期間を経て風邪の症状が現れ、次第にせきが強くなる。成人は抗菌薬投与などで症状の軽減を図れる。しかし乳児はけいれんや呼吸停止などの症状が出て、肺炎や脳症で死亡する例もある。
県によると、今月20日までに罹患(りかん)した計942人のうち、年齢階級別の最多は10~14歳の487人(51・7%)で19歳以下の若年層が全体の9割以上を占めた。乳児を含む4歳以下は31人(3・3%)だった。30~40代も計59人(6・3%)と報告が増えている。
全国的な流行の要因として、新型コロナ禍で感染予防対策が徹底された際、多くの人が百日ぜきの病原体に触れる機会がなかった。このため以前より免疫力が低下し、感染拡大につながったとされる。
乳児の予防には5種混合ワクチンが有効といい、専門家らは公費での定期接種対象となる生後2カ月に達したら速やかに接種することを勧める。乳児が未接種のまま感染すると重症化しやすいという。
乳幼児期にワクチンを接種しても、月日とともに効果は次第に薄れ、感染の可能性は高まる。日本小児科学会は、就学前と11~12歳での追加接種も推奨している。かかりつけ医などとよく相談し検討してほしい。
学校や職場で感染した人が、自宅などで重症化リスクの高い人にうつすことがないよう細心の注意を払うべきだ。うがいや手指消毒など感染症対策の基本を徹底させ、長引くせきなど不調を感じたら医療機関を早めに受診し検査や治療を受ける必要がある。
 ポストする
ポストする