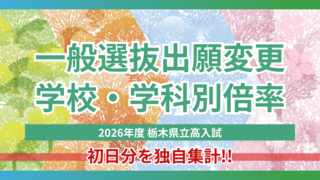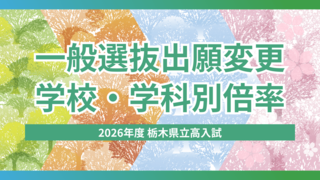JR西那須野駅のほど近く、栃木県那須塩原市永田町の住宅や商店などが立ち並ぶ市街地の一角に、スギの木が1本だけ亭々とそびえている。根元にはほこらや鳥居が祭られ、特別な存在であることがうかがえる。周囲の景色とは一線を画す「一本杉」の由縁を探ってみた。
一本杉は、同駅から北西に350メートルほど離れた二つの通りの交差点に立つ。高さ15メートル強。その脇を車が盛んに行き交う。
今でこそ整備された街並みが広がるが、この一帯は江戸時代、那須野ケ原の広大な原野だったという。
西那須野町史などによると、那須野ケ原を付近の人々が移動するための目印として複数のスギの木が植えられた。その大半が野火で焼けたり、枯れたりした結果、この1本だけが残ったとされる。
一本杉周辺は1881年、那須野ケ原開拓で元勲大山巌(おおやまいわお)と西郷隆盛(さいごうたかもり)の実弟・西郷従道(さいごうじゅうどう)による農場「加治屋開墾場」が開設された。2人が那須野ケ原で狩猟をした際、一本杉の木陰で弁当を食べたという逸話も残る。
那須野が原博物館の坂本菜月(さかもとなつき)学芸員は「人々が方角などを判断する材料にしていたのではないか」と推測。「原野の時代から1本だけがそのまま残っており、大切にされてきたのだろう」と話す。
1955年ごろ、地域住民らが一本杉をご神木とした稲荷神社を祭ったことも、その存在の大きさを裏付ける。現在は市指定天然記念物になっており、かつては保存会も活動していた。
一本杉から数十メートルの通り沿いでスクールショップを営む赤羽善道(あかばねよしみち)さん(82)も愛着を持つ一人。幼い頃から一本杉を見て育ち、約40年前には「一本杉の詩」を自作して歌にもなった。
「この地域の移り変わりをずっと見守ってきたシンボル。これからも残ってほしい」と願っている。

 ポストする
ポストする