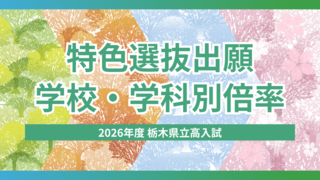国際医療福祉大は今年、大田原市北金丸で開学し、30周年を迎えた。大田原キャンパスからは約2万人が巣立ち、医療福祉の専門職が県内をはじめ各地で共生社会を支えている。少子高齢化は進む。時代に応える人材の養成に一層、期待したい。
大学は1995年、保健学部(現保健医療学部)の看護、理学療法、作業療法、言語聴覚、放射線・情報科学の5学科でスタートした。大学によると、医師以外で診療・治療に携わる専門職「コメディカル」を養成する国内初の総合大学。少子高齢化や共生社会を見越した先駆けと言えよう。
現在は全国5キャンパスに11学部28学科を構え、2017年には成田キャンパスに医学部を設けており、医療福祉分野のほぼ全てをカバーする。大田原キャンパスも3学部9学科となった。30年間の成長を物語っている。
「チーム医療・チームケア」を臨床現場で実践的に学べることが特長だ。多くの付属病院や関連施設があり、教員にも医師やコメディカルがいる。分野の異なる学生同士がチームで研究や実習に当たることができる。卒業生には即戦力の活躍を強く願う。
大学による地域への波及効果も大きい。大田原キャンパスには約4千人が在籍し学生生活を送っている。大田原市の人口は20年間で約1万人減り、現在7万人を割り込む。学生が消費活動や働く力などで継続的に寄与しており、活性化の効果は計り知れない。
市の介護予防などの事業に、大学の人材が関わっている。一方、市もさまざまな支援策を大学に講じてきた。連携を継続・強化し、大学、市、市民の受けるプラス面を広げてほしい。
少子化は止まらず、学生の確保は各大学共通の課題となっている。大学の魅力を知ってもらう取り組みは重要だが、教育内容の充実が大切だろう。大田原にこの4月、臨床検査技師を養成する「医学検査学科」を新設した。こうした先のニーズを見据えた歩みが肝要である。
建学の精神は、病める人も障害のある人も健常な人も認め合って暮らせる「共に生きる社会」の実現である。留学生の受け入れなどを通じ、アジアの医療福祉のリーダーを養成することも目標だ。実現に向け、医療福祉の総合大学の機能強化を望みたい。
 ポストする
ポストする