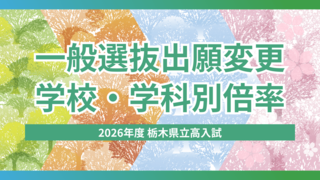太平洋戦争などの戦没者遺族が県内各市町や地区単位で組織する遺族会は過去10年間で140団体から2割弱減少し、117団体となったことが12日までに、下野新聞社が全25市町に実施したアンケートで分かった。戦後80年が経過し、会員の高齢化や後継者不足を背景に解散・休会が相次いでいる。塩谷町ではなくなった。識者は遺族会の縮小を受け止めた上で、慰霊や相互扶助から戦争の記憶継承へ役割を転換していく重要性を指摘している。
遺族会は戦後、戦没者の慰霊や遺族生活を支えることなどを目的として、全国の自治体や自治体内の地区単位で創設された。
アンケートは6月に実施し、全25市町から回答を得た。地区単位では2015年以降、大田原市で5団体、宇都宮市で4団体、日光市で3団体、栃木、真岡、那須塩原、那須の4市町で各2団体が解散した。

足利市は3団体が会長などの後継が決まらずに休会中。市町単位では塩谷町遺族会が昨年4月に解散し、町に遺族会がなくなった。
解散理由は「会員の高齢化」が最多で、高齢化に伴う「後継者不足」「会員数減少」も複数市町から挙がった。県遺族連合会によると、県内遺族会の総会員数はピークだった昭和40年代は約4万人いたが、現在は約5千人に減っており、団体の存続にまで影響している形だ。
解散した遺族会の会員には「県の遺族会の活動等を案内する」(宇都宮市)との対応を取る自治体もあった。解散・休会まで至っていない団体も会員数減少が活動に影を落としている。
アンケートでは「会長のみで(運営業務を)持ちこたえてもらっている」(茂木町)、「役員改選に困難が生じたため遺族会規則を変更した」(高根沢町)などと対応に苦慮する声が相次いだ。
戦没者慰霊に詳しい皇学館大の中山郁(なかやまかおる)教授(宗教学)は、遺族の減少により相互扶助の役割なども薄まっていることから、縮小は「想定の流れ」と説明する。
県内では県遺族連合会が昨年青年部を発会させて語り部活動を本格化させるなど、戦禍の記憶を次世代に引き継ぐ試みが模索されている。中山教授は「各地域で戦争をどのようなものとして受け止めるか考えた上で、継承活動などに落とし込み、取り組んでいけるかが存続の分かれ道となるのではないか」と話した。
「せめて慰霊祭だけでも…」
戦後80年を迎え、会員の高齢化や減少に伴って、解散・休会が相次いでいる県内の遺族会。慰霊祭存続への葛藤を抱え、解散後の忠霊塔の管理を不安視する関係者もいる。一部の団体は小中学生向けの戦争講話や、慰霊祭への招待など次世代への継承に向けた活動に力を入れ始めた。戦争を知らない若い世代に惨禍を伝え、平和の尊さを考えてもらう役割を考えつつある。
「時代の流れだが、できれば続けたかった」。昨年4月に解散した塩谷町遺族会で最後の会長を務めた柿沼一夫(かきぬまかずお)さん(86)は無念さをにじませる。
残り:約 813文字/全文:2071文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする