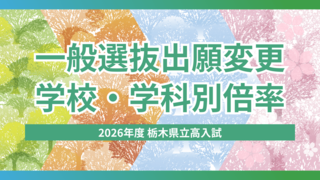新型コロナウイルス対策で実施された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)を受けた企業の倒産(負債額1千万円以上)が、今年6月までの約5年間で計2272社に上った。県内企業は68社だった。大半は中小といい、支援で経営を維持したものの資金繰りに行き詰まったことなどが理由とみられる。
日銀利上げによる金利上昇や物価高に伴う調達経費の増加で企業は苦境に立たされている。地域経済への影響を最小限に食い止めるためにも、国や県、金融機関はゼロゼロ融資を受けた後も経営が苦しい企業への効果的な支援策に努めるべきだ。
帝国データバンクによると、ゼロゼロ融資を受けた企業の倒産は2023年に計652社、24年は計735社に増えた。今年1~6月は計316社で、同社は「下半期も300社前後の水準で推移しそうだ」と見込む。
今年1~6月の業種別では小売業が66社と最多。建設業62社、製造業60社と続く。小売業の中では特に飲食店が目立ち、コメをはじめとした食品の値上がりが収益を圧迫したとみられる。
ゼロゼロ融資は、コロナ禍で売り上げが減った中小企業や個人事業主の資金繰りを支援するため、20年3月に始まった制度。国融資は無利子期間を最長3年に設定し、民間金融機関は21年3月末、政府系金融機関は22年9月末に受け付けを終了した。
業績回復に努める企業などを支えた一方、返済時期に入り対応できないケースが相次ぐのではという指摘は当初からあった。懸念が現実のものとなりつつあると言える。
地方にとって中小企業は、地域経済や雇用に欠かせない。経営難の企業は、新たな事業展開や取引先の新規開拓を目指すなど自助努力に励むことが求められる。国をはじめ県や市町、商工団体は、可能な財政援助や経営支援などきめ細かなサポート体制を一体となって構築したい。
ゼロゼロ融資に関しては、貸した金融機関側の姿勢も問われよう。融資の利子などは公金で賄われ、結果的にリスクのない状況で貸出金を増やしてきた。債務者から返済されなければ最終的に税金で穴埋めされ、国民が負担することになる。貸した側の責務として、融資先の事業継続に向けた丁寧な相談対応や提案などプロ意識に徹するべきだ。
 ポストする
ポストする