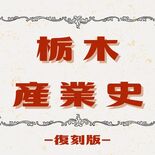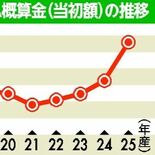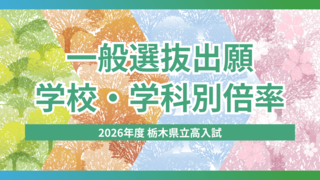2005年に下野新聞紙面で連載した「戦後60年 とちぎ産業史」。第2次世界大戦後、栃木県内の産業や企業はどんな盛衰のドラマを繰り広げたのか-。今年は戦後80年。関係者の証言などを収めた20年前の記事を通して、あらためて戦後の歩みを振り返ります(9月7日まで毎日配信予定)。記事一覧はこちら。
【戦後60年 とちぎ産業史】稲作(上)
終戦のその年、日本は大凶作に見舞われた。コメ作りは、壊滅的な状態だった。
「肥料などの資材はないし、戦争で人手もなかった。それに天候も不順だった」。県内農業を見続けてきた県農協中央会会長の豊田計氏(78)は振り返った。陸軍士官学校に在籍していた当時十八歳の豊田氏も、地元に戻ってきたのは九月になってからだった。
一九四五年の本県のコメ収穫量は約十六万トン。前年より二割少なかった。全国では三割減の五百九十万トンに落ち込んだ。
当時、政府は農家に対してコメをはじめとする食糧の供出を求めていた。しかし、各市町村ともコメの供出量を確保することは困難を極めた。
高根沢町史によると、この年の十一月、旧阿久津村の阿久津登村長が、供出を要請する当時の相馬敏夫知事に窮状を訴えている。「本村は空襲災害農村で、七月下旬の水田除草ができず、生育上甚大な影響が出た。稲の出穂期に台風災害にあい、前年比で四割減収が予想される」
さらに「敗戦後における供出意欲の減退が著しい」とも述べている。敗戦は、農民の労働意欲をそいでいた。
残り:約 2130文字/全文:2787文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする