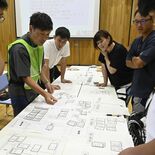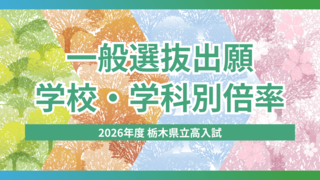災害時に断水した際、住民の生活用水を確保するために民間所有の井戸を「災害用井戸」に登録する制度を県内8市町が導入していることが30日までに、下野新聞社のまとめで分かった。計1042件の井戸が登録され、各市町とも非常時の水源として有効活用できると評価している。2024年1月の能登半島地震では、断水が長期化した被災地区もあったことから、8市町以外でも複数の市町で導入を検討する動きが出ている。9月1日は防災の日。
災害用井戸は、断水で水道が復旧するまでの間、応急用の生活用水や飲料水を地域住民に無料で提供する。個人や企業のほか、自治会や行政区で所有・管理しているケースもある。
震災や水道管の破損といった有事の際は、登録した住民や企業が自発的に開放する場合もあるが、制度があると住民がすぐに井戸の場所を知ることができ、スムーズな活用につながるとされる。
県内では宇都宮、栃木、小山、真岡、矢板、那須塩原、茂木、野木の8市町に登録制度がある。8市町ともに生活用水としての活用を想定している。飲料水は給水車や備蓄で対応できることから、不足になりがちな生活用水に絞っている。
登録している井戸の件数は真岡が最多の671件。東日本大震災後、自治会を通じて市内全域で登録を促したという。市の担当者は「災害時の共助の点で、行政側としては心強い。備えの安心感がある」と話す。
小山市は147件、栃木市99件、宇都宮市91件、那須塩原市16件、野木町6件、茂木町1件が登録されている。
新たに7月から制度を始めた矢板市は、県内で初めて水質検査の費用を補助する内容も盛り込んだ。現状の登録は11件で、担当者は「想定した10件が早々に集まり、市民の防災意識の高さを実感した。20件、30件と増やしたい」と意気込む。
井戸の場所は栃木、矢板、野木の各市町が自治体ホームページで公表している。小山、那須塩原市は地区までを公表し、有事に限って地域住民へ周知する。他の市町は、個人情報保護や自治会内のみでの使用を想定していることなどを理由に公開していない。
佐野、日光市、市貝町は登録制度の導入に向けて検討しているほか、「導入している自治体に話を聞いている」「能登半島地震を踏まえ制度が必要と認識している」などと前向きに捉えている自治体も相次ぐ。
■地域住民が積極的に協力 「備えに役立てて」
残り:約 1038文字/全文:2061文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする