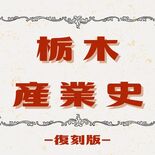2005年に下野新聞紙面で連載した「戦後60年 とちぎ産業史」。第2次世界大戦後、栃木県内の産業や企業はどんな盛衰のドラマを繰り広げたのか-。今年は戦後80年。関係者の証言などを収めた20年前の記事を通して、あらためて戦後の歩みを振り返ります(9月7日まで毎日配信予定)。記事一覧はこちら。
【戦後60年 とちぎ産業史】百貨店(上)
宇都宮市江野町の繁華街、オリオン通りの一角に、工事中の建物のように壁などを目隠しした巨大な空き店舗がある。今年七月に閉店となった若者向けファッション専門店「109宇都宮」の跡地。同店は二〇〇一年秋に華々しくオープンしたものの、開店当初から毎年赤字が続き、わずか四年で撤退を余儀なくされた。
この場所では、一九七四年に地元資本の「山崎百貨店」が閉店した後、月賦販売の「ミドリ屋」、若者向けファッションの「アムス宇都宮店」、そして「109宇都宮」と、出店と撤退、業態変更が繰り返されてきた。
大通りやオリオン通りを軸とした同市中心部は、六〇-八〇年代に「百貨店激戦地域」と呼ばれ活況を呈したが、バブル経済崩壊後は客足が激減し、大型店の撤退などによる空洞化が深刻な問題となっている。「109宇都宮」の跡地は、そうした歴史と現状を体現している。
「かつて『宮(宇都宮)に行くべ』を合言葉に、県内だけでなく遠く水戸市内からも多くの人たちが集まってきた時代があった。そのシンボル的存在が百貨店だった」。中心部活性化に取り組んでいる宇都宮オリオン通り商店街振興組合理事長の入江操さん(69)は、そう言って遠くを見詰める表情になった。
「読んで字のごとく、百貨店は百貨、つまりどんな物も扱う。戦前、戦中の物不足を経験した人にとって、あらゆる商品がそろい、飾り付けもきれいな百貨店はあこがれの対象。買い物することがステータスだったんだ」
残り:約 1941文字/全文:2742文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする