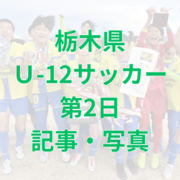コメ価格の高止まりは、2025年産の新米が出回った後も続く公算が大きくなった。JAグループがコメ農家に前払いする「概算金」が、全国各地で前年より増額しているためだ。
本県も例外ではない。JA全農とちぎが県内各JAに提示した概算金は、コシヒカリの1等米で前年比72%増の60キロ当たり2万8千円。昨年に続いて2年連続で最高額を更新し、増加幅も最高となった。とちぎの星、なすひかりといった本県独自の銘柄米も軒並み大幅増となっている。
生産コストの高騰にあえぐ農家にとっては朗報となろう。だが物価高に悩む消費者は、一段と苦しくなりそうだ。価格の高止まりが続けば、コメ離れが進む懸念もある。政府は価格の安定を最優先に手を打つべきだ。
コメ価格の高止まりの背景には、生産コスト上昇以外にも複合的な理由がある。近年の猛暑により一部地域で作柄が悪化していることや、農業者の高齢化に伴い生産人口が減少してすぐに増産に転じられない事情もある。耕作放棄地はすぐに農地へ戻せない。
生産者からコメを買い求めるのは、JAグループだけではない。外食や流通大手、商社なども参入し、競争は激化している。宇都宮大の小川真如(おがわまさゆき)助教(農業経済学)は、新米の店頭販売価格は5キロ当たり4200~6500円になると予想している。
予想の上限まで店頭価格が高騰すれば、家計の圧迫だけでは済まされないだろう。価格転嫁が難しい中小飲食店の経営にも深刻な影響をもたらし、学校給食費の値上げにもつながりかねない。
政府は長年の減反政策を改めてコメ増産に政策転換したが、すぐに効果は期待できない。備蓄米の大量放出が一段落した今、政府に価格をコントロールする手段は限られている。早急に対策を示すべきだ。
同時に、農家の生産意欲をそぐようなことは避けなければならない。米価が一定水準を下回った場合、差額を政府が補填(ほてん)する制度も検討すべきだ。
生産者と消費者の間に立つ政府は、相反するような難しい課題を突きつけられているようにも見える。当面できることは何なのか。仮に輸入米に大きく頼るようなことになれば、農政への信頼は失墜するだろう。
 ポストする
ポストする